Aloysio de Alencar Pintoのページ
Aloysio de Alencar Pintoについて
アロイジウ・ジ・アレンカール・ピントゥ Aloysio de Alencar Pinto は1911年2月3日、セアラー州フォルタレザに生まれた(出生記録が間違って1912年と登録されてしまったので、1912年生まれとする資料も多い)。彼の父Júlio Pinto do Carmoは映画館を経営していたが、アロイジウ・ジ・アレンカール・ピントゥが5歳の時にに亡くなってしまい、しばらく一家は経済的に困窮したとのこと。彼は幼い時から見よう見まねでピアノを弾き、7歳の時から叔母にピアノや楽典を習った。1920年から1921年にかけて約一年間、従姉妹のいるリオデジャネイロに住んだ。当時の彼は放課後に毎日サッカーをしているスポーツ少年であったが、ピアノの練習も続けていて、時々市内中心部の楽器店に行ってみると、店内でエルネスト・ナザレがピアノを弾いているのを見かけたとのことである。
1921年にフォルタレザに戻り、その翌年にはピアノの演奏会に出演してショパンやグリーグなどのピアノ曲を演奏した。14歳の時には歌曲《君の歌、タンゴ O teu cantor, Tango》を作曲している。1928年、ロシアのピアニストのニコライ・オルロフが来伯した際にピントゥはレッスンを受けた。その後セアラ大学で法律を勉強し、1932年に法学士の学位を得ている。間もなく再びリオデジャネイロに移り、国立音楽学校 Instituto Nacional de Música に入学し、バホッゾ・ネットらに師事した。またこの頃にヴィラ=ロボスやミニョーネと知り合いになった。1936年には国立音楽学校の卒業に際して金メダルを授与された。
1937年、ピントゥはフランスに留学し、マルグリット・ロン、ロベール・カサドシュ、ナディア・ブーランジェに師事した。
1939年にブラジルに帰国すると、ピントゥはピアニストとして活動した。また、フランス留学中に知り合ったフランス人のLeone Maret-Miraultと1940年にフォルタレザで結婚し、2人の子どもをもうけた。
1953年からはリオデジャネイロに住んだ。ピアニストとしてブラジル国内に加えて、フランス、スペイン、ポルトガル、アルゼンチン、ウルグアイで演奏会を催した。1963年にはナザレ生誕百周年を記念して、ナザレのピアノ曲12曲を録音した。またピアノ教師としてJacques Klein、Gerardo Parente、Irany Lemeらを育てた。更に音楽学者としてブラジル民族音楽の研究を行い、1965年にはブラジル民族舞踊団を引き連れてフランス各地で公演を行い成功を収め、パリ市勲章を授与された。1972-1988年にかけてはブラジル各地の民族音楽を録音したLPシリーズ『ブラジル民族音楽の音のドキュメンタリー Documentários Sonoros do Folclore Brasileiro』を制作し、計LP46枚をリリースした。また、20世紀初めのサイレント映画全盛時代に映画館のピアノ弾きをしていた「ピアネイロ pianeiro」達が活躍した頃の音楽を復刻する2枚組LP『ピアネイロ達 Os pianeiros』を1986年に制作し、自ら数曲のピアノ曲を録音し、解説文を執筆した。(ブラジルにおける「ピアニスト(ポルトガル語ではピアニスタ)」と「ピアネイロ」の違いは、下記のピアノ曲CD・LPの一番下の説明をお読み下さい。)
2006年にはリオデジャネイロ州連邦大学の名誉博士号を授与された。
2007年10月6日、リオデジャネイロで亡くなった。
アロイジウ・ジ・アレンカール・ピントゥの作品では、歌曲《アフロ・ブラジル歌曲集 Canções afro-brasileiras》、《先住民の歌曲集 Cantos indígenas》、《ブラジルの子守歌集 Acalantos brasileiros》などが代表作である。またいくつかの宗教曲も作曲している。器楽曲ではギター曲《ポンテイオ集 Ponteios》などがある。
アロイジウ・ジ・アレンカール・ピントゥのピアノ曲は、20世紀の作曲家としては時代遅れともとれるような音楽だが、「ピアニスト(ピアニスタ)」より「ピアネイロ」として活躍した彼らしい、分かりやすく、親しみやすい作品揃いである。20世紀初めのサロンパーティーの音楽や、街角のショーロ楽士達の演奏が目に浮かんでくるような、聴いていて何とも言えぬ懐かしさが漂ってくる素敵な作品ばかりである。
Aloysio de Alencar Pintoのピアノ曲リストとその解説
- Abertura do ballet "Bumba meu boi", dois pianos 2台ピアノのためのバレーの序曲「ブンバ・メウ・ボイ」
- Belle époque, valsa ベル・エポック、ワルツ
- Folha d'álbum アルバムの一葉
- Fox-trot フォックストロット
- Improviso 即興曲
- Lamento 哀歌
- Noturno 夜想曲
甘く、ロマンティックな曲。変ニ長調、A-B-A-コーダの形式。Aは静かに寄せては返す波のような左手アルペジオの伴奏にのって、穏やかな重音の旋律が奏される。Bは変イ長調になり、旋律は左手中音部に現れ、右手高音部の重音アルペジオの伴奏は星が瞬くような感じ。 - Oh! Que beco estreito! (Maracatú do carnaval Pernambucano) ああ、何と狭い路地だ!(ペルナンブーコ州のカーニバルのマラカトゥ)
- Quatro peças populares 4つの民謡による小品集
- Xerém シェレム
- Romance sertanejo 田舎のロマンス
- O baile da cotia コチアの踊り
- O forró de Marajó マラジョのフォホー
- Recado para Richter リヒテルへの伝言
- Sarau de Sinhá, piano a 4 mãos (1975) 連弾のためのシニャーのサラウ(奥様の夜会)
サラウとは個人の家などで催される小さな集いで、そこでは音楽の演奏、文学(詩や本の朗読)、踊り、絵の展示など文化的な催しが行われる。この組曲についてピントゥは「シニャーのサラウは小さな1幕物のバレー音楽で、昔のリオのパーティーの光景に基づいたコレオグラフィーの一種である。18世紀にヨーロッパから伝わり、19世紀にはブラジル社会に溶け込んだポルカ、ショッティッシュ 、コントルダンス、ワルツなど踊りや、サラウ(夜会)の光景を私は曲にした。」と語っている。各曲はピントゥのオリジナル曲および、19世紀末から20世紀初めにブラジルのピアネイロ達がサラウで弾いていた国内外の作曲家によるサロン風ピアノ曲のピントゥによる編曲が混じっていており、当時のサラウの賑やかな光景と、そこで活躍するピアネイロ達を描いたような組曲である。和声など作曲技法としてはロマン派初期あたりの単純な作りだが、各曲から匂い立つような何とも懐かしい響きは、百年前のサラウにタイムスリップしたような不思議な感覚を呼び起こすような気がします。この組曲はミニョーネにより管弦楽曲にも編曲された。- Schottisch (música de J. M. Lopes) ショッティッシュ(J. M. ロペスの曲)
ジョゼ・モレイラ・ロペス José Moreira Lopes は1910年代に活動したブラジルの指揮者・作曲家ですが、原曲の曲名は不詳です。へ短調、前奏-A-B-A-C-A形式。舞曲ショッティッシュにありがちな陽気な雰囲気ではなく、何とも哀愁たっぷりの切ない曲。セコンドの問いかけにプリモが返事するようなコール・アンド・レスポンスの旋律が奏される。Bは変イ長調になる。Cはへ長調になり、プリモの問いかけセコンドが返事する旋律となる。 - Polca (música de J. G. Christo) ポルカ(J. G. クリストの曲)
ジョゼ・ガルシア・ジ・クリスト José Garcia de Christo (1867-1919) はブラジルのピアニスト・作曲家で、彼が作曲したピアノ曲《ジロンド派 Girondinos》を編曲している。へ長調、前奏-A-B-A-C-A-B-A形式。主旋律を概ねプリモの右手が演奏し、プリモの左手やセコンドの右手は和音を形成しつつ対旋律にもなっていて立体的な響きだ。更に原曲では見られない半音階進行が醸し出すディミニッシュ(減七の和音)の響きが何ともお洒落だ。BとCは変ロ長調になる。 - Romance (música original) ロマンス(オリジナル曲)
ハ長調、前奏-A-B-B-A'-B形式。サロンパーティーで女性が上品な歌曲を歌っているような曲。前奏はレチタティーヴォ風で、ここだけハ短調でなのが暗示的。セコンドは19世紀のフォルテピアノの音色を思わせるような古風で穏やかな伴奏が奏され、プリモは優雅な主旋律と対旋律を奏する。 - Contradança (música original) コントルダンス(オリジナル曲)
ハ長調、前奏-A-A-B-A-C-B-A'形式。愉快で快活、愛嬌たっぷりの曲。セコンドのブンチャッブンチャッの伴奏にのって、プリモが跳ね回るように踊るような旋律を奏する。珍しく曲全体で転調が現れない。 - Valsa (música de A. Margis) ワルツ(A. マルジの曲)
アルフレッド・マルジ Alfred Margis (1874-1913) はフランスのピアニスト・作曲家で、彼が作曲したピアノ曲《青のワルツ Valse bleue》を編曲している。マルジの原曲は変ホ長調だがこの編曲は変イ長調。前奏-A-B-A-C-D-A形式。プリモは概ね優雅な旋律をユニゾンまたは重音で奏で、セコンドはワルツの伴奏に加えて、時折穏やかなアルペジオを挟み込んで豊潤な響きを醸し出している。Bは変ホ長調、CとDは変ニ長調になる。 - Noturno (música de C. Galos) 夜想曲(C. ガロスの曲)
ジゼル・ガロス Giselle Galos (1821?-1903?) はフランスのピアニスト・作曲家で、彼が作曲したピアノ曲《羊飼いの歌、夜想曲 Le chant du berger, nocturne、作品17》を編曲している。ガロスの原曲はニ長調だがこの編曲は変ホ長調。前奏-A-B-A'形式。セコンドは宛らハープを思わせるアルペジオを穏やかに奏で、プリモは高音のユニゾンで旋律を奏で、時々ショパン風の繊細な装飾音が彩られる。 - Capricho (música de Liebich) カプリーチョ(リービッヒの曲)
イマニュエル・リービッヒ Immanuel Liebich (1832?-1901) はイギリスの作曲家で、彼が作曲したピアノ曲《オルゴール、カプリーチョ The musical box, A caprice》を編曲している。変イ長調、前奏-A-B-A-C-A'形式。リービッヒの原曲は曲名の「オルゴール」らしく全曲ト音記号の高音部で演奏されるのに対し、この編曲はプリモの旋律こそ高音部だがセコンドの伴奏は中低音部で奏されて、舞曲ガボットのように聴こえる。Bは変ホ長調、Cは変ニ長調になる。 - Lundu (música original) ルンドゥ(オリジナル曲)
ルンドゥとはアフリカ(アンゴラあたりが起源とされている)からブラジルに連れてこられた奴隷達が伝えた舞踊が、18世紀末からブラジルで変化してきた踊りや歌の一つで、マシーシやショーロの起源の一つとされている。ト長調、前奏-A-B-A-C-A形式。全曲ズチャンチャズンチャンのシンコペーションのリズムにのった陽気な曲。Bはニ長調、Cはホ短調になる。 - Recitativo (música original) レチタティーヴォ(オリジナル曲)
変ロ長調、前奏-A-A-B-A形式。旋律らしきものはなく、プリモ・セコンドが奏でる3拍子の和音がゆったりと奏される。Bはへ長調になる。 - Galope (música de L. Gobbaerts) ギャロップ
ジャン・ルイ・ゴバールツ Jean Louis Gobbaerts (1835-1886) はベルギーのピアニスト・作曲家で、姓の綴りを逆から読んだストリーボッグの芸名の方が有名である。彼が作曲したピアノ連弾曲《路面電車 Tramway, 作品37》を編曲している。ゴバールツ(ストリーボッグ)の原曲はハ長調だがこの編曲は変ホ長調。前奏-A-B-A-C-A-B-A-コーダの形式。セコンドのブンチャッブンチャッの伴奏にのって、プリモに威勢の良い旋律が奏される。Bは変ロ長調になる。Cは変イ長調になり、時折旋律に現れる連打音が路面電車のチンチンという鐘の音を模しているのだろう。
- Schottisch (música de J. M. Lopes) ショッティッシュ(J. M. ロペスの曲)
- Seresta (1967) セレナード
ホ短調、前奏-A-B-B'形式。ギターのつま弾きを思わせるゆっくりとした伴奏にのって、嘆くような旋律が奏される。Bは一層激情するように盛り上がる。 - Suíte Sul-americana, Sobre temas populares 南アメリカ組曲、民謡の主題による
南米各国の民族舞踊または民謡の形式を元に作られた組曲である。各曲とも分かりやすい和声と表情豊かな旋律で聴いていて心地良く、南米のパノラマを見ているような色彩感たっぷりの組曲である。- El San Pedro (Venezuela) 聖ペドロ(ベネズエラ)
ベネズエラ北部に位置する2つの隣接した町のグアレナス Guarenas とグアティレ Guatire では、毎年6月29日に聖ペドロの祭り Parranda de San Pedro が催されており、この祭りは2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されている。この曲は祭りの音楽を題材にして作曲されたと思われる。変ト長調、A-A'-B-A"形式。6/8表紙の心地良いリズムの伴奏にのって明るい旋律が奏される。BはAの変奏で、イ長調に転調する。 - Huayño (Argentina) ワイニョ(アルゼンチン)
ワイニョ(またはワイノ)はペルー、ボリビアから北部アルゼンチンやチリで演奏される民族舞踊とその音楽の一つ。ワイニョは2拍子の速いテンポの曲が多いが、地方によりリズムは様々らしい。ただこの曲は3/4拍子で、ワイニョよりかはアルゼンチンのビダリータに近いような気がする。嬰ハ短調。太鼓が静かに鳴るようなリズムにのって、嘆くような旋律が三度重音で奏される。 - Chacarera (Argentina) チャカレーラ(アルゼンチン)
チャカレーラはアルゼンチンの民族舞踊の一つ。嬰へ短調、A-B-A'形式。速い3拍子のリズムにのって哀愁漂う旋律が奏される。 - Zás! (Peru) サス!(ペルー)
ロ長調、A-A'-A"形式。左手に太鼓を叩くような♩♫のリズムが続くのにのって、右手に愛嬌ある旋律が五音音階で奏される。最初はppで始まり、楽隊が近づくかの如く徐々にクレッシェンドし、A'ではfになり、A'の後半から徐々にディミヌエンドし、最後は消えるようなpppで終わる。 - Coplas tolimenses (Colômbia) トリマのコプラ(コロンビア)
コプラとはスペイン由来の定型詩およびその詩による歌であるが、それらが伝わった南米各地で変化した地域独特のコプラが存在する。コロンビア中西部のトリマ県では「トリマのコプラ」と呼ばれる民謡があり、多くは3/4拍子と6/8拍子のポリリズムである。嬰ト短調、A-B-A-C-A'-D-コーダの形式。Aは踊りのようなリズムが続き、BはAとほぼ同じ和音進行で哀愁たっぷりの旋律が現れる。 - Tirana (Brasil) チラーナ(ブラジル)
チラーナとは、スペイン由来で18世紀末頃にブラジルに伝わった舞踊で、リオグランデ・ド・スル州など主にブラジル南部で踊られている。チラーナにはいくつかの踊りのタイプがあり、男女のカップルがハンカチーフを手で振りながら足で床を踏みならす「ハンカチーフのチラーナ Tirana do lenço」が有名である。変イ長調、A-B-C-A'形式。Aは(アルゼンチン)のマランボ風の3連符の速いパッセージと、ゆっくり朗々と歌う部分が交互に奏される。Bは6/8拍子の軽快なリズムにのった旋律が現れ、スペイン・アンダルシアのサパテアードを思わせる。Cはいっときロ長調になり、踊り手が興に乗ったような両手和音交互連打など賑やかになる。
- El San Pedro (Venezuela) 聖ペドロ(ベネズエラ)
- Suíte TV Série, piano a 4 mãos 連弾のためのテレビ・シリーズ組曲
テレビドラマの音楽をピアノ連弾に編曲した組曲である。元になった7本のテレビドラマは全て米国の制作(下記の放映年は米国でのもの)であるが、7本とも日本でも放映されており、おそらくブラジルでも放映されていたのであろう。ピントゥの編曲はとりたてて凝っている訳でもなく、分かりやすい旋律と和声でテレビドラマのシーンを連想させるような作品である。- O Incrível Hulk 超人ハルク
『超人ハルク』は米国のコミックを原作とした実写テレビドラマで、1977年から1982年まで放送された(日本でも日本テレビから放映された)。この曲は、テレビドラマの音楽を担当したジョー・ハーネルが作曲し、ドラマのエンディングで流れる〈孤独な男 The Lonely Man〉を元にしている。ニ短調、前奏-A-A'形式。プリモに哀愁たっぷりの旋律が奏され、セコンドに旋律のこだまのような対旋律が現れる。 - McCoy マッコイ(マッコイと野郎ども)
『マッコイ』はコメディー・テレビドラマで、1975年から1976年まで放送された(日本でも『マッコイと野郎ども』という題名でNHKから放映された)。この曲は、音楽を担当したリチャード“ディック”デベネディクティスが作曲し、ドラマのテーマ曲として使用されたものを元にしている。変ロ長調、A-A'-B-A"形式。ゆっくりとしたスゥイングのリズムの陽気な曲。 - Peter Gunn ピーター・ガン
『ピーター・ガン』は探偵物のテレビドラマで、1958年から1961年まで放送された(日本でもTBS系列から放映された)。この曲は、ヘンリー・マンシーニが作曲しドラマのテーマ曲として使用されたものを元にしている。一応へ長調、A-B-A'形式。セコンドが低音でブギウギ風のオスティナートを奏で、原曲では金管楽器が叫ぶように奏される旋律をプリモがブロックコードや2オクターブのユニゾンで奏する。 - Barnaby Jones バーナビー・ジョーンズ(名探偵ジョーンズ)
『バーナビー・ジョーンズ』は探偵物のテレビドラマで、1973年から1980年まで放送された(日本でも日本テレビ系列から放映された)。この曲は、ジェリー・ゴールドスミスが作曲しドラマのテーマ曲として使用されたものを元にしている。へ短調、A-A'-B-A"形式。原曲をスゥイングのリズムに編曲している。プリモが旋律を2オクターブのユニゾンで奏する。 - Bat Masterson バット・マスターソン
『バット・マスターソン』は実在の同名の保安官を元にした西部劇のテレビドラマで、1958年から1961年まで放送された(日本でもNETテレビ[現テレビ朝日]から放映された)。ヘヴンズ・レイが作曲したテーマ曲はドラマの最初ではインストゥルメンタルで、最後には歌で演奏される。曲は変イ長調、A-A-B-A'形式。セコンドが馬の蹄の音を思わせるブンチャッブンチャッの伴奏を奏で、プリモが陽気な旋律をオクターブで奏する。 - Hawai 5-0 ハワイ5-0
『ハワイ5-0』はハワイを舞台とした刑事物のテレビドラマで、1968年から1980年まで放送された(日本でもフジテレビから放映された)。この曲は、モートン・スティーヴンスが作曲しドラマのテーマ曲として使用されたものを元にしている。変ロ短調、A-A'形式。プリモが旋律をブロックコードで奏で、セコンドが合いの手を入れる。A'はへ短調になる。 - Bonanza ボナンザ
『ボナンザ』は西部劇のテレビドラマで、1959年から1973年まで放送された(日本でも日本テレビ系列から放映された)。この曲は、ジェイ・リヴィングストンとレイ・エヴァンスが作曲しドラマのテーマ曲として使用されたものを元にしている。変ホ長調、A-A'-A"形式。セコンドが西部劇らしい速いテンポの伴奏を奏で、プリモが威勢のよい旋律を奏する。
- O Incrível Hulk 超人ハルク
- Toada goiana ゴイアスのトアーダ
1960年に自作自演した録音のみが残されている。へ長調。中低音部で穏やかに和音が鳴るのにのって、レチタティーヴォ風の旋律が即興で歌うように奏される。 - Toccata トッカータ
イ長調、前奏-A-B-A-C-コーダの形式。ラのリディア旋法の前奏に引き続き、ほぼ全曲にわたって左手は太鼓を打つようなシンコペーションのオスティナートで、右手は16分音符が続き、バトゥキかサランベキあたりのアフロ・ブラジル音楽のような躍動的な雰囲気だ。Aの後半やBはソが♮(ラのミクソリディア旋法)になり、またリズムもバイアォンのようでノルデスチ(ブラジル北東部)の民族音楽を思わせる。10小節のみのCはテンポを落とすが、またコーダで速いテンポに戻って終わる。 - Valsa-capricho ワルツ=カプリーチョ
変イ長調、前奏-A-B-C-D-前奏-A-コーダの形式。Aはオクターブの旋律が悠々とした感じ。Bの旋律は3連符混じりで可憐な雰囲気。Dは変ニ長調になり、優美な旋律が歌うように奏される。 - Valsa lenta ゆっくりとしたワルツ
手稿譜には「私の母のために」と記されている。嬰へ短調、A-A'-B-B'-A-A'形式。半音階混じりの旋律が哀愁たっぷりと奏され、内声の対旋律が絡む。BとB'はイ長調になり、郷愁感に溢れる雰囲気の「これぞサウダージ」といった感じ。 - Valsas (no estilo popular) ワルツ集(民謡のスタイルで)
- Noite de maio 五月の夜
- Quando éramos dois 私達が2歳の時
- Apenas um sonho ただの夢
- Lembrança do "Bal-Musette" バル・ミュゼットの思い出
- Idílio em Montparnasse モンパルナスの牧歌
- 14 de julho na Rive Gauche リヴ・ゴーシュの7月14日
- Visão 幻影
Aloysio de Alencar Pintoのピアノ曲楽譜
Musica BrasilisのサイトのAloysio de Alencar Pintoのページで、ピアノや歌曲の楽譜を見ることが出来ます。
Aloysio de Alencar Pintoのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
Música Latino-Americana![]()
- Sonata No. 1 (Alberto Ginastera)
- Suíte Sul-americana (Aloysio de Alencar Pinto)
- Sonata n. 1 (Francisco Mignone)
- Valsa brasileira n. 6 (Francisco Mignone)
- Valsa Lenta (Aloysio de Alencar Pinto)
- Pierrot Op. 33 n. 3 (Henrique Oswald)
- Corta-jaca (Fructuoso Vianna)
Irany Leme (pf)
ピアニストのIrany Lemeはアロイジウ・ジ・アレンカール・ピントゥの弟子で、師弟によるピアノ連弾の動画が残されている。
Grandes Pianistas Brasileiros Volume VI, Arnaldo Rebello![]()
![]()
MCD World Music, MC 017
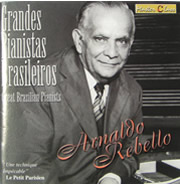 |
|
Arnaldo Rebello (pf)
1964、1973年の録音。
Duo Pianístico da UFRJ - Sarau de Sinhá![]()
Tons e Sons / UFRJ, TS 9804
- Sarau de Sinhá (Aloysio Alencar Pinto)
- Brasiliana nº 4 (Osvaldo Lacerda)
- Seresta op. 1 (Aylton Escobar)
- Tango (Ronaldo Miranda)
- Lundu (Francisco Mignone)
- Congada (em forma de Rondó) (Francisco Mignone)
Sonia Maria Vieira (pf), Maria Helena de Andrade (pf)
IGUAÇU![]()
Paraty Productions
- Dança negra (Mozart Camargo Guarnieri)
- Quebra o côco, menina! (Aloysio de Alencar Pinto)
- Tres romances argentinos (Carlos Guastavino)
- Bailecito (Carlos Guastavino)
- Brasiliana No. 8 (Radamés Gnattali)
- O trenzinho do Caipira (Heitor Villa-Lobos)
- Libertango (Arr. for piano) (Ástor Piazzolla)
- Oblivion (Arr. for piano) (Ástor Piazzolla)
- Tres minutos con la realidad (Arr. for piano) (Ástor Piazzolla)
- Nação No. 2 (Hercules Gomes)
Duo Aurore: Diego Munhoz (pf), Renata Bittencourt (pf)
2020年のリリース。
Duo Kaplan-Parente - Piano Brasileiro a 4 Mãos (LP)![]()
![]()
Discos Marcus Pereira, MPA-9359
 |
|
José Alberto Kaplan (pf), Gerardo Parente (pf)
1977年の録音。
Valsas e Serestas (LP)![]()
Clack, BR 23055
- Carinhoso (Pixinguinha / Arr. Radamés Gnattali)
- Remando (Ernesto Nazareth)
- Valsa original para violão (Mozart Araújo / Transc. Aloysio de Alencar Pinto)
- Valsa N.º 2 (Florzinha Emidyo Távora)
- Valsa lenta (Aloysio de Alencar Pinto)
- Lundu amazonense (Arnaldo Rebello)
- Ao violão (Branca Bilhar)
- Seresta (Aloysio de Alencar Pinto)
- Linda flôr (Henrique Vogeler)
- Valsa amazônica N.º 2 - Vitória régia (Arnaldo Rebello)
- Chuá chuá (Pedro de Sá Pereira)
- Valsinha do Marajó (Waldemar Henrique)
- Festa na cachoeirinha (Francisco Donizetti Gondim)
- Valsa para mão esquerda (Waldemar de Oliveira)
Gerardo Parente (pf)
1981年のリリース。
Os pianeiros (2LPs)![]()
![]()
Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil (FENAB) 114, 115
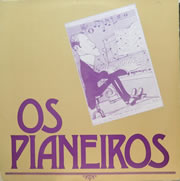 |
LP 1
LP 2
|
Carolina Cardoso de Menezes (pf)*, Antônio Adolfo (pf)**, Aloysio de Alencar Pinto (pf)***, Augusto Vasseur (pf, 1957年録音)****, Ernesto Nazareth (pf, 1930年録音)*****, Nonô (pf, 1932年録音)******, Tia Amélia (pf, 1980年録音)*******
上記に録音年の記載の無い曲は1986年の録音。一時代前までのブラジルでは、ピアノ演奏を職業とする人は「ピアニスト(ポルトガル語ではピアニスタ)pianista」と「ピアネイロ pianeiro」の2種類があった。ピアニスト(ピアニスタ)は主にコンサートホールでクラシック音楽を演奏し、音楽院の教授をするような人を指し、一方ピアネイロは映画館の待合室、カフェ、キャバレー、ダンスパーティーなどでジャンルを問わず客の好みや要望に合わせた曲を弾き、ショーロ楽団とは即興でセッションをしていた。社会的地位はピアニスト(ピアニスタ)の方が高かったようだが、私に言わせると、ピアネイロはその場での移調や即興演奏の能力が必須で、またピアネイロはレコードが無かった時代には楽譜店に雇われ、店頭で客の求めに応じて客が購入を考えている楽譜をその場で弾く初見能力も必要であり、総合的な音楽力はピアネイロの方が上だったんじゃないかな〜と思います。