René Amengualのページ
René Amengualについて
René Amengual Astaburuaga(レネ・アメングアル・アスタブルアガ)は、1911年9月2日、サンティアゴに生まれた。母親のAurora Astaburuaga Urzúaはサンティアゴの国立音楽院卒業でピアノ教師をしており、レネ・アメングアルは母からピアノを習った。12歳で国立音楽院に入学。その後、ロジータ・レナルドにピアノを、ペドロ・ウンベルト・アジェンデに作曲を師事した。1935年に国立音楽院を卒業すると、同院のピアノ科や作曲科の教員として働いた。
1940年には何人かのチリの音楽家と共に、現代音楽舞踊学院 (Escuela Moderna de Música y Danza) を創立した。1943年には米国国際教育研究所の招きで米国に約一年間滞在し、演奏活動を行った。
1947年に国立音楽院院長に就任し、亡くなるまでその職にあった。
1953年に作曲した管楽7重奏曲は 同年にノルウェーのオスロで開かれた国際現代音楽祭で発表されることになり、アメングアルは音楽祭に出席し、またヨーロッパ各国を訪れた。しかし帰国後に腹膜炎となり、1954年8月2日、サンティアゴで亡くなった。
アメングアルの作品は、交響的前奏曲 (1939)、ピアノ協奏曲 (1941-1942)、ハープ協奏曲 (1943-1950)、弦楽四重奏曲第1番 (1941)、第2番 (1950)、ヴァイオリンソナタ (1944)、フルートとピアノのための組曲 (1945)、ソプラノと室内楽のための "El vaso" (1942) などが代表作。合唱曲では混声合唱のための "Motete y Madrigal" (1939-1941)、児童合唱のための "Ocho canciones y cánones" (1952) などを作曲。また1942年のチリ大学創立百周年を記念して校歌 "Himno de la Universidad de Chile" を作曲した。その他いくつかの歌曲もある。
René Amengualのピアノ曲リストとその解説
1932年頃
- Álbum infantil, 12 trozos para piano 子どものアルバム、ピアノのための12の小品
- Juguemos a la ronda 輪になって踊ろう
- Molino de agua 水車
- Había una vez una princesa ある時一人の王女様がいました
- Soldaditos de palo 木の兵隊さん
- La danza de la muñeca お人形の踊り
- Hojas muertas 枯葉
- Cajita de música オルゴール
- Paisaje 風景
- El pastorcito 小さな羊飼い
- Arroyuelo 小川
- Caperucita, a dónde vás? ずきんちゃん、どこへ行くの?
- Fiesta お祭り
- Tres estudios 3つの練習曲
1934年頃
- Burlesca, Op. 5 ブルレスケ、作品5
- Berceuse trágica 悲劇的な子守歌
1937
- Suite 組曲
- Tonada トナーダ
「トナーダ」とは「歌」という意味のスペインや南米の民族音楽の一つで、ギターかハープの伴奏にのって唄われる叙情歌である。この曲はトナーダの形式に従い、ゆっくりした部分と速い踊りから成るA-B形式である。Aはハ短調で、ポツポツと語るような旋律に、不協和音の連打が装飾するように挟まれる。後半Bはハ長調で無邪気な雰囲気。 - Transparencias 透明
機能的和声を離れ、「透明感」をピアノの音色で表現したような繊細な曲。低音部ミ音オクターブが鳴るのにのって、高音部でミのフリギア旋法のフレーズがppで奏され、その下の中音部ではラ♯やレ♯が鳴って多調となり、それらの音が一体となって、クリスタルガラスを思わせる透明感を醸し出している。その後は高音部の旋律は半音階進行が主になり、魔法のような世界。最後の2小節で冒頭の部分が繰り返される。
1938
- Sonatina ソナチネ
このソナチネは、ラヴェルのピアノ曲「ソナチネ」の影響を受けつつも、それを更に進化させたような感じの作品である。全体的に中音域から高音域で弾くようになっていて(楽譜を見ると特に第2楽章、第3楽章は殆どの部分が両手ともト音記号のみで書かれている)繊細な響きが妙に魅力的な曲である。- Allegro
ソナタ形式。提示部の第一主題は強いて言えば嬰ト短調で、四度や七度、九度の和音を多用した響きが透明感を出している(下記の楽譜)。
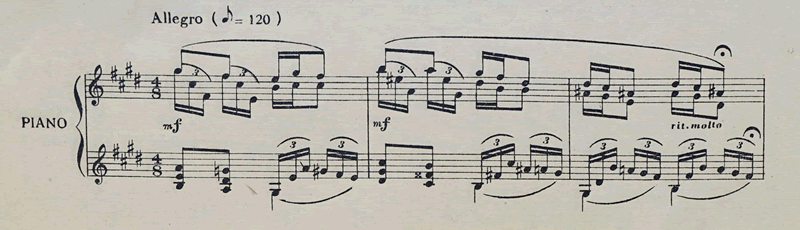
Sonatina、第1楽章1~3小節、Editorial Cooperativa Interamericana de Compositoresより引用
10小節目から第二主題で、ハンガリー音階のようなモチーフが現れ、32分音符の装飾音や32分音符の三度重音下降などの響きは絹織物を触っているような感じだ(下記の楽譜)。
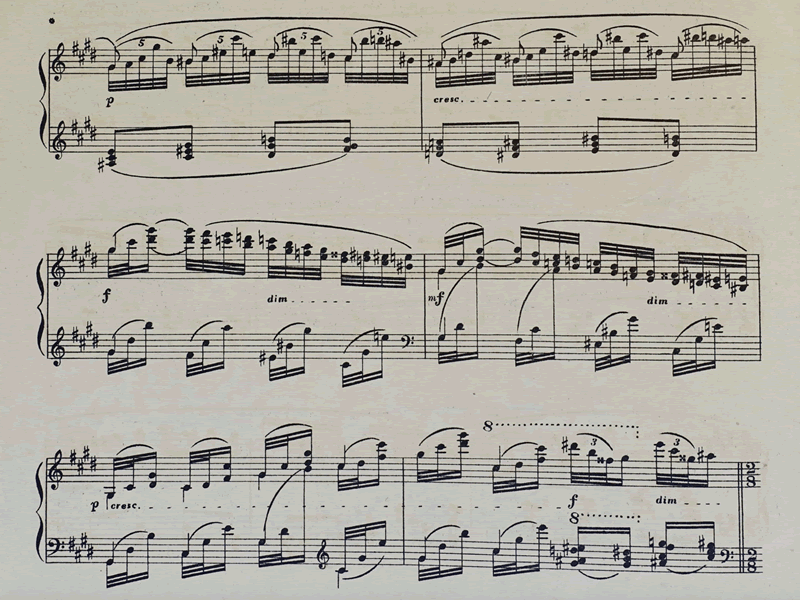
Sonatina、第1楽章15~20小節、Editorial Cooperativa Interamericana de Compositoresより引用
展開部は主に第二主題が繊細な響きを保ったまま奏される。再現部は第一主題、(提示部より長三度音程を下げた)第二主題が奏される。 - Lento y gran expresión
強いて言えばロ短調、A-A'-B-A形式。中音部に静かに鳴る3連符和音にのって、あてもなく彷徨うような旋律が奏される。旋律はミ♯やラ♯が現れ、多調の響きだ。A'は半音階進行を続ける16分音符内声が加わって何とも幻想的な響き(下記の楽譜)。
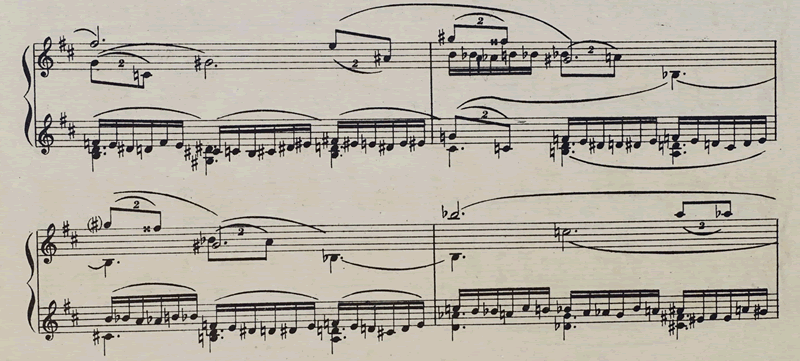
Sonatina、第2楽章9~12小節、Editorial Cooperativa Interamericana de Compositoresより引用
Bはモチーフがカノンのように声部が加わっていく。 - Rondo - Allegro
強いて言えばホ長調。高音部に軽快な旋律が奏され、16分音符分散和音が纏わりつく(下記の楽譜)。これが形や調を変えたりして6回繰り返されるが、その合間に毎回異なる気まぐれのような部分が奏される。
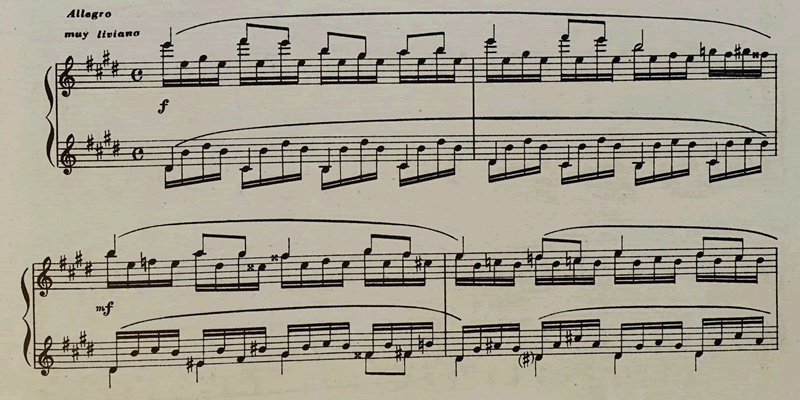
Sonatina、第3楽章1~4小節、Editorial Cooperativa Interamericana de Compositoresより引用
- Allegro
1939
- Homenaje a Ravel ラヴェルへのオマージュ
- Introducción y allegro para dos pianos 2台ピアノのための序奏とアレグロ
1950-1951
- Diez preludios breves (Diez preludios pequeños) 10の短い前奏曲集(10の小さな前奏曲集)
この前奏曲集は派手な所は殆どなく、全体的に少ない音で書かれていて(第1、2、3、4、5、8、10曲は一声または二声のみで書かれている)、耳を澄ませてピアノの音(音程)を味わうような、独特の作品集である。- Lento
3/4拍子で左手がド-シ-シ♭ を繰り返しているのにのって、ホ短調の旋律があてもないように静かに奏される。 - Moderado (mano izquierda) (左手で)
左手のみで弾く曲。二声で書かれている。素朴な旋律の下で、対旋律がE♭、F♯、A♭などのの和音を奏でる。 - Alegre
右手に快活な旋律がへ短調やホ短調で奏されるが、左手の合いの手のような音と調がズレているのが不思議な響き。 - Tranquilo
完全四度の堆積がゆっくりしたアルペジオで鳴る曲。 - Andante
カノン様式の曲。調性に乏しい旋律が右手に現れ、三拍遅れて長九度下を同じ旋律が追っていき、空虚な響きを醸し出している。 - Lento
右手で8分音符ラ -ソ-ラ-ソの音がゆらゆらと続く下で、2分音符の重音が静かに鳴る。 - Andante
左手重音の全音符と右手三度重音の2分音符が静かに鳴る響きを味わうような曲。 - Improvisadamente
楽譜には最後まで小節線はなく、まず低音部で脅すような響きの旋律らしきものがfで現れ、それに呼応するように高音部で弱々しい旋律がpで奏されるのが、対話のように交互に現れる。個人的には、金持ちと貧しい人を描いているようにも思えます。 - Moderado
最初の5小節のモチーフは長三和音または短三和音で弾かれ、(コードネームで記すと)F-Am-F-C♯m-Em-F♯-A♯m-・・・と離れた関係の和音に飛んでばかりである。後半は同時に右手C+左手C♯が鳴るなど多調に成る。 - Moderadamente movido
組曲中、唯一の速いテンポの曲。左手音階→右手音階が16分音符で流れるように滑らかに続くが、左手は全て黒鍵の♯音(即ちペンタトニック)、右手は全て白鍵で弾かれ、その音色は幻想的な響きである。
- Lento
René Amengualのピアノ曲楽譜
Instituto de Estudios Superiores Montevideo
- Boletín latino-americano de música, Suplemento musical Año IV, Tomo IV (1938)
- Transparencias
G. Schirmer
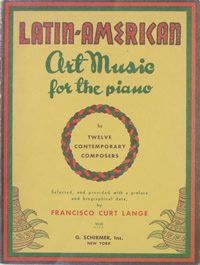 |
|
Editorial Cooperativa Interamericana de Compositores
- Sonatina
Universidad de Chile, Instituto de extención musical
- Diez preludios pequeños
斜字は絶版と思われる楽譜
René Amengualのピアノ曲CD・カセットテープ
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Música Chilena del siglo XX, Volúmenes VII y VIII (2枚組CD)![]()
SVR Producciones, ANC 6003-7 6003-8
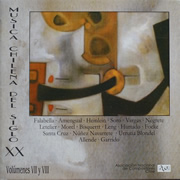 |
CD 1
CD 2
|
レネ・アメングアルのSonatinaの録音は1964年。
Piano Chileno de Ayer y Hoy![]()
SVR Producciones, 1026
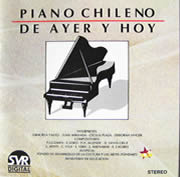 |
|
Garciela Yazigi (pf)*, Elma Miranda (pf)**, Cecilia Plaza (pf)***, Deborah Singer (pf)****
1994年のリリース。
Bicentenario del Piano Chileno, Vol. 1![]()
SVR Producciones, 6000-1
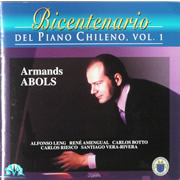 |
|
Armands Abols (pf)
2002、2003年の録音、2004年のリリース。
Música Chilena Contemporanea para Dos Pianos (カセットテープ)![]()
Asociación Nacional de Compositores de Chile, MCC 101
 |
|
1987年の録音。
René Amengualに関する参考文献
- Vicente Salas Viú. La obra de René Amengual. Del neoclasicismo al expresionismo. Revista musical chilena, Año XVIII, Octubre-Diciembre 1964, Nº 90.