Sylvio Deolindo Fróesページ
Sylvio Deolindo Fróesについて
シルヴィオ・デオリンド・フローエス Sylvio Deolindo Fróes は1864年10月26日、バイーア州サルヴァドールに生まれた。彼の父は法律家で、また母はドイツ出身でパリ音楽院で学んだ歌手・音楽教師であった。シルヴィオは4歳より母からピアノを習い、9歳頃には《メロディー、天使達の音楽》というピアノ曲を作っている。1880年、ブラジルを代表する作曲家カルロス・ゴメスがサルヴァドールを訪れた際、シルヴィオ・デオリンド・フローエスはゴメスの面前でゴメスのオペラ《グアラニー族》をモチーフとした即興演奏を披露し、ゴメスから賞賛を受けている。1882年にリオデジャネイロ工科大学に入学し学ぶが、音楽の勉強も続けた。
1888年、フローエスはパリに渡り、オルガン奏者・作曲家のシャルル=マリー・ヴィドールに師事し、オルガンや作曲法、対位法などを学んだ。また彼はパリのサン=シュルピス教会のオルガニストを務め、またサル・プレイエルでリサイタルを催した。その後、ドイツのライプツィヒとカールスルーエに滞在して指揮者・作曲家のフェリックス・モットルに師事した。
1898年にブラジルに帰国すると、その前年に設立されたばかりのバイーア音楽院の院長に就任した。1901年から1904年まで再びフランスに滞在してリサイタルを催したが、帰国後はバイーア音楽院の院長に再び就いた。彼の任期中には、1904年に州政府からの音楽院への財政援助がカットされるなどの困難に見舞われたが、彼は院長職を1930年台まで続けた(1917年にバイーア音楽院はバイーア音楽学校 Instituto de Música da Bahia へ改組された)。
1908年にAna Americaと結婚した。
1946年にはブラジル音楽アカデミー会員に選ばれた。
1948年12月3日にサルヴァドールで亡くなった。葬儀では彼自身が作曲した《葬送行進曲》が演奏された。
フローエスは生前、息子に「音楽院の仕事の為に作曲する時間が取れない」と語っていたそうだが、数々の作品を残している。ピアノ曲以外の代表作を記すと、交響詩《老人達の思い出 Souvenirs de vieilles gens、作品3》(1888-1889)、歌曲《2つのロマンス Deux romances、作品4》(1893)、《管弦楽六重奏曲嬰へ短調 Sextour en fa# mineur、作品7》(1897)、《ヴァイオリンソナタ、作品8》(1896)、《交響曲変ロ短調、作品15》(1909)、合唱と管弦楽のための《ドナ・サンチャの伝説 Lenda de Dona Sancha、作品16》(1912) などがある。彼はドイツ留学中にワーグナーのオペラに心酔し、自らもオペラの作曲にも取りかかっていたが、未完成に終わった。
フローエスのピアノ曲は、《熱帯の風景集、第3集》の第3曲〈黒人の踊り〉でアフロ=ブラジル音楽が認められるのを除けば、ブラジル風味な作品は見られない。作曲家としての彼にはブラジル民族主義という意識が殆どなかったのであろう。一方、後期ロマン派の作曲家として見ればなかなか優れた作曲法で、聴けばフローエスの曲であると分かるような独特の和音使いを感じるし、また音楽は単なる風景や人物描写ではなくその奥の霊感を音にしたような作品揃いである。
Sylvio Deolindo Fróesのピアノ曲リストとその解説
未完または作品の一部のみが残されている手稿譜については、以下のリストに載せませんでした。
多くの作品の楽譜では出版譜・手稿譜ともに、曲名が二か国語またはそれ以上で併記されています。以下のリストではポルトガル語の曲名に続いて併記された言語での曲名(殆どがフランス語)を括弧内に記しました。
ca. 1874
- Melodia, Música dos anjos メロディー、天使達の音楽
1888-1889
- 3 pièces (Petite suite), Op. 1 3つの小品、作品1
- Barcarolle-Nocturne (fa min.) (1888?) 舟歌ー夜想曲(へ短調)
- Allegro scherzando (la b maj.) アレグロ・スケルツァンド(変イ長調)
- Bluette (fa maj.) 小品(へ長調)
- Deux feuilles d'album 2つのアルバムの葉
- *
- Conversation de vieilles gens (Souvenirs de vieilles gens, Op. 3)、d'après une poésie brésilienne 老人達の会話(老人達の思い出、作品3)、あるブラジルの詩による
1890
- Arioso アリオーソ
1890?
- Capriccio, Op.13 奇想曲、作品13
1895
- Impromptu sur un thème donné 一つの決まった主題による即興曲
1897?
- Marche funèbre (Trauermarsch) du Sextour en fa# mineur, Op. 7, Arrangement pour 2 pianos par l'auteur 六重奏曲嬰へ短調より葬送行進曲、作品7、作曲者による2台ピアノ用編曲
管弦楽のための《六重奏曲嬰へ短調、作品7》の楽章の一つを2台ピアノ用に編曲し〈葬送行進曲〉と名付けた曲。楽譜はドイツで出版された。ロ短調、A-B-C-D-A'-B'-C'-コーダの形式。Aは低音部のゆっくりとした行進曲のリズムの上で悲痛な旋律が奏される。Bはニ長調で激情したようなffが奏され、Cで力尽きたように静まる。Dはイ長調で、故人を回想するような雰囲気。
1905
- Sonata, Op. 6 ソナタ、作品6
- Allegro festivo
- Adagio (Lento e lugubre)
- Rondo finale (Allegretto con grazia)
1900-1907
- Paisagens tropicaes (Paysages troipicaux), 1ª série, Op. 17 熱帯の風景集、第1集、作品17
まずこの組曲全体を聴いてみると、我々が一般的に想像する「熱帯の風景」とか「灼熱のブラジル」といったイメージは殆ど浮かびません。むしろヨーロッパの作曲家が作った後期ロマン派音楽かと見紛うような曲ばかりである。フローエスが暮らしたブラジル北東部のサルヴァドール市は熱帯雨林気候であり、フローエス自身が日常生活の中で見聞きしたものの印象を音楽にしたという意味でこの組曲を「熱帯の風景集」と命名するのは間違ってはいないが、ブラジルの民衆が普段歌い奏でる民俗音楽との繋がりは感じられない。この組曲が作られた20世紀初頭のブラジルでは、既にナザレのような民族主義的なピアノ曲が現れているが、この頃のフローエスの音楽的思考は10年間のヨーロッパ留学で培った旧大陸のものがおそらく全てで、それを自国の民俗音楽と結びつけようとする考えにはまだ至っていなかったのかもしれない。あくまで一人の後期ロマン派の作曲家のピアノ曲として聴けば、複雑な和声や転調、特に全音音階の多用による調性のぼかしなど、なかなかの腕前の作品である。- Prelúdio (Prélude) 前奏曲
組曲の冒頭に相応しい爽やかな雰囲気の曲。ニ長調、A-B-A'形式。下行モチーフが旋律や対旋律に現れつつ、頻繁に転調していく。 - Vozes d'alva (Voix du matin) 夜明けの声
フランス語の曲名では「朝の声」となる。イ長調、A-B-A'形式。冒頭はカッコウが鳴くようなモチーフで始まり、声部を増やしながら4分音符〜8分音符〜16分音符と賑やかな響きになる様は、何羽の鳥が思い思いに鳴いている様だ。また全音音階や増三和音の響きは、徐々に夜が明けていくような雰囲気を醸し出している。Bでは所々で高音部にトリルが鳴る。 - Rajada (Rafale) 突風
変ニ長調、A-B-B-C形式。3連16分音符または32分音符による速い音階(全音音階が多い)やアルペジオが右手左手交互で奏され、曲名通り突風が吹くような雰囲気だ。 - Queixas da velha árvore (Plaintes du viel arbre) 老木の嘆息
変イ短調。嘆息をつくような旋律が重々しい和音を伴って奏される。嬰ハ短調に転調すると、前記の旋律の上高音部で悲痛な旋律がオクターブで重なる。後半は乾いた風が吹くような高音部モチーフが寂しく鳴るのが繰り返される。 - O que diz a selva ao mar (Ce que la forêt raconte à la mer) 森が海に語っている事
ホ長調。冒頭は風がそよぐ様な16分音符が中音部で奏されるのにのって息の長い旋律が現れ、続いて軽快な3拍子の踊りのような部分が現れ、次に変ニ長調の牧歌的な部分がポリフォニックに奏される。これらの主題が調を変えつつ順不同で次々と変奏され、物語を聞いているような気分である。 - Dansa de folhas seccas (Bal de feuilles mortes) 枯葉の踊り
フランス語の曲名では「踊り」は「舞踏会」になる。強いて言えばロ長調、A-B-A'形式。曲名通り、ずっと16分音符または32分音符が鳴り続ける。Aは右手左手交互に16分音符の全音音階が1オクターブ内で上下し、やがて2つの枯葉がシンクロする様に三度重音のトリルが奏される。Bはロ短調になり、高音部で16分音符のアルペジオが繰り返される下で、中音部に哀愁漂う旋律がゆったりと奏され、秋らしい寂寥感を醸し出している。 - Domingo na aldeia (Dimanche au village) 村の日曜日
変ホ長調。小さな村の教会の光景を描いた曲であろう。冒頭9小節はコラール風の和音が静かに鳴り、それに続いて祈りの歌を思わせる旋律がオクターブ和音を伴って穏やかに奏される。最後はコラール風の和音が再び奏される。
- Prelúdio (Prélude) 前奏曲
1907-1910?
- Paisagens tropicais (Paysages troipicaux), 2ª série, Op. 18 熱帯の風景集、第2集、作品18
- Tarde na clareira (Après-midi dans la clairière) 林間の空き地の午後
ホ長調、A-B-C-A'-B'形式でソナタ形式とも言える。またCが短いので序曲形式とも言える。Aは二声のポリフォニーで書かれていて、軽快な主旋律の下で8分音符の対旋律が絡む。Bはト長調になり、二声の16分音符オスティナートの上に浮かび上がるように、新たな旋律が現れる。短いCの経過句を経て、ホ長調のA'、同じくホ長調のB'が奏される。 - À sombra da encosta (A l'ombre sur le versant) 斜面の日陰で
微睡みを誘うような穏やかな午後の光景を思わせる曲。ト長調、A-B-C-D-E-A'-B'-D'形式(A-B-A'-コーダの形式ともとれる)。Aは穏やかな旋律が現れ、旋律に絡む半音階の中音部16分音符と低音部8分音符が渾然となった幻想的な響きは、モワッとした雰囲気。Bはニ長調になり、優しい下行音階の旋律がゆったりと降ってくる。Cはロ長調、Dは嬰ヘ長調で始まり、ちょっと戯けたスタッカート混じりのモチーフが現れる。再現部に相当するA'、B'、D'はいずれもト長調になる。 - A morte do passarinho (Oiseau mourant) (Scène et impressions d'un soir d'été) (1909-1910?) 小鳥の死に際(ある夏の夕暮れの光景と印象)
フローエスのピアノ曲の中でも最も印象深く、美しい曲に思えます。野生動物は他の動物に捕まって命を失うことが大半であるが、他の理由(飢えや病気など)で死ぬ場合もある。一般的にそういう時は本能的に人や他の動物の目に触れられない所に隠れて孤独に最期を迎えるらしいので、我々がその場面を見ることは滅多にない。動物の死に際を描いた音楽はあまりなく、この作品は、ある夏の夕暮れに、死の間際の一羽の小鳥の脳裏に走馬灯のように思い浮かぶ心情までも空想したような曲と言えよう。曲は〈悲歌〉と〈間奏曲〉の二部から成る。- Élégie 悲歌
変ニ長調。冒頭は、小鳥が力なく囀るようなモルデントを伴った旋律が高音部で静かに奏される。音階を少しづつ上がり、しかし力尽きて下がるような旋律は素朴ながら何とも哀しく美しい。やがて転調をしつつ和音を厚くして音階を下がっていくが、高音部の静かなアルペジオを経てアタッカで間奏曲に続く。 - Interlude 間奏曲
嬰ハ短調。中低音部のハープを思わせるアルペジオにのって悩ましい旋律がゆったりと奏され、頻繁な転調が醸し出す劇的な場面を経て、やがて属九の和音やsus4のアルペジオが恍惚な響きを奏でる。最後は〈悲歌〉の冒頭部分が再現され、静かなアルペジオと和音で曲を閉じる。
- Élégie 悲歌
- Vozes vespertinas (Voix du soir) 夕暮れの声
いくつかの手稿譜が現存するが、楽譜によって相違点が多数ある。嬰イ短調(楽譜によっては異名同音調の変ロ短調)、A-B-C-A'形式。Aは溜息をつくようなモチーフが力なく奏される。Bはへ短調になり、Aの旋律が和音を増して変奏される。Cは軽快に踊るような旋律が繰り返される毎にへ長調〜変ホ長調〜変ニ長調と転調する。A'は両手和音が激情するようにfffで奏されるが、やがて萎んでいくように静まり、ピカルディ終止で終わる。 - Sussurros ao luar (De vagues murmures au clair de lune) 月の光の下のささやき
変ホ長調、A-B-A'-B'-B"-A"-C-A"'-コーダの形式。印象派風の幻想的な曲。Aは8分音符の穏やかな旋律に16分音符の伴奏が纏わり、ハープの音色を思わせる。Bは息の長い旋律が現れるが、変ニ長調の長九の和音に始まり頻繁に転調していく。A'はロ長調、B'は変イ長調、B"はホ長調と転調しつつ変奏される。A"は変イ長調で冒頭の旋律がfffで高らかに奏され、Cの情熱的な和音連打を経て、A"'は変ホ長調に戻り、技巧的な装飾音が施される。 - Cavalheiro fantasma (Chevalier fantôme) (1910?) 亡霊の騎士
「亡霊の騎士」という伝説がブラジルか、またはヨーロッパにあったのだろうか不明で、物語のような曲である。増三和音が鳴る前奏に引き続き、幻想的な二つの主題が変奏されつつ繰り返される。曲の後半はギャロップのような音形が最初は静かに途切れ途切れ、やがて音量を増しながら激しく奏されて終わる。 - E o mar respondeu à selva (Et la mer répondit á la vaste forêt) そして海は森に答えた
楽譜の冒頭には米国の詩人ヘンリー・ワズワース・ロングフェローの叙事詩『エヴァンジェリン―アカディアの物語― Evangeline, A tale of Acadie』の最後の一節が以下のように記されている(日本語訳は、下條信敏 (1953)「エヴァンヂェリーンに就いて」『文芸と思想:福岡女子大学国際文理学部紀要』 (6), 37-47, 1953-01. より引用しました。)
「程近き大洋の濤声は洞の巖に高鳴りて、森の悲しき調べに淋しげに応ふ。 While from its rocky caverns the deep-voiced, neighboring ocean Speaks, and in accents disconsolate answers the wail of the forest.」
曲は演奏時間約10分と長く、全体として波の怒涛やさざ波が物語を語るような曲である。変ニ長調で、概ねA-B-C-A'の形式。Aは低音オクターブ全音符に高音付点音符のモチーフ、Bは狭い音域を上下する不安げなモチーフが展開され、Cは3オクターブを下るモチーフの繰り返しの展開され、A'で冒頭のモチーフが静かに回想されて終わる。
- Tarde na clareira (Après-midi dans la clairière) 林間の空き地の午後
1910?
- Paisagens tropicais, Série burlesca-3ª série (Paysages troipicaux, Série burlescque-3me série), Op. 19 熱帯の風景集、戯けた作品集ー第3集、作品19
- Sapos e gias ヒキガエルとナンベイウシガエル
- Papagaios e macacos オウムとサル
- Danse nègre 黒人の踊り
1903年7月にパリでフローエス自身がこの曲を演奏したとする記録がある。フローエスが住むブラジル北東部は、奴隷としてアフリカから連れて来られた黒人が多く住む地方であり、この曲はフローエスの作品の中でも数少ない「ブラジル民族主義」的な曲と言ってよく、彼のピアノ曲では比較的知られている曲である。変ホ長調、前奏-A-B-A'形式。前奏は、後のAで現れるリズムが遠くで鳴っているが如く途切れ途切れにppで現れ、徐々にそのリズムの姿を現していく。Aは16分音符と8分音符の両手交互打鍵による踊りのモチーフが現れ(下記の楽譜)、波のようにクレッシェンド・デクレッシェンドしつつ盛り上がる。

Danse nègre, Paisagens tropicaes (Série burlesca-3ª Série)、13-18小節、A melhor música do mundo, Tomo IX より引用
Bは突然変ト長調になり、変ハ長調〜ホ長調〜と転調していくのが色彩的。A'は変ホ長調に戻り、踊りは更に盛り上がりfffで両手オクターブ和音が連打されるも、間もなく萎むように音量を減らして消えるように終わる。なお1941年にフローエスは楽譜の改訂を行い、一部の音の変更や終止部の和音の追加を行なっている(下記の楽譜)。

Danse nègre, Paisagens tropicaes (Série burlesca-3ª Série)、96-98小節、A melhor música do mundo, Tomo IX より引用

Danse nègre, Paysages tropicaux (-III- Série burlesque)、97-100小節、Autógrafo より引用 - Preguiça no galho 枝にぶら下がったナマケモノ
作曲年代不詳
- Op.20 作品20(作品全体の題名は不明)
- Prélude sur les lettres a, e, a, g, d, a, piano solo ou dois pianos 文字a, e, a, g, d, aによる前奏曲(ピアノ独奏または2台ピアノ)
- Fantasia in E sur les lettres a, e, a, g, d, a 文字a, e, a, g, d, aによる幻想曲
- Fuga sur les notes a, e, a, gis, d, a (1909), (Fughetta a, e, a, gis, d, a para dois pianos) 音名a, e, a, gis, d, aによるフーガ(2台ピアノのための音名a, e, a, gis, d, aによるフゲッタ)
- Aria in G ト長調のアリア
ト長調、A-B-A'形式。Aは静かなさざ波のような8分音符連打の左手伴奏にのって、息の長い穏やかな旋律が奏される。Bはハ短調になり、一転して嵐のような32分音符アルペジオが奏され、激情するような旋律がオクターブ和音で奏される。 - Allegro in D ニ長調のアレグロ
- Rondo grotesco (Rondeau grotesque) in A sur les lettres a, e, a, g, d, a (Estudo ritmico) 文字a, e, a, g, d, aによるグロテスクなロンドイ短調
- Toccata sur les lettres a, e, a, g, d, a 文字a, e, a, g, d, aによるトッカータ
- Sobre um Natal francês フランスのクリスマスについて
Sylvio Deolindo Fróesのピアノ曲楽譜
Escola de Música da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
- Paisagens tropicais (2ª série), Tarde na clareira, Op. 18, no. 1
Casa Bevilacqua
- 3 pièces (Petite suite), Barcarolle-Nocturne (fa min.), Op. 1, n. 1
- 3 pièces (Petite suite), Allegro scherzando (la b maj.), Op. 1, n. 2
- 3 pièces (Petite suite), Bluette (fa maj.), Op. 1, n. 3
- Paisagens tropicaes 1ª série, Vozes d'alva (Voix du matin), Op. 17, n. 2
- Paisagens tropicaes 1ª série, Queixas da velha árvore (Plaintes du viel arbre), Op. 17, n. 4
- Paisagens tropicaes 1ª série, O que diz a selva ao mar (Ce que la forêt raconte à la mer), Op. 17, n. 5
- Paisagens tropicaes 1ª série, Dansa de folhas seccas (Bal de feuilles mortes), Op. 17, n. 6
- Paisagens tropicaes, Série burlesca-3ª série, Danse nègre
Carlos Wehrs
- Paisagens tropicais 2ª série, Tarde na clareira (Après-midi dans la clairière), Op. 18, n. 1
- Paisagens tropicais 2ª série, Cavalheiro fantasma (Chevalier fantôme), Op. 18, n. 6
Mangione
- Aria in G
G. Ricordi
- Paysages troipicaux 2me série, E o mar respondeu à selva (Et la mer répondit á la vaste forêt), Op. 18, n. 7
F.M. Geidel, Leipzig
- Marche funèbre (Trauermarsch) du Sextour en fa# mineur, Op. 7, Arrangement pour 2 pianos par l'auteur
- Capriccio, Op.13
The University society, Inc., New York
- A melhor música do mundo, Tomo IX
- Paisagens tropicaes, Série burlesca-3ª série, Danse nègre, Op. 19, No. 3
斜字は絶版と思われる楽譜
Sylvio Deolindo Fróesのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
Silvio Deolindo Fróes
Sons da Bahia
- Evocation, Op. 4 - poesia de Adolfo Bezerra de Menezes
- Un petit cimetiére - poesia de Adolfo Bezerra de Menezes
- Fleur Mourante - poesia de Charles-Hubert Millevoye
- Dança das folhas secas, Op. 17, N. 6*
- Dimanche au village (Domingo na aldeia), Op. 7, N. 7*
- Prelúdio, Op. 17, N. 1*
- Rajada, Op. 17, N. 3*
- Queixas da velha árvore, Op. 17, N. 4*
- Vozes d’alva, Op. 17, N. 2*
- O que diz a selva ao mar, Op. 17, N. 5*
- Matinata, Op. 10, N. 1 - poesia de Gabriel D'Annunzio
- Melopée, Op. 10, N. 2 - poesia de Gabriel D'Annunzio
- La sirinetta, Op. 9 - poesia de Gabriel D'Annunzio
Graça Reis (voz), Paulo Gondim (pf), Fernando Lopes (pf)*
O Piano Brasileiro - Século XIX (2CDs)![]()
![]()
Paulus, 001726
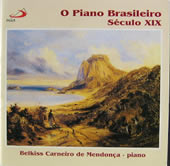 |
CD 1
CD 2
|
Belkiss Carneiro de Mendonça (pf)
Sylvio Deolindo Fróesに関する参考文献
- Ivana Pinho Kuhn. Sílvio Deolindo Fróes: Profile of an early twentieth-century brazilian musician. Journal of Historical Research in Music Education 22(1):38-46, 2000.