Manuel Gómez Carrilloのページ
Manuel Gómez Carrilloについて
マヌエル・ゴメス・カリージョ Manuel Gómez Carrillo は1883年3月8日(1881年とする文献もあり)にアルゼンチン北部のサンティアゴ・デル・エステロで生まれた。彼の父は熱心なカトリック信者であり、ゴメス・カリージョを隣州のサルタの神学校に入学させた。神学校の聖歌隊で音楽を勉強した彼は、13歳の時には聖歌隊の副指揮者を務めていたとのこと。ゴメス・カリージョの優れた音楽的才能に気付いた神学校の校長は、15歳の彼を、優れた音楽教師のいる隣州のカタマルカの神学校に転校させた。カタマルカでは本格的にピアノをソルフェージュを習っている。
その後、父の勧めでゴメス・カリージョは首都ブエノスアイレスへ出て数学物理学を学んだらしい。それでも音楽は独学で続け、1908年頃からは音楽教師をしている。
故郷に戻った彼は1917年、ピアノ教師のMaría Inés Landeta Césarと結婚。6人の子供をもうけた。娘のInés Gómez Carrilloはアルゼンチンで有名なピアニストになった。また3人の息子と1人の娘はアカペラ四重唱のクアルテト・ゴメス・カリージョ Cuarteto Gómez Carrillo を結成し1940年代〜1950年代に活動した。
1918年、ゴメス・カリージョは国立トゥクマン大学よりアルゼンチン北部の民謡の調査を委嘱された。彼は北部地方のカタマルカ州、フフイ州、ラ・リオハ州、 サルタ州、トゥクマン州、サンティアゴ・デル・エステロ州をくまなく旅行して調査・研究を行い、1920年には論文を発表した。また彼が蒐集・採譜した民謡は『アルゼンチン北部地方のモチーフ、舞曲と歌曲集 Colección motivos, danzas y cantos regionales del Norte Argentino』という題名で全5集が出版された。
1936年にはロサリオに移住し、師範学校で音楽を教えた。1943年にはブエノスアイレスに移り、翌年には国立伝承研究所 Instituto Nacional de la Tradición(現在はInstituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano)の副所長に就任した。
1968年3月17日、ブエノスアイレス州サン・イシドロで亡くなった。
ゴメス・カリージョは民族音楽研究が主たる業績の音楽学者であったが、作曲家でもあり、バレー音楽《La Salamanca》、舞踊音楽《La Telesita》(1925?)、また北部アルゼンチン民謡を題材にしたいくつかの室内楽曲や歌曲を作った。ピアノ曲は下記の通りで、多くの作品が彼の故郷サンティアゴ・デル・エステロ州の民謡や踊りを元にしていて、フォルクローレの素朴な響きムンムンである。アルゼンチン北部の民謡って、正直の所あまり明るい雰囲気とは言えないので彼のピアノ曲もどこか憂いを帯びて地味であるが、和声など作曲技法は一流です。
Manuel Gómez Carrilloのピアノ曲リストとその解説
下記の作品以外にも彼がアルゼンチン北部を回って採譜した楽譜集『アルゼンチン北部地方のモチーフ、舞曲と歌曲集 Colección motivos, danzas y cantos regionales del Norte Argentino』全5集にはピアノ独奏の楽譜が多数ある。それらは民謡や舞曲の採譜が元とは言え、ゴメス・カリージョが施したピアノ編曲は質が高く、多くはピアノ独奏曲としても通用する内容である。(ヴィラ=ロボスによる楽譜集《ギア・プラチコ Guia prático》に似た性格であるが、ヴィラ=ロボスのそれより以前にゴメス・カリージョがこの楽譜集を作ったのは特筆すべきであろう。)
1905-1910
- Cuatro valses 4つのワルツ集
- Re Mayor ニ長調
- Sol Mayor ト長調
- Re Mayor ニ長調
- La Mayor イ長調
1912
- Bazar Buenos Aires, Tango compadre ブエノスアイレスの市場、タンゴ・コンパドレ
1915頃
- Tenga mano!!, Tango お手をどうぞ!、タンゴ
アルゼンチン北部の民謡や舞曲を元にした作品が多いゴメス・カリージョだが、若い時は都会のポピュラー音楽であるタンゴも作曲している。イ短調、A-B-B'-A-B形式。Aはイ長調~イ短調が4小節毎に入れ替わり、優雅な旋律が流れている思いきや、いきなりバンドネオンの鋭い刻みを思わせる16分音符ユニゾンが現れる。BとB'はイ短調になり、アルゼンチン民謡《Zamba de Vargas》を、原曲はZambaなので3/4拍子だが、それが2/4拍子のタンゴに編曲されて奏される。
1916
- Mi poema, Valse 私の詩、ワルツ
-1920
- Rapsodia santiagueña, inspirada en motivos populares de Santiago del Estero サンティアゴ狂詩曲、サンティアゴ・デル・エステロ地方の民謡の主題に霊感を受けて
演奏時間約12分の大作。1920年に初演された。ゴメス・カリージョの故郷であるアルゼンチン北部のサンティアゴ・デル・エステロ州の光景を絵巻のように描いた作品で、彼自身が現地調査で採譜したいくつもの旋律が次々と現れ、正に民族主義作曲家ゴメス・カリージョを象徴するような傑作である。冒頭はヘ短調で、楽譜には「サンバ“4月7日”を模して Int. de la Zamba "7 de Abril"」および「リストを思い浮かべで Pensando en Liszt」と記されていて、(サンティアゴ・デル・エステロ州およびトゥクマン州の)民謡〈4月7日 7 de Abril〉の旋律がリストのハンガリー狂詩曲第2番の冒頭を思わせる劇的な変奏で始まる。次は楽譜に「サンバ“ラ・エストレリータ”Zamba "La Estrellita"」と記された、変イ短調のサンバのリズムの哀愁漂う主題で、旋律および伴奏はアルペジオや両手オクターブへと派手に盛り上がる。次の主題は異名同音の嬰ト短調になり、「ビダーラ VIDALA」と記された(ビダーラとは先住民の音楽を起源とするアルゼンチン北部の民謡)悲しげな旋律は民謡〈哀れな私の愛しい人 Pobre mi negra〉で、ソ♯のドリア旋法で静かに奏される。これも3連符和音連打や両手オクターブ和音へと派手に展開され、また萎むように静かになる。次は「サンバの雰囲気で Aire de Zamba」と記された、突然の左手16分音符アルペジオにのったオクターブ和音の主題が華やかに奏され、ホ長調〜変ト長調〜変イ長調と転調する。そのテンポのまま楽譜に「ワルツのテンポで Tempo di Valse」と記された変ニ長調の華やかな旋律が奏される。続いて現れるのは「サパテアード Zapateado」と記されたヘ長調の3/4拍子の活発な主題で、楽譜の右手の軽快なリズムには「ギターをかき鳴らすように ragueo de guitarra」と、左手低音のバスには「ボンボを打つリズムを模して Imitando los golpes ritmicos del bombo」と記されている(ボンボとは主にアルゼンチン北部やボリビアの民族音楽で使われる大太鼓)。このサパテアードは最初は静かにpで、徐々に音域を増してffまで盛り上がる。途中では「チャカレラ Chacarera」と記された旋律や、またサンティアゴ・デル・エステロ州民謡「エル・エクアドル El Ecuador」も現れる。最後はニ短調で、「民謡 Canción popular」と記された旋律がオクターブ和音で荘厳に奏され、華やかなコーダで終る。この曲はフランスのピアニスト、モーリス・デュメスニルに献呈され、彼によってパリでも演奏され、また1923年に管弦楽曲にも編曲された。
1922
- Danza santiagueña サンティアゴ舞曲
7分程の曲だが、楽しい雰囲気や旋律の優美さは前作の《サンティアゴ狂詩曲》より上かな。変イ長調、A-B-C-A'-コーダの形式。楽譜冒頭の拍子記号は3/4 (6/8) と記されていて、Aはアルゼンチンの民族舞踊ガトのリズムで、楽譜に「(ギターの)かき鳴らしを模して Imitando un rasgueo」と記された3拍子の伴奏にのって右手旋律は時々♩. ♩♪となるので3/4と6/8のポリリズムになっている。Aの後半は両手オクターブで、踊りが興にのったような華やかな響きだ。Bは変ロ短調で、楽譜に「ボンボを模して Imitando el bombo」と記された左手低音のオスティナートのリズムにのって「ケーナの牧歌 Idilio de quenas」と記された右手高音の三度重音の旋律が哀愁たっぷりと静かに奏される。Cはへ長調で、テンポを落としたアンダンテになり、民謡〈松の木の下で Bajo un coposo pino〉の旋律がしっとりと奏され、これが繰り返される毎に両手オクターブ和音の壮麗な響きになったり、内声が半音階進行になったり、変イ長調に転調したりと色彩的だ。
1924
- El mistolero, Gato santiagueño エル・ミストレート、サンティアゴ地方のガト
ト長調、曲の構成はアルゼンチンの民族舞踊ガトの形式に概ね沿っており、楽譜に順にIntroducción〜Danza〜1er. Zapateo〜Vuelta〜2º Zapateo〜Vuelta finalと記されていて、その順に演奏される。陽気な曲で、Danzaで朗々とした旋律が現れ、1er. Zapateoで愉快なリズムが刻まれ、Vueltaは4小節のみでDanzaの旋律が現れ、2º Zapateoでは右手高音部で再び愉快なリズムが刻まれる。
1934
- Fiesta criolla, Panorama inspirado en motivos santiagueños クリオージョの祭り、サンティアゴ民謡の主題に霊感を受けたパノラマ
- Alegría - Allegro vivo 喜んで
- Canción triste - Andante 悲歌
- El amor en los pañuelos - Vivo ハンカチの中の愛
- Siempre alegría - Allegro vivo 常に喜んで
1937
- Danza del cuervo, inspirada en el baile popular santiagueño "El Pala - Pala" カラスの踊り、サンティアゴの有名な踊り「パラ・パラ」に霊感を受けて
「パラ・パラ」 とはサンティアゴ・デル・エステロ州南部の民族舞踊の一つ。変ニ長調、A-B-A-コーダの形式。軽快で流れるような旋律の曲。Bはホ長調~ト長調~ホ長調となる。
1938
- La huahua, Gato salteño ラ・ウアウア、サルタのガト
イ長調、構成は楽譜に記されている通りーIntroducción〜Danza, vuelta redonda〜1er Zapateo〜Media vuelta〜2º Zapateo〜Vuelta redonda (giro)ーの順。Introducciónは楽譜に「ギターのつま弾きを模して Imitando un punteado de guitarra」と記され、8分音符のリズムがウキウキとしてくる。Danza, vuelta redondaは「アルフレド・コレア氏により採譜された民謡の“ガト”の主題 Tema de "gato" popular dictado por Don Alfredo Correa」と記され、伸びやかな旋律がガトのリズムにのって奏される。Zapateoは生き生きとしたリズムだ。繰り返しだらけの曲だが、段々盛り上がっていく様が舞曲らしくてイイ。
作曲年代不詳
- Château Enchanté, Vals cantabile 魔法の城
- Impresiones de mi tierra, Suite 我が故郷の印象、組曲
- La Donosa, Zamba 優雅に、サンバ
- La estrellita, Zamba 小さな星、サンバ
- La Mocha, Vals ラ・モーチャ、ワルツ
- La muchachada, Milonga ラ・ムチャチャーダ、ミロンガ
- Morceau lyrique, Preludio 抒情的な小品、前奏曲
- Sumaj..! Gato スマック!、ガト
ニ短調、ガトの形式に概ね沿っており、Introducción〜哀愁帯びた三度重音の旋律のDanza〜右手分散和音の1er. Zapateo〜4小節のみのVuelta〜2º Zapateo〜Vuelta finalの順に演奏される。 - 18 de Infantería, Marcha 歩兵第18連隊、行進曲
Manuel Gómez Carrilloのピアノ曲楽譜
Ricordi Americana
- Danza santiagueña
- El mistolero, Gato santiagueño
- El Tunante catamarqueño, Danza nativa tradicional
- La huahua, Gato
- Sumaj..! Gato
Breyer Hnos.
- Tenga mano!!, Tango
Casa Romano
- Danza del cuervo, inspirada en el baile popular santiagueño "El Pala - Pala"
Universidad de Tucumán
- Rapsodia santiagueña
1999年に出版された下記の本に《Fiesta criolla》の初版譜のファクシミリが載ってます。
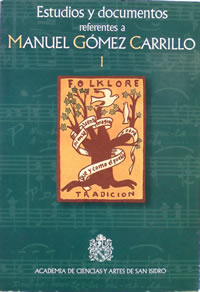 |
|
斜字は絶版と思われる楽譜
Manuel Gómez Carrilloのピアノ曲CD
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Obras de Manuel Gómez Carrillo![]()
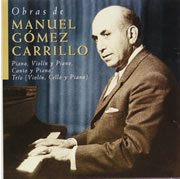 |
|
Inés Gómez Carrillo (pf), Leo Viola (Cello), Susana Naidich (Canto), Edgardo Cataruzzi (Violin)
ゴメス・カリージョの作品を集めた貴重な録音。ピアノ曲は5曲収録されている。ピアノを弾いているイネス・ゴメス・カリージョ (1918-2014) はマヌエル・ゴメス・カリージョの娘で、《Fiesta criolla》は1934年に彼女により初演された。彼女は2014年6月22日に95歳で死去された。
Obras para piano de E. Drangosch, C. Piaggio, M. Gómez Carrillo![]()
CD Tradition, TR050513
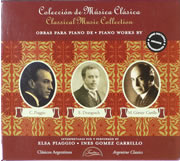 |
|
Elsa Piaggio (pf), Inés Gómez Carrillo (pf)
Los Compositores Académicos Argentinos y El Tango (1867-2002)![]()
Argentmúsica
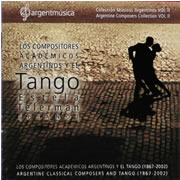 |
|
Estela Telerman (pf)
2002、2003年の録音。
Sur: Piano Music from Argentina![]()
![]()
Albany records, TROY1972
- Para empezar a volar (Lillán Saba)
- Tres marías (Lillán Saba)
- Tres danzas (José Resta)
- Vals miraflores (Juan José Ramos)
- Fiesta criolla (Manuel Gómez Carillo)
- Triste (Miguel Francese)
- Recuerdos de mi tierra (Lía Cimaglia)
- Aire de milonga (Arturo Luzzatti)
- Milonga, Op. 2 (Leonardo Brunelli)
- Milonga gris (Carlos Aguirre)
- Bocetos del litoral (Adolfo Cipriota)
- Levante (Osvaldo Golijov)
Agustin Muriago (pf)
2024年のリリース。
Manuel Gómez Carrilloに関する参考文献
- Juan María Veniard. Estudios y documentos referentes a Manuel Gómez Carrillo 1. Academia de Ciencias y Artes de San Isidro 1999.
- Juan María Veniard. Estudios y documentos referentes a Manuel Gómez Carrillo 2. Academia de Ciencias y Artes de San Isidro 2001.
- Luis Gonzalo Melicchio. Manuel Gómez Carrillo. Consideraciones en torno al concepto de autenticidad referido a la interpretación de su obra pianística. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño 2018.