Francisco González Gamarraのページ
Francisco González Gamarraについて
フランシスコ・ゴンサレス・ガマラ Francisco González Gamarra は1890年6月4日、クスコに生まれた。彼の生家はかつてのクスコ王国の王宮の壁の上に建っていたとのことである。彼の父は趣味で絵を描き、母は音楽好きでピアノを弾いたとのこと。ゴンサレス・ガマラは小学生の頃から絵画などに優れていた。一方で音楽にも才能を伸ばし、1905年にペルー大統領ホセ・パルドがクスコを訪問した際に催されたパーティーでピアノを弾き、ヴァイオリニストのレアンドロ・アルビーニャ Leandro Alviña と共演してスッペの《詩人と農夫》の序曲を演奏したとのことである。1909年にクスコのサン・アントニオ・アバド大学文学部に入学して学んだ。1910年にはリマで発行されていた雑誌「多様性 Variedades」が雑誌専属のカリカチュア画家を募集するコンクールを催すと、ゴンサレス・ガマラはこれに応募して一等賞となる。間もなくリマに移って国立サン・マルコス大学文学部に転校して学びつつ、雑誌「Variedades」に掲載するカリカチュアを描き続けた。
1915年に提出した卒業論文『ペルーの芸術より De Arte Peruano』でゴンサレス・ガマラは先コロンブス期のペルーの装飾絵柄について詳述し、高い評価を得る。これにより1918年に彼は米国を訪れ、ニューヨークやワシントンD.C.でペルーの伝統芸術の展覧会を催し、また彼自身の絵画も展示された。1925年から1928年まではヨーロッパに滞在し、イタリアやフランスで「ペルーの芸術 D'art peruvien」と題した展覧会を催した。1928年に帰国すると、ペルーの伝統芸術を国内外に紹介した功績で政府からペルー太陽勲章 La Orden del Sol を授与された。この頃にSofía Umeres Rodríguezと結婚し、三人の子どもをもうけている。1937年には『十戒の形式によるペルー芸術の理論 Teoría del arte peruano en forma de decálogo』を発表した。1945年にはIgnacio Merino国家賞を受賞、1950年にはドゥンケル・ラバージェ国家賞を受賞した。リマの国立芸術大学の校長を1949年から1950年まで務めた。
1972年7月15日、リマで亡くなった。
ゴンサレス・ガマラの描いた絵画は油絵、水彩画、カリカチュア、ペン画などに及び、ペルーの歴史やクスコの風景や人物(特に先住民)について描いた作品が多い。
ゴンサレス・ガマラは画家として有名であったが、それに加えて彼はピアニスト・作曲家であった。管弦楽曲では《管弦楽のための組曲 Suite para orquesta》(〈儀式の踊り Danza ritual〉〈野原の踊り Danza campestre〉〈打ち上げ話 Confidencias〉の3曲から成る)、下記の《クスコ、5つの音楽の随筆》から抜粋した管弦楽編曲《ヤラビとカシュワ Yaravi y Qhaswa》がある。また歌曲《2つの歌曲集 Dos canciones》がある。
彼のピアノ曲は、おそらく若い頃に作曲したマズルカ、夜想曲、ワルツはショパンの影響が強いが、それ以降に作曲されたと思われる《ガルシラーソ・インカ・デ・ラ・ベーガ (1539-1616) へのオマージュ》、《風景第1番、クスコの月の夜》、《クスコ、5つの音楽の随筆》(女性独唱および混声合唱の部分もあり)はいずれも旋律はほぼペンタトニックで、リズムはインカ帝国時代より存在するとされる舞曲だったりと、徹底的なペルー民族主義音楽である。ピアノ技法も結構高度で、正に知られざるピアノ音楽の作曲家である。
Francisco González Gamarraのピアノ曲リストとその解説
- Homenaje a Garcilazo Inca de la Vega 1539-1616 (ca. 1939) ガルシラーソ・インカ・デ・ラ・ベーガ (1539-1616) へのオマージュ
ガルシラーソ・インカ・デ・ラ・ベーガ(インカ・ガルシラーソ・デ・ラ・ベーガ Inca Garcilaso de la Vega と記すのが一般的)は、1539年ペルーのクスコ生まれの歴史家・作家である。彼の父はスペイン生まれで、ペルーに渡りピサロらと共にインカ帝国を滅ぼした征服者の一人で、一方母はインカ皇帝ワイナ・カパックの孫娘であり、ベーガはペルー史上最初期のメスティーソ(白人とラテンアメリカの先住民の混血)である。ベーガは1561年にスペインに移住した後、インカ帝国の盛衰を記した壮大な年代記『インカ皇統記 Comentarios Reales de los Incas』を書き、1616年にスペインのコルドバで亡くなった。ゴンサレス・ガマラは1925年より米国やペルーでベーガの肖像画を何度か描き、その後1959年にはベーガの墓のあるスペイン・コルドバの聖マリア大聖堂 Catedral de Santa María de Córdoba(メスキータ Mezquita と呼ばれることが一般的)にベーガの肖像画を描き、スペイン政府より文民功労勲章を授与されている。このピアノ曲は、1941年に出版された楽譜に「クスコにて彼の生誕四百周年を祝い讃えた作品」と記されていることより、1939年頃の作曲と思われる。イ短調、A-A'-B-A"形式。Aの冒頭はギターが静かに鳴るような左手十度和音にのって、右手に語るようなペンタトニックの旋律が昔語りをするように哀愁たっぷりと奏される。続いて左手3連符アルペジオの伴奏が始まり、右手に冒頭の旋律が内声の和音を伴って繰り返される。ここでは左手アルペジオや右手内声の中に半音階進行が含まれ、それによる減三和音や増三和音が絶妙で豊かな響きを醸し出し、また4/4拍子と5/4拍子が1小節毎に交替するのが旋律に(レチタティーヴォのような)即興的な節回し感を与えている(下記の楽譜)。A'はホ短調になってAが変奏される。Bは3/4拍子に変わり、踊りのような伴奏にのって可憐な旋律が繰り返される。A"はホ短調のままで、両手和音の重々しい響きの中でAの旋律が再現され、最後はピカルディの三度で終わる。

Homenaje a Garcilazo Inca de la Vega 1539-1616、9-14小節より引用 - Kosko, 5 ensayos musicales, homenaje a los paises de América con motivo de la celebración del IV centenario de la fundación de Lima (ca. 1935) クスコ、5つの音楽の随筆、リマ創設四百年祝賀を記念しアメリカ大陸各国へのオマージュ
この組曲は女性独唱、混声合唱およびピアノのための作品であるが(第1曲はピアノ独奏のみ、第5曲の一部には「ピンクーユ(ピンキージョ)」(後述)という縦笛のパートがある)、ピアノ独奏部分が全体の7割くらいを占めていて、ピアノパートは結構技巧的でもあり解説に含めました。歌詞は全てケチュア語(ペルーを中心とした先住民言語の一つ)で、音楽は五音音階を多用し、インカ帝国時代を起源とされている舞踊のリズムが用いられるなど徹底して先住民の音楽に近いものを作曲しようとしているが、ピアノの書法や和声進行などはゴンサレス・ガマラの独創性に満ちており、彼の代表曲に相応しい見事な作品である。以下の解説で、独唱や合唱の但し書きが無い部分はピアノ独奏である。- Willka-mayu ウィルカ・マユ
駐ペルー米国大使Fred Morris Dearingに献呈。ウィルカ・マユとはケチュア語で「聖なる川」という意味。ペルー南部を流れるウルバンバ川の中流部はかつてウィルカ・マユと呼ばれ、川沿いにはマチュピチュなどのインカ帝国の遺跡が残されている。ピアノ独奏で、A-B-A'形式。Aはペンタトニックのモチーフが調を変えながら繰り返され、その間に川のせせらぎ音を思わせる3連符が現れたり、32分音符分散和音が重なったりする。Bは3/4拍子になり、新たなペンタトニックのモチーフが現れ、ここでも高音部の32分音符分散和音が重なる。A'は幅広いアルペジオ、両手オクターブ、32分音符半音階などが加わって技巧的に変奏される。 - Kosko napayacuykin クスコ万歳
駐ペルーメキシコ公使Juan Manuel Albarez del Castilloに献呈。概ねト短調。冒頭はピアノ独奏で、高音部32分音符アルペジオがサワサワと鳴り続け、後で現れる女性独唱の旋律がゆっくりと左手中音部に奏される。続いて合唱と独唱の部分となる。まず朗々とした歌が混声四部合唱で歌われる。楽譜に記されているケチュア語の歌詞は、
「クスコ!母なる土地!、サパ・インティ(太陽神)が昇り、サパ・インカ(インカ皇帝)が治める場所、万歳! Kosko! mama llajta!, Sapan Intij pakarinan, Sapan Inkaj camachinan, Napaycuykin!」
とある。続いて少しテンポを速め、ピアノのブンチャッブンチャッの伴奏にのって女性独唱が(楽譜では「詩節 estrofa」と記され)、
「遠い地から、巡礼者である、私は来た、信仰のために、ああクスコ!、私の燃えるような情熱を沈めてくれ! Kjaru llajtamantan, puririmurkani, Kampi tajyachispa, Sonko-yuyainiita, Ailly Koskollay!, Sinchi-munainiira, Kampin tasnurisaj!」
と可憐に歌う。再び混声四部合唱が最初と同じ旋律で、
「クスコ!母なる土地!ピューマが生まれ、コンドルに守られる場所、万歳! Kosko! mama llajta!, Pumacunaj wachaskan, Kunturcunaj uywaskan, Napaycuykin!」
と力強く歌う。最後はテンポを速めたAllegretto vivoの部分になる。まず両手16分音符ユニゾンが前奏のように奏されるが、音階を上行する時はソ-ラ-シ♭-ド-レ-ファ♯-ソで、下行する時はソ-ファ♮-ミ♮-レ-ド-シ♭-ラ-ソと独特の音階なのが面白い。続いて楽譜に「カシュワ Kjaswa」と記された部分になり(カシュワとはケチュア語で「輪になっての踊り」という意味で、インカ帝国時代が起源であろうとされている踊りである)、左手♪♬♪♬の快活な踊りのリズムにのって右手にペンタトニックの旋律が奏され、楽譜には「インディオの歓声を模して」と記された音高の無い詞が記され、
「万歳!クスコよ!愉快になろう!楽しもう!我々は着いた! Aylly! Koskollay! Cusiricusun! Kjochuricusun! Chayamuscanchismanta!」
と皆が声を上げる。 - Sajsa-uma-pukara サクサウマ・プカラ
駐ペルーチリ大使Luis Subercaseauxに献呈。サクサウマ(サクサイワマン)はクスコの郊外にあるインカ帝国時代の城塞のこと。冒頭はピアノ独奏で、低音オクターブが重々しく鳴るのにのってケーナを思わせるへ短調の高音のモチーフが静かに現れ、続いて重音のペンタトニック音階が3オクターブを上下して荘厳な響きを醸し出す。次にニ短調になると、新たな高音の旋律が弱々しく奏される。次に行進曲のようなリズムのピアノにのって混声四部合唱が、
「万歳! 我々の皇帝は永遠に!我々の神は永遠に、万歳! Aylly! Kausachun Inkanchis! Apunchis Kausachun! Aylly!」
と高らかに歌う。最後はニ長調になり、行進曲のような部分と、カシュワの快活な踊りのリズムの部分が交互に現れ、いずれもペンタトニックの旋律が奏される。 - Machu-pijchu マチュ・ピチュ
駐ペルーブラジル大使Jorje Arberto Ipanema Moreyra(楽譜表記のママ)に献呈。冒頭のピアノ独奏は前奏のような部分で、重々しい和音にのってつぶやくような旋律が嬰ハ短調〜ホ短調〜ト短調と転調しながら繰り返される。次はト短調または変ロ長調で、太鼓の音を思わせる低音♩♫がオスティナートで続き、高音部にケーナを思わせるペンタトニックの旋律が奏される。次の部分は楽譜に「太陽の歌 inti-taky」と記され、ゆっくりとしたGraveのテンポでト短調ペンタトニックの旋律を女性独唱が哀愁たっぷりと歌う。歌詞は、
「インティライ、インティライ、インティライ、私を見て、私を聞いて:昼、夜、あなたは仰った、光、闇、あなたは作った、インティライ Intillay, Intillay, Intillay, Cjawarimuway, urarimuway: Punchau cachun, Tuta cachun, Nir'kanki, K'anchaytataj, Lacjatapas, Kamar'kanki', Intillay」
で、続いて混声三部合唱が同じ歌を繰り返す。以降は再びピアノ独奏となる。まず楽譜に「intipaj」と記さた、ホ短調の左手十度和音にのって寂しげな旋律が高音部に奏され、続いて♪♬♪♬のリズムにのって勇ましい旋律が奏される。最後に、最初に現れたト短調または変ロ長調の低音♩♫と高音ケーナを思わせる旋律が再現されて終わる。 - Chuki-llautu チュキ・リャウトゥ
駐ペルーアルゼンチン大使Antonio de Mora y Araujoに献呈。Chuki-llautuとは女性の名前またはお祭りの衣装のことらしく、この曲の歌詞は恋物語のようである。曲は楽譜にI、II、IIIと記された三部から成る。I 部は変ホ短調。楽譜のピアノパートの上に「ピンクーユ(ピンキージョ)を吹く羊飼いAcoya tocando "pincuyllu"」と記された息の長い旋律があり(ピンクーユとはペルーの民族楽器でリコーダーに似た縦笛)、ピアノ高音部の32分音符アルペジオ伴奏がpppでそよ風のように鳴り続ける。II 部はト短調。前奏は楽譜に「鳥の歌を模して como imitando el canto de un ave」と記され、鳥の鳴き声宛らの旋律が現れる。続いて楽譜に「ハラウィ jawawi」と記された部分になり(ハラウィとはインカ帝国時代が起源であろうとされている叙情歌の一種である)、まず6/8拍子でチュキ・リャウトゥを演ずる女性独唱が可憐な歌を歌う。歌詞は、
「泉よ、私の問いを聞いて下さい、そして密かに教えて下さい、生きていくのはどんなに辛いのか、死ぬことは取るに足らぬことか、私の哀れな心は傷ついている、傷ついている Pujyucuna, Uyaricuway tapuricus'kayta, Pacapacallapi, Willariway, sasancusay, Puchunwanuy, Son'kollaymilla K'iri, K'irik'irinannan」
とある。続いて混声四部合唱が3/4拍子で、
「チュキ・リャウトゥ、可憐な小さな花、自分を苦しめないで、泣かないで Chuki-llautu, Mutmu t'icacha, Ama llakjichu, Ama wua'kaychu」
と歌う。続いてホ短調に転調すると、カシュワの♪♬♪♬の軽快なピアノ伴奏にのって女性独唱が、
「私の好きな人、見失ったわ、この辺り、あの辺り、ああ!、見つけるわ、この辺り、あの辺り、ああ!、見つけるわ Warmayanachayta, Chincachicur'kani, Caypicha, chayllapicha Ay!, Tariracapusaj, maypicha, chayllapicha Ay!, Tariracapusaj」
と歌われる。III 部はピアノ独奏でロ短調。低音部オクターブの堂々とした旋律は楽譜に「太陽が出始める Comienza a despuntar el Sol」と記され、初めppで始まり、太陽の煌めきのような4オクターブ上行アルペジオの装飾を伴いながら徐々に音量を増し、最後はfffの壮麗な響きで終わる。
- Willka-mayu ウィルカ・マユ
- Paisajes musicales, Serie de aires incaicos 音楽の風景、インカの民謡の連作
- Paisaje Nº 1, Noche de luna en el Cuzco (1914?) 風景第1番、クスコの月の夜
この曲は(楽譜に記された)上記の題名からすると組曲の第1番となるのだが、第2番以降が作曲されたかは不明である。管弦楽版もあるらしい。クスコの月夜の静かな風景と、そこに現れた先住民の踊りが夢か幻のように現れて熱狂的に盛り上がるも、また消えて静かな夜となるーといった何とも幻想的な作品である。イ短調、A-B-C-A-コーダの形式。楽譜のAの冒頭には「静かで穏やかな動きで、弱々しく投げやりで、深い憂うつを表現して」と記されていて、3/4拍子のゆったりとしたテンポで、ケーナの音色を思わせるペンタトニックの旋律が哀愁たっぷり奏される。Bはへ長調で、楽譜に「カシュワの音楽(先住民の踊り) Aire de "khashua" (Danza indígena)」と記された2/4拍子の速いテンポになり、左手伴奏がスタッカートで♪♬♬♬を奏でるのにのって、軽快な旋律が現れる。Cは変ロ長調になり、楽譜に「タタシテオのざわめき(先住民のサパテオ)Rumor de "ttacjteo" (zapateo indígena)」と記されている。(タタシテオとはペルーの伝統民謡ワイノで楽器のみで演奏される部分のこと。)ここで更にテンポを速めて高音部でBが変奏されるや、カデンツァのような16分音符両手交互連打が技巧的に奏され、踊りは興奮の坩堝となる。やがて踊り疲れた様に音楽は徐々に静まり、イ短調のAが再現され、コーダではBの旋律が呟くように静かに回想されて終わる。
- Paisaje Nº 1, Noche de luna en el Cuzco (1914?) 風景第1番、クスコの月の夜
- Suite Chopiniana ショピニアーナ(ショパン風)組曲
ゴンサレス・ガマラはマズルカ、ワルツ、夜想曲をそれぞれ2曲ずつ作曲したが、これらは《ショピニアーナ(ショパン風)組曲》として纏められた。- Mazurka Nº 1 マズルカ第1番
嬰ハ短調、A-A-B-C-A'形式。Aは8分音符の旋律が優雅ながらも哀愁を帯びている。Bはイ長調、Cはニ長調になり力強い響きだ。A'はなぜかロ短調になりそのまま終わる。 - Mazurka Nº 2 マズルカ第2番
イ短調、A-A-B-A'-A"形式。旋律の付点リズムはマズルカらしい雰囲気だ。 - Valse Nº 1 ワルツ第1番
ホ短調、前奏-A-A-B-C-A形式。Aは3連符が続く可憐な旋律が奏される。Bは陰うつな雰囲気。Cはホ長調になり、両手和音と8分音符の旋律が交互に奏される。 - Valse Nº 2 (Valse brillante) (1913) ワルツ第2番(華やかなワルツ)
楽譜によっては曲名が《Valse brillante》となっている。嬰ハ短調、前奏-A-A'-B-B'-C-C-A-コーダの形式。8分音符が上に下へと舞う旋律の優雅な曲。Cはホ長調になり、息の長い旋律が奏される。 - Nocturno Nº 1, Adiós a Lima (1914) 夜想曲第1番、さよならリマ
旋律の装飾音がとてもショパン風の作品。イ長調、A-B-B'-A'-コーダの形式。AはLentoのテンポで、夜に静かに歌ような旋律が装飾音混じりで奏され、時折ハープを思わせる和音がポロンと鳴る。Bは嬰ハ短調になり、Andante tranquiloのテンポで繊細な旋律が音階の装飾音やトリルを織り込みながら奏される。再現部のA'では旋律に装飾音がたっぷりと纏わりつく。 - Nocturno Nº 2 夜想曲第2番
変ロ長調、A-B-A'-コーダの形式。夜想曲第1番にも増してアルペジオや装飾音がてんこ盛りのショパン風の曲。Aは息の長い旋律の合間に下行アルペジオが鳴り響く。Bは変ト長調で始まり、両手オクターブの激情するような曲調だ。Bの終わりは長大な装飾音が奏され、A'では右手旋律はオクターブ和音、左手は4オクターブに及ぶアルペジオが華やかに奏され、コーダでAの冒頭が静かに回想されて終わる。
- Mazurka Nº 1 マズルカ第1番
- Vicuña, Vals lento ビクーニャ、ゆっくりとしたワルツ
Francisco González Gamarraのピアノ曲楽譜
出版社(者)不明
- Kosko, 5 ensayos musicales, homenaje a los paises de América con motivo de la celebración del IV centenario de la fundación de Lima
- Homenaje a Garcilazo Inca de la Vega 1539-1616
- Nocturno Nº 1, Adiós a Lima
- Paisajes musicales, Serie de aires incaicos: Paisaje Nº 1, Noche de luna en el Cuzco
Comité de Servicios Integrados Turístico Culturales Cusco (COSITUC), Imprenta Amauta S.R.L.
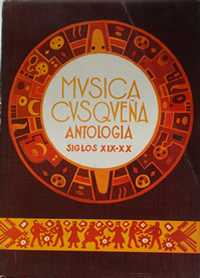 |
|
Ricordi Americana S.A.E.C.
- Album para piano de autores peruanos
- Noche de luna en el Cuzco
斜字は絶版と思われる楽譜
Francisco González Gamarraのピアノ曲LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
Discoteca Peruana - Serie: Autores Cuzqueños (LP)![]()
Casa de la cultura del Peru, D.P.A.6
- Suite para piano (Francisco González Gamarra)
- Mazurca No. 1
- Mazurca No. 2
- Vals No. 1
- Vals No. 2
- Nocturno No. 1
- Nocturno No. 2
- Wanakauri (Víctor Guzmán)
- Auras andinas (José Domingo Rado)
- Idilio andino (José Domingo Rado)
- Estampas peruanas (Armando Guevara Ochoa)*
Lupita Parrondo (pf), Armando Guevara Ochoa (vl)*
Música Cusqueña Antología siglos XIX-XX (3枚組LP)![]()
Comité de Servicios Integrados Turístico Culturales Cusco (COSITUC)
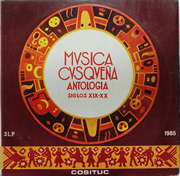 |
|
1985年のリリース。
Francisco González Gamarraに関する参考文献
- Luz González Umeres. Francisco Gonzáles Gamarra: Una teoría del arte peruano.