Júlio Bragaのページ
Júlio Bragaについて
ジュリオ・ファリア・ダ・シウヴァ・ブラーガ Júlio Faria da Silva Braga は1918年4月24日、ペルナンブコ州オリンダに生まれた。子どもの頃よりピアノを習い、10歳でペルナンブコ州州都レシフェでピアノ演奏会を催している。その後レシフェにあるペルナンブコ州音楽院に入学して学び、またブラジル国内各地で演奏会を開いた。
1948年にリオデジャネイロで開かれた「オランダ・フィリップス社杯コンクール」のピアノ部門でジュリオ・ブラーガは優勝。これによりペルナンブコ州より奨学金を得て彼は同年フランスのパリに留学した。同年11月にはパリのサル・ガヴォーで演奏会を催している。その後もヨーロッパ各国や中南米、米国で演奏会を開いていて、1958年9月にはニューヨークのスタインウェイホールでピアノソロ・リサイタルを行い、1959年7月にはニューヨークのカーネギーホールでピアノソロ・リサイタルを行った。また一時ベネズエラに滞在し、カラカスやマラカイボの音楽学校で教鞭を執った。
1948年以降のジュリオ・ブラーガは海外生活が主であったが、1964年にブラジルに帰国し、ピアニストおよび作曲家として活動を続けた。
1993年10月10日、レシフェにて亡くなった。
ジュリオ・ブラーガは管弦楽曲、ヴァイオリン曲、歌曲などを作曲したらしいが音源が乏しいため詳細不明です。ピアノ曲は私が調べた範囲で楽譜または音源が入手できた作品を下に記しましたが、おそらく他にも未出版のピアノ曲があるものと思われます。名ピアニストだった彼らしく、ピアニスティックで技巧的な作品が多く、ドビュッシーやラフマニノフの影響を受けたピアノ曲が目立ちますが、その一方で彼の出身地ブラジル北東部(ノルデスチ)の民族音楽の旋法などを用いた高度なピアノ曲もあり、作曲家としても個性たっぷりで、正に小さな宝石のような「知られざる作曲家」に思えます。
Júlio Bragaのピアノ曲リストとその解説
1937 (1959年改訂)
- Acalanto, Berceuse - Arrullo, Op. 1, N.º 1 子守歌、作品1-1
ニ長調、A-A'-A"形式。穏やかなオスティナートの左手伴奏にのって、三度または四度重音の旋律が歌うように奏される。旋律の大部分はペンタトニックで、素朴な雰囲気。
1939
- Estudo "Movimento perpétuo", Op. 1, N.º 2 練習曲「無窮動」、作品1-2
ニ長調、A-B-C-A'-コーダの形式。アルペジオの左手伴奏にのって、アラベスク模様を思わせるような無窮動の16分音符が右手で流れるように奏される。長九の和音の多用も含め、ドビュッシーの有名な《2つのアラベスク》の第1番ホ長調の影響を感じる。Bはト長調になり、2オクターブ半の16分音符アルペジオが右手に現れる。CはAの主題をト長調に移調して変奏している。
1937 (1979年改訂)
- Batuque em forma de toccata, em memoria de Heitor Villa-Lobos, Op. 1, N.º 4 トッカータの形式によるバトゥーキ、エイトール・ヴィラ=ロボスの思い出に、作品1-4
1938 (1972年改訂)
- Canção de amor, Op.1, N.º 5 愛の歌、作品1-5
ホ長調、A-B-A'形式。中音部に甘く穏やかな旋律が奏され、その上では後打ちの和音、その下の低音部ではオクターブ〜十度の和音が鳴って豊かな響きだ。A'では旋律の上で16分音符の分散和音が優しく奏される。
作曲年代不明
- Espanhola, Op.1, N.º 7 スペインの女、作品1-7
変ホ短調、三部形式。リズミカルな伴奏にのって哀愁漂う旋律が奏される。時々ミの旋法になる所がスペインらしい。中間部は変ホ長調になり、アルペジオの伴奏にのって甘い旋律が奏され、転調を繰り返すのがロマンチック。 - Valsinha saudosa para a mão esquerda, Op.1, N.º 8 左手のための懐かしい小さなワルツ、作品1-8
へ長調、A-B-A-コーダの形式。中音部の旋律は和音またはオクターブで奏され、その下で8分音符の伴奏が滑らかに奏される。いずれも豊かで艶かしい響きの和音だが、左手のみで演奏するのはかなり難しそう。
1951 (1959年改訂)
- Chôro N.º 1 "Noatsalgia", Op. 2, N.º 1 ショーロ第1番「ノスタルジア」、作品2-1
変ホ長調。ギターのつま弾きを思わせるシンコペーション混じりの分散和音のモチーフと、3-3-2のリズムのモチーフの両者が交互に奏されながら変奏される。最後は余韻たっぷりだ。
1952
- Improvisação, Op. 2, N.º 2 即興曲、作品2-2
ハ短調。熱情的な曲で、途中から旋律はオクターブ和音、伴奏は音域の広い8分音符アルペジオ、とラフマニノフのピアノ曲を思わせる。
1953
- Chôro N.º 2 "O carrilhão da saudade", Op. 2, N.º 3 ショーロ第2番「望郷のカリヨン」、作品2-3
変イ長調、A-B-A'形式。冒頭は楽譜に「とても柔らかく、鐘を模して dolcissimo, imitando le campane」と記された、四度重音の旋律が優しく鳴る。旋律のリズムが3-3-2なのがブラジルらしくていい(下記の楽譜)。
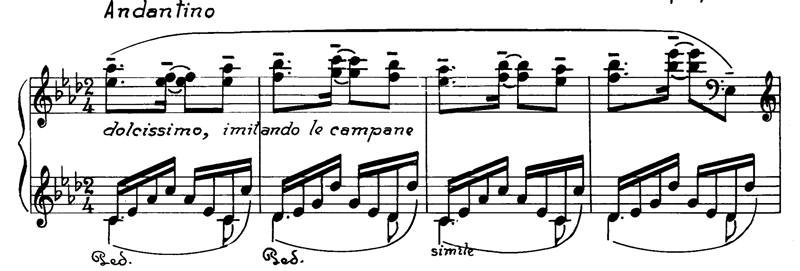
Chôro N.º 2 "O carrilhão da saudade", Op. 2, N.º 3、1-4小節、Edição do Júlio Bragaより引用
Bは野生的なリズム(おそらくバトゥーキのリズム)の新たなモチーフが現れる。このモチーフはラ♭のリディア旋法とミクソリディア旋法の混合でブラジル北東部(ノルデスチ)の民謡風の響きだ(下記の楽譜)。最初はpで、徐々に盛り上がって両手オクターブ和音fffで複数の鐘が鳴り響くように奏される。
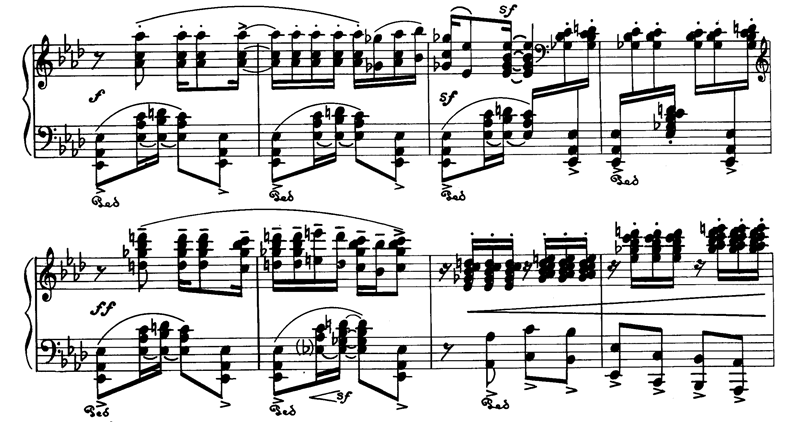
Chôro N.º 2 "O carrilhão da saudade", Op. 2, N.º 3、25-32小節、Edição do Júlio Bragaより引用
1956
- Allegro appassionato, Op. 2, N.º 4 アレグロ・アパショナート、作品2-4
1959
- Toccatina, Op. 3, N.º 2 トッカッティーナ、作品3-2
両手交互連打(概ね右手は和音・左手は単音)の速いテンポの曲で、短調〜長調が頻繁に入れ替わる。
作曲年代不明
- 2.ª Improvisação "Reflexos de uma visão", Op. 3, N.º 3 即興曲第2番「ある幻影の反射」、作品3-3
- Chorinho, Op. 4, N.º 1 小さなショーロ、作品4-1
へ短調、A-B-A'-C-A"形式。Aは二声のポリフォニーで作られていて、冒頭左手の主旋律を右手対旋律がカノンのように追い、その後は主旋律・対旋律が逆転したりと対位法的であり、またブラジルのショーロで見られる主旋律と対旋律(コントラポント )の掛け合いのようにも聴こえる。Bは変イ長調に鳴る。A'後半以降は両手共にオクターブになり派手な響きだ。 - Prelúdio "Brejeiro", Op. 4, N.º 1 前奏曲「ならず者」、作品4-1
へ短調。両手和音の力強い旋律と低音オクターブのバスの劇的な響きは、ラフマニノフのピアノ曲集《幻想的小品集、作品3》の第2曲〈前奏曲〉に似ている。 - Polichinelo, Op. 4, N.º 2 道化師、作品4-2
変ホ短調。全曲3-3-2拍の左手のリズムと右手の和音連打が続き、うねるようにクレッシェンド・デクレッシェンドしながら奏される。カマルゴ・グァルニエリが1959年に作ったピアノ曲集《ポンテイオス第5巻》の第49曲の影響を感じる。
1978
- 1.ª toccata nordestina, Op. 4, N.º 8 ノルデスチのトッカータ第1番、作品4-8
4分程の曲だが、ジュリオ・ブラーガの最高傑作である(と思う)!。全曲、リディア旋法とミクソリディア旋法を混合したノルデスチ民謡固有の旋法(ファの旋法の場合、ファ-ソ-ラ-シ-ド-レ-ミ♭)が二声のポリフォニーで息もつかず奏され、さながら2人の歌手がパンデイロ(ブラジルのタンバリン)を打ちながら即興を競う歌合戦(ノルデスチではデサフィーオ desafio とかエンボラーダ embolada とか呼ばれる)のようだ。まず、上述の旋法を上下するような16分音符の旋律が右手に、そして左手に1小節遅れた追唱がカノンとなって奏される。9小節目からのスタッカート16分音符の旋律は冒頭の旋律が短縮された形で、いわば縮小フーガのような形で、更に右手の旋律にわずか1/2小節の遅れで追唱が始まる様はフーガのストレッタを思わせる。続いてラの旋法に転調すると新たに野生的な連打のリズムが和音で加わり、ソの旋法→ドの旋法→ミの旋法→シ♭の旋法→レの旋法→と転調しつつ、上述の16分音符の旋律や連打のリズムが華やかに展開される。ノルデスチ民族音楽の旋法や形式、フーガを思わせる対位法上の様々な工夫、頻回の転調による色彩的な響きと、聴き応えタップリの見事な作品である。
1979
- Noturno N.º 1, Op. 6, N.º 3 夜想曲第1番、作品6-3
- 11.ª Improvisação "Ilusão", Op. 6, N.º 4 即興曲第11番「幻想」、作品6-4
ホ短調、A-B-B'-A'-コーダの形式。左手8分音符・右手3連8分音符でそれぞれ無窮動な分散和音が奏され、右手音形の中から悩ましい旋律が浮かび上がる。BとB'は一時ト長調になる。 - Noturno N.º 2 "Lamento em estilo brejeiro", Op. 6, N.º 5 夜想曲第2番「放浪するようなスタイルの哀歌」、作品6-5
- Noturno N.º 3, Op. 8, N.º 2 夜想曲第3番、作品8-2
1980
- Noturno N.º 4, Op. 8, N.º 4 夜想曲第4番、作品8-4
作曲年代不明
- Prelúdio da casinha solitária, Op. 8, N.º 6 人里離れた小さな家の前奏曲、作品8-6
- Frevo das muricocas, Op. 8, N.º 10 蚊の群れのフレーヴォ、作品8-10
- 24.ª Improvisação, Op. 10, N.º 4 即興曲第24番、作品10-4
1991
- 2ª Valsa capricho, Movimento perpétuo N.º 2, Op. 13, N.º 2 奇想的なワルツ第2番、無窮動第2番、作品13-2
作曲年代不明
- Dança Afro-Brasileira アフロ・ブラジルの踊り
- Dança dos pinguins (para crianças) ペンギンの踊り(子どものために)
ト短調。小さな歩幅でヨタヨタ歩くペンギンの姿を、短い音階とブンチャッブンチャッの繰り返しで愛嬌たっぷりと描写している。 - Os sinos de natal (para crianças) クリスマスの鐘(子どものために)
Júlio Bragaのピアノ曲楽譜
Escola de Música da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
- 4 Noturnos para piano
- Noturno N.º 1, Op. 6, N.º 3
- Noturno N.º 2 "Lamento em estilo brejeiro", Op. 6, N.º 5
- Noturno N.º 3, Op. 8, N.º 2
- Noturno N.º 4, Op. 8, N.º 4
Edição do Júlio Braga
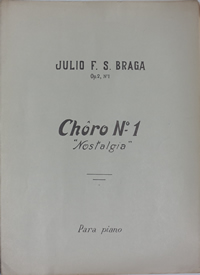 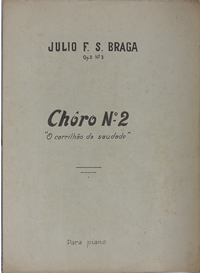 |
|
斜字は絶版と思われる楽譜
Júlio Bragaのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Relevos: A obra para piano solo de Júlio Braga![]()
![]()
A Casa Discos, ACD-CLA 039
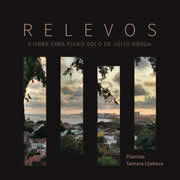 |
|
Tamara Ujakova (pf)
O Piano de Norte a Sul (LP)![]()
Sociedade Cultural e Artistica Uirapuru, LPU-1012
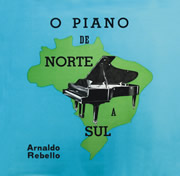 |
|
Arnaldo Rebello (pf)
Júlio Bragaに関する参考文献
- Tamara Ujakova Corrêa Schubert. Elementos estruturais e gestuais da Primeira Toccata Nordestina para piano solo de Júlio Braga. Anais do IV SIMPOM (simpósio brasileiro de pós-graduanos em música). PPGM (Programa de Pós Graduação em Música) da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) 2016.