Luiz Levyのページ
Luiz Levyについて
ルイス・エンリキ・レヴィ Luiz Henrique Levy は1861年8月8日、サンパウロで生まれた。彼の父アンリ・ルイ・レヴィ Henry-Louis Levy はフランス生まれで、1848年頃にブラジルに移民するとポルトガル語のエンリキ・ルイス・レヴィ Henrique Luiz Levy に名を改めた。エンリキ・ルイス・レヴィはクラリネット奏者で、サンパウロに来てからは1860年にCasa Levyという楽器・楽譜店を開いていた。またアレシャンドリの母はフランス系スイス人で、同じくブラジルに移民として来ていた。ルイス・レヴィが生まれた3年後の1864年には、弟のアレシャンドリ・レヴィ Alexandre Levy が生まれていて、弟も作曲家兼ピアニストである。父の店には多くの音楽家が訪れていて、ルイス・レヴィは子どもの頃より音楽的な環境の中で育ち、フランス人ピアニストでサンパウロに住んでいたガブリエル・ジロードンにピアノを習った。1878年には母に連れられてパリ万国博覧会を見にフランスを訪れ、パリではピアノ演奏を披露したらしい。1882年には弟アレシャンドリ・レヴィと共に叔父が住むアルゼンチンのブエノスアイレスを訪れ、当地で弟とピアノの演奏会を催している。
ルイス・レヴィが成人してどんな音楽活動をしていたのかは資料が僅かです。ピアニストとしてはメンデルスゾーンの作品演奏に力を入れたらしく、メンデルスゾーンの《ピアノトリオ第1番》や、《ピアノ協奏曲第1番》を演奏会で弾いた記録がある。1891年より彼はCasa Levyの経営を父より引き継ぎ、晩年まで続けた。1935年、サンパウロで死去。
ルイス・レヴィの作品には、僅かに弦楽曲がある他は歌曲とピアノ曲ばかりである。彼は本名以外にL. Henri、Ziul Y Vel、Yvu Lelizというペンネームを作曲したジャンルによって使い分けた。比較的シリアスな作品番号付きの作品は本名で発表し、甘い曲や軽い曲などにはL. Henriというペンネームを、ポルカやショッティッシュ、パ・ド・カトルといった舞曲にはZiul Y Velというペンネームを、またセルタネージャなど歌曲《A frorada》などにはYvu Lelizというペンネームを用いた。本名で第1番から第4番までのピアノ曲《ゆったりとしたワルツ (Valsa lentaまたはValse lente)》を作曲し、またL. Henri名義で別の作品である第1番から第6番までのピアノ曲《ゆったりとしたワルツ Valse lente》を作曲している。
ルイス・レヴィはペンネームの作品も含めてピアノ曲を結構たくさん作曲しており、その多くはワルツ、ポルカ、ガボット、マズルカといったサロン風の、当時のブラジルの上流階級で人気を博したと思われる作品である。それらの多くの曲はブラジル風味もないのだが、その中にも《ゆったりとしたワルツ第4番 4.ª Valsa lenta、作品32》のような、ヴァルサ・ブラジレイラの走りとも思えるピアノ曲があるのは興味深い。また2曲の《ブラジル狂詩曲 Rapsódia brasileira》は、(結局の所かなりリスト風にはなってしまっているが)ブラジル民族主義としての大作を作ろうとした意気込みを感じさせる作品です。
Luiz Levyのピアノ曲リストとその解説
- Graciosa, Capricho-Gavota, Op. 6 優雅に、奇想曲ーガボット、作品6
- 2da Gavota, Op. 7 ガボット第2番、作品7
イ長調、前奏-A-B-A'-C-A形式。スタッカートの響きが、時計がカチコチ打つのを描写するような溌溂とした曲。Bは嬰ヘ短調、Cはニ長調になる。 - Minuete-Improviso, Op. 8 (1890?) メヌエットー即興曲、作品8
ト長調、A-A-B-A-C-A'形式。軽やかなメヌエット。Cは強いて言えばト短調になる。 - 3.ª Gavota, Op. 9 ガボット第3番、作品9
- Barcarola, Op. 10 舟歌、作品10
サンパウロ州を流れるチエテ川の舟に乗った印象を受けて作曲したとされる。ヘ長調、A-A'-B-A'-コーダの形式。舟歌の8/12拍子のリズムにのって、水のせせらぎが聞こえてくるようなアルペジオ和音混じりの旋律が奏され、静かで情緒溢れる曲。Bは問いかけのようなモチーフが転調を繰り返す。 - 3.ª Mazurka, Op. 12 マズルカ第3番、作品12
- 4.ª Mazurka, Op. 13 マズルカ第4番、作品13
- Valse-caprice, Op. 14 ワルツ-カプリース、作品14
- Serenata, Op. 16 セレナーデ、作品16
ト長調、前奏-A-B-A'-C-D-A"-コーダの形式。のどかなガボット風の曲。Bはニ長調、Dはハ長調に成る。後に弦楽曲にも編曲された。 - 1.ª Rapsódia brasileira, Op. 17 (1894) ブラジル狂詩曲第1番、作品17
リストの有名な作品集《ハンガリー狂詩曲》に倣って、ルイス・レヴィも自国の主題を用いた本格的な「狂詩曲」を作ろうと考えたのであろう。ブラジル民謡をいくつか用いて、演奏時間約8分という大曲を作った彼の意気込みを感じます。しかし、まだまだ民謡の扱い方が表面的で、和声は19世紀ヨーロッパロマン派からは抜け出せず、何と言ってもリストのハンガリー狂詩曲にリズムや旋法があちこちで似ていて、ハンガリー音階(ロマ音階またはジプシー音階とも呼ばれる)まで現れ、二番煎じの謗りは免れない作品であるように思える。ピアノ譜は2種類存在していて、一つ目は1895年頃に出版されたルイス・レヴィ自身によるオリジナルの楽譜で、もう一つは1906年に出版されたアルトゥール・ナポレオンが曲の一部を編曲した楽譜である(アルトゥール・ナポレオンはポルトガル出身の作曲家・ピアニストで、ブラジルに移民してからは楽譜出版業でも活躍した)。後者の楽譜には「作品17ー増補版(アルトゥール・ナポレオンの彼の演奏会での演奏と同じ版) Op. 17 - bis (Edição conforme executava Arthur Napoleão em seus concertos)」と記され、また楽譜の脚注にはこの曲で用いられた4つのブラジル民謡名が記されており(以下の文の〈〉内が民謡名)、このアルトゥール・ナポレオン増補版の方が当時より現在に至るまで広く流布している。曲は3オクターブの重々しいニ短調の旋律で始まり、これは民謡〈ワラの籠、私の愛しい人 Balaio, meu bem, Balaio〉による。続いて高音部にレシタティーボ風に奏されるト短調の旋律は民謡〈シッ、シッ、シッ、アラウナ Chô, Chô, Chô, Araúna〉(アラウナとはルリコンゴウインコのこと)で、装飾音混じりのハンガリー音階で奏される。その次の変ロ長調の穏やかな旋律は民謡〈ビトゥ、こっちに来なさい Vem Cá, Bitú〉で、一通りブラジル民謡が奏される(増補版ではハープのようなアルペジオを伴って繰り返される)。一段落した後に、「サンバの形式で In forma di samba」と楽譜に記されたニ長調の軽やかなリズムが奏され、3連符混じりの優雅な旋律が見え隠れする(増補版では華やかに変奏されつつ繰り返される)。次に、《ハンガリー狂詩曲第2番》のフリスカを思わせる経過句を経て、変ト長調3/8拍子の踊りのリズムにのって旋律〈牛飼いの歌 Canção de Boiadeiro〉が現れる。所々「In forma di samba」で現れた旋律も顔を出す。最後は、ヘ長調の活発な旋律がVivoで奏され、ニ長調に転調して終わる(増補版ではへ長調のまま熱狂的に盛り上がり曲を閉じる)。この曲は後に、João PoratanoとFrancisco Mignoneによりそれぞれ管弦楽曲にも編曲された。 - Hino ao quinze de novembro, Op. 18 11月15日賛歌、作品18
- Á memoria de Carlos Gomes, Marcha fúnebre, Op. 19 (1896) カルロス・ゴメスの想い出に、葬送行進曲、作品19
- Romance, Op. 20 (1900?) ロマンス、作品20
ヘ長調、A-A-B-C-コーダの形式。Aは旋律の上下に鏤められたアルペジオの伴奏が可憐な雰囲気。Bはハ長調になる。Cは右手オクターブの旋律と左手重音3連符の伴奏が劇的に奏され、へ短調から転調してへ長調に戻る。この曲はチェロとピアノ用にも編曲された。 - Madrigal, Romance sem palavras, Op. 21 マドリガル、無言歌、作品21
- Valsa lenta, Op. 22 (1904) ゆったりとしたワルツ、作品22
当時のブラジルの音楽雑誌「ルネサンス Renascença」が1904年に催した「第1回ルネサンス・音楽コンクール 1º Concurso de musica da Renascença」で佳作(三等賞)を受賞した作品(ちなみに一等賞はネポムセノ作曲の《即興曲 Improviso、作品27-2》であった)。エンリキ・オスワルドに献呈。ホ長調、A-B-A'-C-A形式。楽譜のメトロノーム指示では1小節=63から80で、あまり「ゆったり」とはしていないテンポの曲。流れるように踊る感じの曲。Bは嬰ハ短調〜嬰へ短調になる。Cはイ長調でのびやかな旋律。 - Poudrée, 4eme Gavotte, Op. 23 (1905) 白粉、ガボット第4番、作品23
ニ長調、A-B-A'-C-C-A形式。旋律はスタッカートとスラーが混じって愛嬌たっぷり、上品な雰囲気のガボット。Bはロ短調、Cはト長調になる。 - 5.ª Gavota, Op. 24 (1906) ガボット第5番、作品24
ルイス・レヴィの父が亡くなったのを偲んで作曲された曲。変ホ長調、A-B-A'-C-A-コーダの形式。旋律や対旋律に半音階的経過音が多く、優雅でいい雰囲気。Bは変ロ長調、Cは変イ長調になる。 - Humorística, 2.ª valsa lenta, Op. 25 ユーモラスに、ゆったりとしたワルツ第2番、作品25
嬰ヘ長調、A-B-A'-C-A"-コーダの形式。流れるような雰囲気の曲。Bは変ニ長調になる。Cはニ長調から頻繁に転調する。 - Diálogo, Melodia sem palavras, Op. 26 対話、無言歌、作品26
変ト長調、A-B-A'-B-A'-コーダの形式。右手の下行する4分音符旋律と、左手の上行する4分音符伴奏が優しい対話のような、とっても抒情的な曲。ややシューマンっぽいかな。Bは変ニ長調になり、主旋律に遅れて現れる中音部対旋律は一部カノンのようになっている。A'では左手伴奏は3連4分音符になり、右手4分音符旋律とのヘミオラが流れるような美しさだ。 - 3me Valse lente, Op. 27 ゆったりとしたワルツ第3番、作品27
ニ長調、A-A'-B-A"-C-C'-A'''形式。Aは落ち着いた雰囲気ながらオクターブの旋律がやや重いワルツが奏される。Bは嬰ヘ短調になり、16分音符アルペジオの伴奏にのって流れるような旋律が奏される。C-C'はト長調になる。 - Tango burlesco, Op. 28 (1913) おどけたタンゴ、作品28
ニ長調、A-B-A'-C-A-コーダの形式。シンコペーションのリズムが快活で、南国的な陽気な曲。Bはロ短調で、トレシージョのリズム(♪.♪.♪)の伴奏にのって歌うような旋律が現れる。Cは変ト長調で、のびやかなオクターブの旋律が明るい。この曲は後に、ソウザ・リマにより管弦楽曲に編曲された。 - 2.ª Rapsódia brasileira (Listziana), Op. 29 (1910) ブラジル狂詩曲第2番(リスト風)、作品29
1894年作曲の《ブラジル狂詩曲第1番、作品17》にも増してリストのハンガリー狂詩曲の影響が色濃い作品で、ルイス・レヴィ自身もさすがに副題に「リスト風」と記さない訳にはいかなかったのかな。冒頭は変ロ短調で、3オクターブの旋律が重々しく現れる。続いて変ロ長調の静かな主題、ニ短調の舞曲風の主題と奏され、これらの主題が展開されていく。後半は舞曲風の主題が変ロ長調で最初は単音で歌い出し、これを繰り返しながら響きを分厚くし、音量も増していくーこれはリストの《ハンガリー狂詩曲第6番》のフリスカの部分にあまりにも似ている。コーダの部分はシンコペーションのリズムで、少しブラジル風味を感じる。 - Valsa brilhante, Op. 30 華やかなワルツ、作品30
変ホ長調、前奏-A-A'-B-A'-C-C'-D-C"-A"-コーダの形式。華やかな前奏に続き、速いテンポの流れるような旋律が奏される。Bは変ロ長調に、Cは変イ長調で優雅だ。この作品、構成・調・曲想ともフランスの作曲家オーギュスト・デュラン Auguste Durand (1830-1909) の《ワルツ第1番、作品83》にそっくりだ~。 - Habanera, Op. 31 (1922) ハバネラ、作品31
ニ長調。この曲は2つのバージョンが出版されていて、A-A'-A"形式で比較的演奏が簡単な「サロン版 Edição de salão」と、A-A'-A"-A"'形式で技巧的な装飾音の多い「演奏会版 Edição de concerto」がある。いずれもハバネラのリズムにのってゆったりとした旋律が奏される。ニ長調で、途中で一部ロ短調や嬰ヘ長調に転調する所など、曲想がアルベニスの《タンゴ》にかなり似ている(下記の楽譜)。ただしアルベニスより音は豪奢で(特に「演奏会版」では)艶かしい響きの曲。またこの曲は後にAugusto de Carvalhoの詞による歌曲にも編曲された。

Habanera、1-15小節、Casa Levy.より引用 - 4.ª Valsa lenta, Op. 32 (1904?) ゆったりとしたワルツ第4番、作品32
哀愁溢れる旋律の美しさから、ルイス・レヴィの作品の中でも演奏されることの多い曲。後に、ミニョーネなどのブラジル作曲家によって完成されるヴァルサ・ブラジレイラの世界を先取りしているようにも思える作品だ。嬰ヘ短調、A-B-A'-C-C-A"-D-A形式。Aは泣けてくるような旋律で、Bも悲しく訴えかけるようなモチーフが繰り返される。Aの旋律の半分だけ奏された後に現れるCはイ長調で、右手主旋律と左手対旋律が掛け合いのように奏される。A"は旋律が微妙に変わっている。Dは嬰ヘ長調で、何かへの憧れを穏やかに歌うような旋律。

4a Valsa lenta、1-14小節、Irmãos Vitale.より引用 - Tango grotesco, Op. 33 グロテスクなタンゴ、作品33
イ長調、A-B-A'-C-A"形式。Aのリズムは浮き浮きするようで、旋律の盛り上がりも楽しい。Bは嬰ヘ短調。Cはニ長調でハバネラのリズムになる。 - Nice, Pequena gavota, Op. 34 (1930?) ニース、小さなガボット、作品34
- Boas festas, Schottisch クリスマスおめでとう(ペンネーム:Ziul Y Vel)
- Brazilian cake walk ブラジルのケークウォーク(ペンネーム:L. Henri)
ハ長調、A-A'-B-A-C-C-D-A-A'-B-A形式。ケークウォークのリズムにのった陽気で愉快な曲。Bはト長調、CとDはヘ長調になる。 - Brigada, Dobrado 軍隊、ドブラード(ペンネーム:L. Henri)
- Cabôclo cake walk カボクロのケークウォーク(ペンネーム:Ziul Y Vel)
- Captivaram-me os teus olhos, Polka brazileira (1893) 君の瞳は私を捕らえる、ポルカ(ペンネーム:Ziul Y Vel)
ニ長調、A-B-A'-C-C-A形式。楽譜には「E. ナザレのポルカ Os teus olhos captivam へのお返しに」と記されている。ナザレのピアノ曲《君の瞳は私を捕らえる Os teus olhos captivam》を変奏したような感じの軽快な曲で、Aの三度重音の跳ねるような旋律、Bはイ長調になり軽快な16分音符のモチーフ、Cはト長調になり左手オクターブの下降音階に右手の16分音符音型などがそっくり。 - Gostosa, Schottisch 愉快に、ショッティッシュ(ペンネーム:Ziul Y Vel)
- Gueixa 芸者
イギリスの作曲家、シドニー・ジョーンズ Sidney Jones (1861-1946) が書いたオペレッタ「芸者」のいくつかの場面をルイス・レヴィがピアノ曲に編曲したとのことですが、まだ未聴です。 - Ideal..., Valsa 空想・・・、ワルツ(ペンネーム:Ziul Y Vel)
- La valse de Roses, Valse boston (1911) バラのワルツ、ワルツ・ボストン
アルゼンチン・ブエノスアイレスの楽譜出版社Litografía Musical Francalanciが1911年に催した「フランカランシ南米コンクール Concurso Sud Americano Francalanci」で1等賞を受賞した作品。タンゴの楽譜を主に出版していた同出版社への応募を意識したような、メロディックで親しみやすい曲である。変ホ長調、前奏-A-B-A-C-B'-C'-A'形式。前奏に引き続き、艶やかな旋律が中音部オクターブで奏され、右手オクターブ和音fでリフレインされる。Bは変ロ長調、Cは変イ長調、B'は変ホ長調になる。 - Marcha dos alliados (1918) 同盟行進曲(ペンネーム:L. Henri)
- Mimosa, 6e Valse lente ミモザ、ゆったりとしたワルツ第6番(ペンネーム:L. Henri)
ホ長調、前奏-A-A'-B-A'-C-C'-C-C'-D-C'-A-A'-コーダの形式。全曲通して甘い旋律がゆったりと流れ続ける。AとBは可憐で、Cは中音部のオクターブ旋律が上品で落ち着いた雰囲気。Bはロ長調、CとC'は変イ長調になる。 - Mystère, 3me Valse lente(ペンネーム:L. Henri)
- Natalia, Schottisch(ペンネーム:Ziul Y Vel)
- Para a frente!, Marcha militar 前進!、軍隊行進曲(ペンネーム:L. Henri)
- Parfum parisien, 1ère Valse lente パリの香り、ゆったりとしたワルツ第1番(ペンネーム:L. Henri)
- Pas de quatre パ・ド・カトル(ペンネーム:Ziul Y Vel)
ハ長調、前奏-A-B-A-C-A-B-A形式。パ・ド・カトルはバレエ用語で「4人の踊り」のこと。3連符の軽やかな旋律が、バレリーナが4人横一列に手をつないで踊る様子を、愛嬌たっぷり描写しているよう。Bはト長調、Cはヘ長調になる。 - Pleureuse, 5e Valse lente 泣いて、ゆったりとしたワルツ第5番(ペンネーム:L. Henri)
ホ短調、A-B-A'-C-A-コーダの形式。中声部オクターブの旋律が重々しく奏され、何とも切ない調べの曲。Bはイ短調。A'の後半はイ長調に転調し、Cはイ長調で郷愁を誘うような旋律が静かに奏される。 - Pourquoi partir?, 2ème Valse lente 何故行くの?、ゆったりとしたワルツ第2番(ペンネーム:L. Henri)
変イ長調、A-B-A'-C-B-A-コーダの形式。題名通りフランス風雰囲気の、少し哀愁漂う艶かしい旋律がゆったりと奏される。Bは変ホ長調、Cは変ニ長調になる。 - Rêveuse, 4e Valse lente(ペンネーム:L. Henri)(1917)
- Santos-Dumont, Marcha (1913) サントス・デュモン、行進曲
- Sentimental, Tango brasileiro 感傷的に、タンゴ・ブラジレイロ(ペンネーム:Ziul Y Vel)
ニ短調、A-B-C-B-A形式。旋律は哀愁あるが、全曲通して左手伴奏はトレシージョのリズムで、シンコペーションが何か躍動的な感じ。Aはベース音がレ-レ♯-ミ-ファ-ファ♯-ソ-ソ♯-ラと半音づつ上がっていくのが粋である。Bは変ロ長調、Cは変ホ長調になり、3連符混じりの旋律が艶やか。 - Setenta y cinco, Tango criollo 75、タンゴ・クリオージョ(ペンネーム:L. Henri)
「75」とはフランスが開発した口径75mmの野砲(カノン砲)を指しており、楽譜の表紙には、第一次世界大戦中にフランスが戦費調達のために鋳造したメダル「Journée du 75」のイラストが描かれている。ニ短調、A-A-B-A-C-C-A-B-A形式。アルゼンチンタンゴ初期の時代の曲を思わせる、硬い雰囲気のタンゴ。BとCはニ長調になる。 - Silver dreams (Sonhos de prata) 銀色の夢(ペンネーム:L. Henri)
- Timbrée, Mazurka de salon 切手、サロン風マズルカ
ルイス・レヴィは大の切手蒐集家だったとのこと。1863年創刊のベルギーの切手収集趣味誌「Le Timbre-Poste」に敬意を表して、創刊者のJeanne Baptiste Philippe Constant Moens (1833-1908) に献呈された曲。楽譜もベルギーで出版された。ヘ長調、A-B-A'-C-A"形式。落ち着いたマズルカ。Bはニ短調、Cは変ロ長調になる。 - Valse des alliés, sur des thémes patriotiques (1915) 連合国のワルツ、愛国的な主題による(ペンネーム:L. Henri)
- Vicilino, Polka brazileira (1893) ヴィシリーノ(ペンネーム:Ziul Y Vel)
ヴィシリーノとはハチドリの一種のこと。ニ長調、A-B-A-C-A形式。楽譜には「E. ナザレのポルカ《ハチドリ》への応答 Resposta Do "Beija Flôr" Polka de E. nazareth」と記されている。確かにAの旋律は《ハチドリ Beija-flor》のトリオの部分に少し似ている。Bはロ短調になり、ナザレが好んで用いた16分音符アルペジオの伴奏型が現れる。Cはト長調になる。 - Voluntários Paulistas, Polka-marcha(ペンネーム:Ziul Y Vel)
Luiz Levyのピアノ曲楽譜
Irmãos Vitale
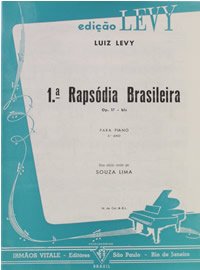 |
|
Casa Levy / L. Levy & Irmão / Levy Filhos
- Graciosa, Capricho-Gavota, Op. 6
- 2da Gavota, Op. 7
- Minuete-Improviso, Op. 8
- Barcarola, Op. 10
- Serenata, Op. 16
- 1.ª Rhapsodia brasileira, Op. 17. bis.
- Romance, Op. 20
- Poudrée, 4eme Gavotte, Op. 23
- Diálogo, Melodia sem palavras, Op. 26
- 3me Valse lente, Op. 27
- Tango burlesco, Op. 28
- 2.ª Rhapsodia brasileira (Listziana), Op. 29
- Valsa brilhante, Op. 30
- Habanera, Op. 31
- 4.ª Valsa lenta, Op. 32
- Boas festas, Schottisch (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Brazilian cake walk (pseudônimo: L. Henri)
- Brigada, Dobrado (pseudônimo: L. Henri)
- Cabôclo cake walk (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Captivaram-me os teus olhos, Polka brazileira (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Gostosa, Schottisch (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Ideal, Valsa (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Marcha dos alliados (pseudônimo: L. Henri)
- Mimosa, 6e Valse lente (pseudônimo: L. Henri)
- Mystère, 3me Valse lente (pseudônimo: L. Henri)
- Natalia, Schottisch (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Para a frente!, Marcha militar (pseudônimo: L. Henri)
- Parfum parisien, 1ère Valse lente (pseudônimo: L. Henri)
- Pas de quatre (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Pleureuse, 5e Valse lente (pseudônimo: L. Henri)
- Pourquoi partir?, 2ème Valse lente (pseudônimo: L. Henri)
- Rêveuse, 4e Valse lente (pseudônimo: L. Henri)
- Sentimental, Tango brasileiro (pseudônimo: Ziul Y Vel)
- Silver dreams (Sonhos de prata) (pseudônimo: L. Henri)
- Valse des alliés, sur des thémes patriotiques (pseudônimo: L. Henri)
- Vicilino, Polca brasileira (pseudônimo: Ziul Y Vel)
I. Bevilacqua & C. / E. Bevilacqua & C.
- Graciosa, Capricho-Gavota, Op. 6
- 2da Gavota, Op. 7
- Poudrée, 4eme Gavotte, Op. 23
- 5.ª Gavota, Op. 24
Litografía Musical Francalanci
- La valse de Roses, Valse boston
J. B. Moens, Editeur, Bruxells
- Timbrée, Mazurka de salon
The University society, Inc., New York
- The world's best music, Volume I, Compositions for the pianoforte concert selections
- Tango burlesco, Op. 28
- A melhor música do mundo, Tomo IV
- Tango burlesco, Op. 28
- A melhor música do mundo, Tomo V
- Valsa lenta, Op. 22a
斜字は絶版と思われる楽譜
Luiz Levyのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
A obra pianística de Luiz Levy (LP)![]()
Chantecler, 2-08-404-072
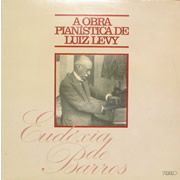 |
|
Eudóxia de Barros (pf)
1976年のリリース。
LUIZ LEVY Intérprete: Cláudio de Brito (LP)![]()
Estúdio Eldorado, 90.84.0443
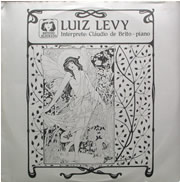 |
|
Cláudio de Brito (pf)
1984年の録音。
Luiz & Alexandre Levy![]()
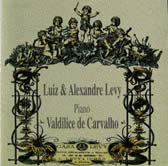 |
|
Valdilice de Carvalho (pf)
1996年の録音。CDまるまるレヴィ兄弟のピアノ曲という貴重なアルバム。
Panorama da Música Romântica Brasileira para Piano![]()
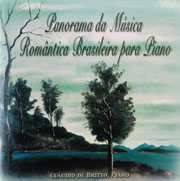 |
|
Cláudio de Britto (pf)
O Piano Brasileiro - Século XIX (2枚組CD)![]()
![]()
Paulus, 001726
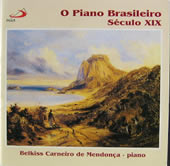 |
CD 1
CD 2
|
Belkiss Carneiro de Mendonça (pf)
1987年の録音。
BRASILIANA: Three Centuries Of Brazilian Music![]()
![]()
![]()
BIS, BIS-CD-1121
- Paulistana no 4 (Claudio SANTORO)
- Paulistana no 1 (Claudio SANTORO)
- Dança Negra (Mozart Camargo GUARNIERI)
- Ponteio no 49 (Mozart Camargo GUARNIERI)
- Il neige (Henrique OSWALD)
- Valse de Esquina no 1 (Francisco MIGNONE)
- Corrupio (Francisco BRAGA)
- Valsa Lenta no 4 (Luiz LEVY)
- Prelúdio Tropical no 2 (César Guerra PEIXE)
- Prelude in f sharp minor Op32 (Eduardo DUTRA)
- Cenas Infantis (Octavio PINTO)
- from 12 Peças Características (Leopoldo MIGUEZ)
- from Solfejo Lessons (Luiz Álvares PINTO)
- Gaúcho - Tango Brasileiro (Francisca (Chiquinha) GONZAGA)
- Air (from Suite Antiga) (Alberto NEPOMUCENO)
- Fantasia para Pianoforte no 4 (José Mauricio Nunes GARCIA)
- O Polichinello (Heitor VILLA-LOBOS)
- Valsa da Dor (Heitor VILLA-LOBOS)
- Valsa no 7 (Radames GNATTALI)
- Valsa no 3 (Jose SIQUEIRA)
- Apanhei-te, Cavaquinho (Ernesto NAZARETH)
- Coeur blessé (Alexandre LEVY)
- Congada (Danca brasiliera) (Francisco MIGNONE)
- Serenata Espanhola Op1 no2 (Fructuoso VIANNA)
- Odeon - Tango Brasiliero (Ernesto NAZARETH)
- Suite Brasiliera no 2 (Oscar Lorenzo FERNÂNDEZ)
Arnaldo Cohen (pf)
2000年の録音。こういったブラジルの作曲家を多数紹介するオムニバスCDは、沢山のピアニストが出している。が、さすが有名レーベルがリリースしただけあって?このCDの演奏はテクニックも達者で歌心もあり上手。
Valsas Brasileiras![]()
VCCD 02
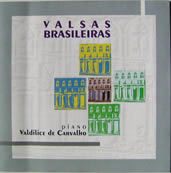 |
|
Valdilice de Carvalho (pf)
2000年のリリース。
SÃO PAULO E SEUS COMPOSITORES![]()
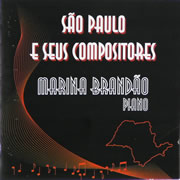 |
|
Marina Brandão (pf)
2006年の録音。
Encontros com a Música de São Paulo![]()
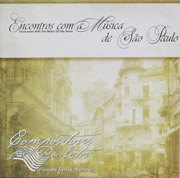 |
|
Sylvia Maltese (pf)