Octavio Maulのページ
Octavio Maulについて
オクタヴィオ・マウル Octavio Maul は1901年11月22日、リオデジャネイロ郊外のペトロポリスに生まれた。彼の父はコントラバスなどの楽器が演奏できる人で、息子達に音楽を教えた。オクタヴィオはピアノとフルートを習い、親子で小さなバンドを組んで演奏していたらしい。オクタヴィオ・マウルは17歳の1919年にリオデジャネイロの国立音楽学校 Instituto Nacional de Música に入学し、フランシスコ・ブラーガに作曲などを師事した。1929年には短期間ながらドイツとベルギーに留学した。留学からの帰国直後の1930年には、郷里のペトロポリスで兄と共に音楽学校の設立をした。1934年には再び国立音楽学校で学び、フランシスコ・ミニョーネに指揮法を師事した。
1936年にピアニストのLaura Geoffroy Pristaと結婚した。
1939年にはリオデジャネイロに移住した。1945年には国立音楽学校の教授に就任。1951年には、リオデジャネイロ市立劇場交響楽団を指揮して、自作の演奏会を行った。1960年にはRadio MECにより "Festival Octavio Maul" が催された。1974年4月5日にリオデジャネイロで死去。現在、ペトロポリスの町にはマエストロ・オクタヴィオ・マウル通り Rua Maestro Octavio Maul があるそうである。
マウルの作品は、管弦楽曲では《祝祭行進曲 Marcha festiva》(1922)、《交響的前奏曲》(1927)、《交響詩 A Selva transfigurada》など。また《ピアノ協奏曲》(1951)、《弦楽四重奏曲》(1944)、《チェロソナタ》(1931-1935)、その他宗教曲、歌曲や下記のピアノ曲などを作曲しましたが、詳しいことは分かりません。
マウルのピアノ曲を聴くといかに作曲技法が高く、それでいて親しみやすい曲も多いことに気がつきます。これだけの素敵なピアノ曲を作ったのに殆ど知られていないなんて、正に当サイトきっての「知られざる作曲家」です。彼のピアノ曲の特徴の一つはフランス印象主義や、時にはスクリャービン風も混じった幻想的な響きで、和音も素晴しく、かつピアニスティックである。そして最高に彼に特徴的なのは、機銃掃射のような目の覚めるような16分音符のパッセージ、特にヴィラ=ロボスの有名な《赤ちゃんの家族第1集第7番 "O Polichinelo"》を更に発展させたような両手交互連打は本当に面白く、(弾くのはかなり難しいが)演奏会で上手に弾けたら喝采間違いなしです。
Octavio Maulのピアノ曲リストとその解説
1929年頃
- Valsa poética N.º 1 詩的なワルツ第1番
変ホ長調、A-B-A形式。ゆったりとしたワルツだが、旋律には前打音や装飾音がしばしば付き、オクターブを越える分厚い和音は前打音やアルペジオ混じりで、纏わりつくモノが重々しい響きだ。Bは転調が多く調性が定まらない。 - Valsa poética N.º 2 詩的なワルツ第2番
ト長調、A-B-B'-A形式。この曲もゆったりとしたワルツのリズムにのって重音の旋律と分厚い和音の伴奏が奏される。Bはハ長調になり、やや活発でコケティッシュなワルツが奏される。ここでは楽譜に次々と「anim. poco a poco」、「meno」、「animato」、「alarg. poco a poco」、「rall...」、「retomando o tempo」といったテンポ指示があって、ユーモアたっぷりのテンポの揺らしがピアニストの腕の見せ所となろう。
1932
- A cantilena dos águas 水のカンチレーナ
二長調、A-B-A'-コーダの形式。「水」を描写したこの作品は、増三和音や六度の和音、全音音階を多用し、ドビュッシーの影響を強く感じさせる曲。中音部で繰り返される♪♬♬は水の揺らめきのようで、その上で四度重音の旋律が途切れ途切れ奏される。マウルがいかにフランス印象主義の作曲技法を身につけていたかが分かる。 - Estudo em Fá maior, Op. 21 練習曲へ長調、作品21
前奏-A-A'-間奏-A-A"形式。左手3連符アルペジオの伴奏にのって流れるような旋律が現れる。旋律・和音ともに半音階的進行が多い。A'では旋律は左手に移ったり、A"ではオクターブで力強く奏されたりと、変奏曲風に繰り返されて奏される。
1934
- Balada バラード
A-B-A'-B'形式。E9~B♭7の和音で始まる霧がかかったような幻想的な響き。全曲、ゆったりとしたアルペジオの伴奏にのって、高音部に笛の音のような旋律が奏される。 - Estudo II em Fá sustenido menor 練習曲第2番嬰ヘ短調
A-B-A-コーダの形式。左手アルペジオの伴奏にのって息の長い旋律が奏される。Aはイ長調と嬰へ短調が揺れ動き、属九の和音が移動するなど調性は定まらず、スクリャービン風に感じます。
1940?
- Coleção mirim 小品集
- Passinhos de dança 踊りの一歩
- Travessa わんぱく
- Corridinha 競走
- No campo... 野外で…
- Natal クリスマス
- Papagaio, periquito... オウム、インコ…
- Patinando no rinque リンクでのスケート
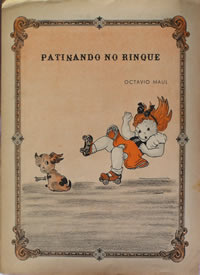
いずれも1941年初版。子どもの世界を愛らしく描いた小品集。第1曲から第3曲までは、楽譜もト音記号のみで技巧的にも初心者向けなのだが、第4曲以降は描写の対象は子どもなのだが、演奏技巧の方はだんだん難しくなり、特に第6、7番はかなりピアニスティック。第1曲〈踊りの一歩〉はハ長調、A-B-A-コーダの形式。子どもがバレエの初歩を習っている光景を描いた風の、可愛らしい曲。右手左手とも殆ど単音で書かれている。Bはト長調になる。第2曲〈わんぱく〉はハ長調、前奏-A-B-A形式。ちょっといたずら好きな子ども(Travessaは女性形なので女の子かな)を描いている。Bはヘ長調、6/8拍子になり女の子の可憐な一面も描写している。第3曲〈競走〉はハ長調、A-B-A'形式。子どもが駆けっコをしているみたいな曲。Bはヘ長調になり民謡風の旋律が奏される。第4曲〈野外で…〉はハ長調、A-B-A'形式。小鳥のさえずりが聞こえてくるような、田舎ののどかな光景が目に浮かぶような曲。第5曲〈クリスマス〉はニ長調、A-B-A'形式。クリスマスで子ども達が浮き浮きしているのを描いてるみたい。Bはト長調になり、静かで平和なクリスマスイブの夜の家庭の団欒を眺めているような温かい雰囲気。第6曲〈オウム、インコ…〉はハ長調、A-A'形式。オクタヴィオ・マウルお得意の、速い両手交互の16分音符連続のパッセージが小鳥を愛嬌たっぷり描写している。第7曲〈リンクでのスケート〉はハ長調、A-B-A形式。この曲は面白い!。最初はおずおずとリンクに上がるも、滑り始まるや段々加速していくのを何とも上手に愛嬌たっぷり描写している。(左の絵は初版時の楽譜の表紙。)
1941
- Xô! Passarinho... 小鳥、シッ!
1942年初版。ヴィラ=ロボスが1926年に作曲したピアノ曲集《シランダス(ブラジル民族舞曲集)Cirandas》の第7番に〈シッ、シッ、小鳥よ Xô, Xô, Passarinho〉という曲があり、曲のアイデアはここから来たのかも知れない。ただしヴィラ=ロボスのちょっと憂うつな曲とは対照的に、マウルのこのピアノ曲はとても華やか!。4分程の短い曲だが、この作品は正にマウルの真骨頂を発揮したような作品で、彼の最高傑作かなと思います。二長調、A-B-A-コーダの形式。忙しない16分音符の両手高速連打は、いくら追い払ってもまとわりついてくるうるさい小鳥みたいで、連打音の半音階が何とも絶妙な響きで面白い(下記楽譜)。Bは静かになり、ブラジル童歌〈シッ、シッ、小鳥よ〉がしっとりと奏される。
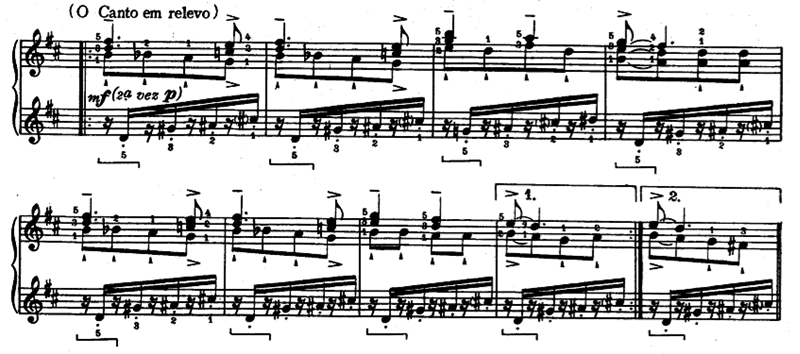
Xo! Passarinho...、13~21小節、Irmãos Vitaleより引用
1947
- Romance ロマンス
1952
- Festa no arraial 田舎の祭り
ブラジルの「6月の祭り Festa Junina」の印象をピアノ曲にしたらしい。ヘ長調、A-B-A'-C-A"-B'-C'-コーダの形式。 全曲速いテンポの、お祭り宛らの賑やかな曲。冒頭のAはマウルらしい16分音符がちょこまかと動く活発な踊りのよう。Bは16分音符のラ-ラ-ラ-ソが何十回も繰り返される無窮動。Cは変イ長調になり両手和音連打で野性的。最後のC'が同主調のヘ長調になるのが作品にまとまりを与えている。 - Tríptico 三部作
ブラジル風味ムンムンの組曲。作曲技法は高度で不協和音の使い方も複雑だ。- Choro ショーロ
一応変イ長調、A-B-B-A'形式。パンデイロがシンコペーションのリズムを奏でるような軽快な曲で、Bのヘ短調の部分は多調になり、溌溂とした響きで面白い。 - Canção カンサォン(歌)
全体的に多調を用いていて、それがアマゾンの密林を連想させるような、神秘的ながらも豊潤な響きの曲。A-B-A'形式。Aはファ♯-ラ-ド♯和音が3-3-2(♪. ♪. ♪)のゆったりとしたリズムを奏で、その上で一応ハ長調の気怠い旋律が奏される。Bは旋律が最初中音部で、やがて高音部オクターブ和音で奏される。 - Dança 舞曲
アフリカ的な野性的なリズムにのった曲で、フルクトゥオーゾ・ヴィアナのピアノ曲《黒人の踊り、作品2-1》に雰囲気が似ている。A-B-C-A'-B'-C'形式。Aはハ短調で始まり、低音の♪♬♪♬のリズムが続く中から旋律が見え隠れする。Bは嬰ヘ短調で始まり音域を拡げ、Cでは16分音符連打やアルペジオが華やかだ。最後のC'は楽譜に "Muito vivo" と記され、テンポアップして熱狂的に盛り上がり、グリッサンドで終る。
- Choro ショーロ
1957
- Duas miniaturas a 4 mãos 連弾のための2つのミニアチュール
- Cirandinha シランジーニャ
ト長調、A-B-A-コーダの形式。Aは高音部16分音符のトリルの旋律が愛嬌あって可愛らしい。Bはハ長調で、ブラジルの童歌〈シランダ・シランジーニャ Ó ciranda, Ó cirandinha〉の旋律が静かに奏される。 - Polka antiga 古風なポルカ
ハ長調、A-B-A'形式。プリモの旋律、セコンドの伴奏ともに愛嬌たっぷりの楽しい曲。
- Cirandinha シランジーニャ
1958
- Toccata トッカータ
強いて言えばニ短調。16分音符で同音連打、アルペジオ、両手交互連打など色々現れる曲。
1963
- Baião バイアォン
バイアォンとはブラジル北東部(ノルデスチ)の代表的な民族舞踊と音楽で、西洋で言うと教会旋法にあたる音階を用いているのがノルデスチ音楽の一つの特徴である。全体的に熱帯の気怠い雰囲気が伝わってくるような曲。ト長調、A-B-C-A'形式。Aののどかな旋律はソのミクソリディア旋法で、内声の対旋律を含んだ重音の響きはサンフォーナ(ノルデスチのアコーディオン)がブイブイ鳴るような響きだ。Bはニ短調になり、くぐもった声のような旋律が現れる。Cはニ長調になり、三段楽譜で書かれていて、低音部は五~八度のベース、中音部はサンフォーナが鳴るような重音でレのミクソリディア旋法の旋律、高音部はトライアングルが鳴るようなシンコペーションのアクセント混じりの16分音符から成り豊潤な響きだ。
作曲年代不詳
- Alegria matinal 朝の喜び
- Avante! Soldadinhos 兵隊達、進め!
- Lenda do velho moinho
- O cavaleiro e a princezinha 騎士と小さな王女
- Paisagem 風景
一応変イ長調、A-B-A'形式。左手8分音符ミ♭-ミ♭-ラ♭のオスティナートにのって、現れては消えるような旋律が奏される。微風が吹く広大な風景を静かに描いたような曲。 - Suite (3 peças) 組曲(3つの小品)
- Prelúdio 前奏曲
ハ長調、A-B-A'-コーダの形式。速い両手連打の軽快な曲。 - Toada トアーダ
ホ長調、A-B-A'-B'形式。ゆったりとしたリズムで子守歌のような六度重音の旋律が郷愁たっぷりと静かに奏される。Bはロ長調だが、B'はホ長調である。細やかな和音使いやBで現れる対旋律などが何とも美しく、マウルのピアノ曲の中で一番美しい曲かなと思います。 - Polka ポルカ
ト長調、A-B-A'形式。愛嬌たっぷりの曲。Bはニ長調になる。
- Prelúdio 前奏曲
- Variações e coral (para Martha Milek autora de tema) 変奏とコラール(主題の作曲者マーサ・ミレクのために)
Octavio Maulのピアノ曲楽譜
Fermata do Brasil
 |
|
Ricordi Brasileira S.A.
- Festa no arraial
- Toccata
Irmãos Vitale
- Xô! Passarinho
作曲者出版
- Estudo em Fá maior, Op. 21
斜字は絶版と思われる楽譜
Octavio Maulのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Obras para piano de OCTAVIO MAUL![]()
![]()
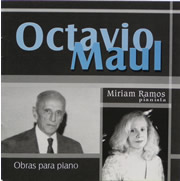 |
|
Miriam Ramos (pf)
1986年の録音で、LPからのリマスタリング。
Piano Brasileiro II + 70 anos de História (2枚組CD)![]()
![]()
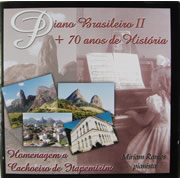 |
CD 1
CD 2
|
Miriam Ramos (pf)
Cristina Ortiz (LP)![]()
SOMLIVRE, 403.6102
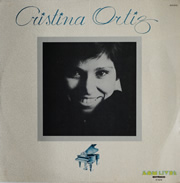 |
|
Cristina Ortiz (pf)
1976年のリリース。
"Futuros Mestres em Música" do curso de mestrado em música da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 007 (LP)![]()
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ 007
- Sonata n.º 1 (Francisco Mignone) - Eduardo Monteiro (pf)
- 6 e 1/2 Prelúdios (Francisco Mignone) - Mônica Salgado Torres Tavares (pf)
- Variações sobre um tema popular (Fructuoso Vianna) - Sergio Tavares (pf)
- Suíte litúrgica negra (Brasílio Itiberê) - Roberto Molinari Neves (pf)
- Suíte brasileira sobre temas originais (Lorenzo Fernandez) - Sônia André Cava de Oliveira (pf)
- Minha terra (Barrozo Netto) - Diva Evelyn Reale (pf)
- Lenda brasileira (Domingos Raymundo) - Harlei Aparecida Elbert Raymundo (pf)
- Estudo II (Octavio Maúl) - Mônica Salgado Torres Tavares (pf)
1988年の録音。
Brasileiras - Duo Fortepiano![]()
- Graciosa - Valsa (Radamés Gnattali)
- Brasiliana Nº 4 (Osvaldo Lacerda)
- Lundu (Francisco Mignone)
- No fundo do meu quintal (Francisco Mignone)
- Congada (Francisco Mignone)
- Brasiliana Nº 8 (Osvaldo Lacerda)
- Cirandinha (Octavio Maul)
- Sonata (Edino Krieger)
- Suite Nordestina (Ernst Mahle)
Sarah Cohen (pf), Miriam Braga (pf)
