Oriano de Almeidaのページ
Oriano de Almeidaについて
オリアノ・ジ・アウメイダ Oriano de Almeida は1921年7月15日、ブラジル北部パラー州の州都ベレンに生まれた(本名はオリアンネ Orianne であったが、フランス語ではOrianneは女性名であるため、彼は20歳の時に芸名をオリアノ Oriano としたとの説がある)。彼の母は薬剤師で、またピアノを弾けたとのことで、オリアンネは子どもの時から母にピアノを習い、その後8歳の頃からリオ・グランデ・ド・ノルテ州州都のナタール(ナタウ)で、彼の従兄にあたるピアニストのワウデマール・ジ・アウメイダ Waldemar de Almeida にピアノを師事した。1930年7月のワウデマール・ジ・アウメイダ門下の発表会で彼はショパンの《夜想曲、作品37-1》を弾いている。1931年に父が亡くなったが、彼はワウデマール・ジ・アウメイダの父の養子として迎え入れられた。1934年の発表会ではリストのピアノ曲《伝説》の第2番〈波の上を歩くパオラの聖フランチェスコ〉を弾いている。同年には自身のソロリサイタルも行い、またブラジル北東部の諸都市で演奏会をしている。レパートリーはバッハやベートーヴェンからドビュッシーやヴィラ=ロボス、ミニョーネまで幅広かったが、特にショパンの演奏に力を入れていた。
1939年にリオデジャネイロに出て、翌年よりピアニストのマグダ・タリアフェロに師事した。1944年から1945年にかけてはヴァイオリニストのヘンリク・シェリングと共にブラジル北部・北東部にあるブラジル軍および米軍のいくつかの基地を訪れて慰問演奏を行った。1946年にはタリアフェロに勧められ、フランス・パリで開催されたロン=ティボー国際コンクールに出場したが予選で落選した。しかし彼はその後も約一年近くパリに留まり、ピアノを練習し、またジョルジュ・ダンドローに作曲を師事した。1947年4月にはパリのサル・プレイエルでソロリサイタルを行い、同年6月にはローマでもリサイタルを行った。
1949年5月、同年秋にポーランドのワルシャワで開かれる第4回ショパン国際ピアノコンクールの出場者を決める、ブラジル国内のコンクールがリオデジャネイロで催された。オリアノ・ジ・アウメイダはこれに出場して予選を通過し、本選ではショパンのピアノ協奏曲第2番を演奏して一等を受賞した。同年9月、第4回ショパン国際ピアノコンクールはオリアノ・ジ・アウメイダも含め65名のコンテスタントの参加のもと、ワルシャワで開催された。審査結果は、第1位から第12位までの入賞者(第1位が2名のため計13名)が全員ポーランド人とソ連人で占められ、オリアノ・ジ・アウメイダは「Distinction」であった。コンクール終了後、オリアノ・ジ・アウメイダはは翌年7月までヨーロッパに留まり、演奏会を催した。
ブラジル帰国後は彼はピアニストとして精力的に演奏会活動を行った。またナタールで「Curso Oriano de Almeida」と称した公開ピアノレッスンを開いた。1952年にはマグダ・タリアフェロ門下のピアニストのイリス・ビアンキ Íris Bianchi と結婚し、二人は「Duo Íris Bianchi-Oriano de Almeida」として活動した。(1962年に二人は離婚した。)
1954年には米国を訪問し、各地で演奏会を行い、またニューヨークではNBC交響楽団との共演でショパンのピアノ協奏曲第2番を演奏した。1958年から翌年にかけて、毎週金曜夜のテレビ番組「O Céu é o Limite」という勝ち抜きクイズ番組に彼は出演した。この番組ではクイズに正解し続けると賞金がどんどん増え、翌週の番組にも出場できるというものであった。オリアノ・ジ・アウメイダはクイズの解答者として毎週正解を続け、クイズに関する音楽をピアノで演奏し、テレビの人気者となった。また1960年にはショパン生誕150周年を記念した毎週月曜夜のラジオ番組「Ciclo Chopin」に出演し、一年間かけてショパンの生涯を解説し、ショパンのピアノ曲をほぼ全曲演奏した。レコード録音としては、1959年にはLP「Oriano de Almeida Interpreta Chopin」をリリースした。作曲家としても、1966年に自作の歌曲集をソプラノ歌手のMaria Helena Coelho Cardosoと共にLPに録音した。また教育者としてもリオグランジ・ド・ノルテ連邦大学音楽学部などで教鞭を執った。
1972年にはヨーロッパを再訪し、スイスのローザンヌでショパンに関する8回に亘る講演会・演奏会を行い、スペインのバルセロナとマドリードでは演奏会を行った。ポーランドではワルシャワのショパン博物館で調査研究を行い、ジェラゾヴァ・ヴォラにあるショパンの生家の日曜日の演奏会に出演した。
1982年には自作のピアノ曲を3枚のLPに録音した。
1988年に心臓手術を受けたのを機にピアニスト引退し、以降は主に執筆活動に専念した。著書には、師のマグダ・タリアフェロとの思い出を書いた『マグダレーナ、マグダレーナさん:マグダレーナ・タリアフェロとの私の思い出 Magdalena, Dona Magdalena: minhas lembranças de Magdalena Tagliaferro』(1993)、ドビュッシーに関して書いた『パリ‥‥、ドビュッシーの時代 Paris... nos tempos de Debussy』(1997) などがある。
2003年、彼は前立腺癌および骨転移と診断された。2005年5月11日、ナタールで亡くなった。
オリアノ・ジ・アウメイダの活動の中心はピアニストとしてであり、おそらく作曲は折りに触れて余暇でしていたものと思われる。彼の作品で残されているのは歌曲とピアノ曲のみである。歌曲は十数曲あり、《カシューナッツ Cajueiro》、《Quando as nuvens eram nossas》(1950) が代表作である。彼のピアノ曲はまだ全ての音源が入手できていないのでその全貌は不明ですが、代表作《ポチグアルの前奏曲集 Prelúdios potiguares》を聴くと、自分の故郷の思い出を自然体で音楽に描いたような作品揃いである。作曲技法は比較的単純で、ピアノ作品の歴史に名を残すような作曲家ではないのだが、だからこそ肩肘張らずに聴けるいい音楽です。
Oriano de Almeidaのピアノ曲リストとその解説
1938
- Suíte, Op. 1 組曲、作品1
まだ十代のオリアノ・ジ・アウメイダの作品。後年の代表作《ポチグアルの前奏曲集》に比べれば和音やピアノの書法は単純だが、彼らしい心温まるような響きのロマンティシズムが漂ってくるような作品である。- Improviso 即興曲
ト長調、A-A'-コーダの形式。アルペジオの優しい伴奏にのって穏やかな旋律が奏される。長九の和音などが魅惑的な響きだ。 - Arabesque アラベスク
ト長調、A-A'-A"-コーダの形式。野鳥の鳴き声のような高音部のモチーフと、少し陰うつな旋律が奏される。 - Valsa ワルツ
ハ長調、A-A'-B-A-コーダの形式。速目のテンポで可憐なワルツが奏される。Bの冒頭はイ短調になるが、間もなくハ長調に戻る。
- Improviso 即興曲
1947
- Valsa de Paris パリのワルツ
オリアノ・ジ・アウメイダは、この《パリのワルツ》の他にも《ロンドンのワルツ》、《モスクワのワルツ》、《ワルシャワのワルツ》を作曲している。ヨーロッパ滞在中に見た各都市の優雅な街並みに印象を受けて作ったのであろうか。《パリのワルツ》はト長調、前奏-A-A-B-A'-コーダの形式。 旋律は3拍子の中で概ね2拍を刻むヘミオラが浮き浮きするような雰囲気を醸し出し、旋律に纏わりつく和音の豊かな響きがパリの華やかさを描いているよう。
1947-1982
- Prelúdios potiguares ポチグアルの前奏曲集(リオ・グランデ・ド・ノルテ州の前奏曲集)
ブラジル北東部の沿岸に住んでいた先住民族の一つにポチグアラ族がいて、今もリオ・グランデ・ド・ノルテ州やパライバ州にその末裔が居住している。「ポチグアラ potiguara」は先住民の言葉で「エビを食べる人」の意味で、現在ではリオ・グランデ・ド・ノルテ州の住民は「ポチグアル(ポチグアー)potiguar」と呼称されている。20曲から成るこの前奏曲集は、作曲当時は組曲として意図されたものではなかったが、1982年にオリアノ・ジ・アウメイダの作品集のLPを作るに当たって、今まで書き溜めていた個々のピアノ曲を組曲として構成したものと思われる(そのため曲順と作曲年は一致しない)。各曲は彼の故郷リオ・グランデ・ド・ノルテ州の自然、人々やその歴史など様々な風物を描いたピアノ曲集である。和声的にはロマン派であり、新しい作曲技法だの、民族音楽の高度な処理だのの難しい音楽はあまり見られないが、オリアノ・ジ・アウメイダが自分の故郷を思って頭に思い浮かんだ音楽をそのまま楽譜にしたような、気取らない自然な書法は我々聴き手にとって親しみ易く、心和むようなこういう音楽っていいじゃない〜と個人的にはとても気に入っている曲集です。1-2番、3-4番、11-12番、13-14番、17-18番、19-20番はそれぞれ平行調で、また5-6番、7-8番はそれぞれ同主調である。- No caminho do sertão (1982) セルタォンの道で
ピアニストのネルソン・フレイレに献呈された。セルタォン sertão とはブラジル北東部の内陸の乾燥地帯を指す。強いて言えばへ長調、A-B-A'形式。馬がトコトコ行くのを描写したような左手伴奏のリズムにのって、右手に16分音符の戯けた旋律がファのミクソリディア旋法で奏される。和音はコードネームでFとE♭のみで旋律も単純だが、荒野の一般道を馬車が行く光景が思い浮かぶような面白い曲である。 - Lenda do carreiro (1966) 牛車引きの語り草
強いて言えばニ短調、A-B-A-コーダの形式。全曲レのドリア旋法で書かれている。Aは嘆くような旋律が繰り返される。Bは6/8拍子になり、ギターを思わせるアルペジオの伴奏にのって、悲しげで素朴な旋律が奏される。 - Toada ingênua (1966) 素朴なトアーダ
トアーダとはブラジル民謡の一つのジャンルで、一般的に単純なメロディーに自然や故郷を歌う哀愁のこもった歌である。ト長調、A-A-B形式。ギターのつま弾きを思わせるアルペジオの穏やかな伴奏にのって、シンコペーション混じりの旋律が歌うように奏される。ブラジルの田舎の光景が眼に浮かぶような、郷愁たっぷりの美しい曲です。 - À sombra da velha jaqueira (1982) 古いパラミツ(波羅蜜)の木陰で
パラミツ(波羅蜜)はブラジルなどの熱帯に生える高木で、大きな果実がなる。ホ短調。パラミツの木陰に佇んでいると、老木が昔からの悲しい歴史を語りかけてくるような雰囲気の曲。アルペジオの静かな伴奏にのって、高音から降るような旋律が奏される。 - Flor de cactus (1982) サボテンの花
強いて言えばニ長調、A-B-A'-B-A"-B-コーダの形式。花をイメージしたワルツのリズムの曲だが、右手旋律はレのリディア旋法なのが謎めいた響きである。Bでは左手はニ長調(ヒポリディア旋法)の上行音階、右手はレのリディア旋法の下行音階が対話するように交互に現れるのが面白い。 - Chorinho de Guarapes (1967) グアラペスの小さなショーロ
グアラペスはナタール市の西部にある地区の名前。ニ短調、A-B-A-C-A-コーダの形式。3-3-2のシンコペーションの左手リズムと、軽快ながらも哀愁漂う右手16分音符の即興的な旋律の組み合わせがショーロらしい雰囲気。 - Sequilhos e alfinins (1982) セキーリョとアルフェニン
セキーリョとはキャッサバやココナッツミルクで作る焼き菓子でタマゴボーロに似ている。アルフェニンは砂糖菓子のこと。ト長調、A-B-A-C-A-B'-A-B-A-コーダの形式。曲名に深い意味はなさそうで、速いテンポの左手3-3-2のシンコペーションと合いの手のような右手和音がお茶目な雰囲気。 - Caiçara do Rio dos Ventos (1982) カイサラ・ド・リオ・ドス・ヴェントス
カイサラ・ド・リオ・ドス・ヴェントス(一般的にはカイサラ・ド・リオ・ド・ヴェント Caiçara do Rio do Vento と呼ぶ)はリオグランデ・ド・ノルテ州にある小さな町の名前。ト短調、A-A'形式。ショーロらしい雰囲気の曲で、左手アルペジオの伴奏にのって、右手に感傷的な旋律がしっとりと奏される。 - Sertanejo cantador (1948) カンタドールのセルタネージョ
カンタドールは和訳すれば「歌手」になるが、特にノルデスチの即興歌手のことをカンタドールと呼ぶらしいです(へペンチスタとほぼ同義)。へ短調、A-B-C-A-B-C'-A'形式。ノリノリのリズムの曲で、ノルデスチの街角の賑やかな光景が浮かんでくるような曲です。Aは前奏のような部分で、速いテンポのリズムが奏される。Bは忙しない16分音符の旋律が現れ、カンタドールがパンデイロ(ブラジルのタンバリン)を叩きながら早口で挑発的な歌を歌うような感じである(ノルデスチの大道芸に、二人の歌手がお互いに即興で早口の歌を歌い合い、パンデイロを叩いて相手を挑発していくという一種の歌合戦があり、エンボラーダとかデサフィオとか呼ばれている)。Cは低弦ギターを思わせる左手オスティナートにのって、朗唱するような旋律がファのミクソリディア旋法で現れる。 - Os negros do Rosário (1982) ホザーリオの黒人達
ノルデスチでは黒人の守護神として知られるホザーリオ(ロザリオ)の聖母マリアを讃えるお祭りが毎年行われており、信者達の行列を描いた曲であろう。ロ長調、A-A'形式。左手低音に信者達の行進を思わせるリズムがppで始まり、それにのって右手高音で(ロ長調だが)レやラがしばしば♮になる旋律が奏される。 - Polytheama (1950) ポリテアマ
ポリテアマとは当時の劇場兼映画館のこと。変ホ長調、A-B-A-B'-C-B'-A-コーダの形式。1952年にオリアノ・ジ・アウメイダと結婚することになるピアニストのイリス・ビアンキに献呈された。楽譜の冒頭には「ラグタイムで In Rag-Time」と記されている。チャールズ・チャップリンが演ずるサイレント映画を彷彿させるような、陽気ながらもノスタルジックな思いが湧いてくるような雰囲気の曲。ストライドピアノ奏法の左手伴奏にのって、シンコペーション混じりの陽気な旋律が奏される。Cの旋律は半音階混じりの16分音符が出て来たりと興に乗った感じでワクワクする。 - Saudades do Potengi (1980) ポテンジ川の郷愁
ナタール市内を流れるポテンジ川を描いたと思われる曲。ハ短調、A-B-C-A-B'-A'形式。Aのアルペジオは滔々と流れるポテンジ川を描いているよう。BとCは哀愁たっぷりの旋律が奏される。B'の後半では旋律も川の流れを思わせる8分音符音階に変奏される。 - O galinho de Santo Antônio (1982) サント・アントニオの雄鶏
ナタール市のサント・アントニオ地区にある教会は、教会のドームの屋根にある避雷針の先端が雄鶏の像なので、「雄鶏の教会 Igreja do galo(またはIgreja do galinho)」と呼ばれている。ハ長調、A-B-A-コーダの形式。Aは穏やかな旋律が四声〜六声の和音を伴って奏され、聖歌の合唱か、または教会の静寂な空気感を思わせる。Bは司祭が聖書を朗読しているようなモチーフが奏される。 - Xarias e canguleiros (1947) シャリア達とカングレイロ達
ナタール市のシダージ・アウタ Cidade Alta 地区の住人は通称「シャリア」(アジの一種のシャレウ xaréu に由来する)と呼ばれ、またその隣のヒベイラ Ribeira 地区の住人は「カングレイロ」(カワハギの一種のネズミモンガラという魚)と呼ばれている。かつて2つの地区はライバル関係で、しばしば石を投げ合って喧嘩することがあったとのことである。イ短調、A-B-A'-B'-B-A"形式。戦いを思わせるような野生的な16分音符の伴奏にのって、Aは高音部の旋律が、Bでは中音部の旋律が交互に荒々しく奏される。 - O alvissareiro da torre da matriz (1982) マードレ教会の灯台の信号
ナタールのマードレ教会は、近くのポテンジ川を航行する船のための灯台をしていたらしい。全体的に神秘的な雰囲気の曲。イ短調、A-B-A'-B-C-A"-B'-コーダの形式。Aは鐘の音のようなモチーフがラのドリア旋法で繰り返される。BはコードネームでD9とAm7のアルペジオが繰り返される。 - Sarau na rua da Conceição (1982) コンセイサォン通りの夜会
ナタール市の中心街にあるコンセイサォン通りには昔はダンスホールもあったのであろう。嬰ハ短調、A-B-A-B-A形式。楽譜の冒頭には「ポルカのようなアレグロ Allegro alla Polka」と記されていて、ちょっと滑稽な感じで垢抜けない速いテンポのポルカが、一時代昔の夜会の光景を思わせる。Bはホ長調になる。 - Comprai Juá Jucá (1982) ジュア、ジュカを買って
ジュア(ジュアゼイロ)とジュカは共に高木で、その草は薬草として利用されているらしい。強いて言えば嬰ヘ長調、A-B-B'-A'形式。Aは街角の薬草売りの掛け声を模した2オクターブのユニゾンがレチタティーヴォ風に奏される。Bは3-3-2のリズムにのって中音部に旋律が現れる。 - Lamento da senzala (1950) センザラの哀歌
センザラとはキンブンド語由来で奴隷小屋という意味(キンブンド語はアフリカのアンゴラのキンブンド人の言葉で、アンゴラからは多くの人が奴隷としてブラジルに連行された)。変ホ短調、A-A'-A"形式。楽譜の冒頭には「物悲しいサンバ Samba dolente」と記されていて、左手低音で刻まれる4分音符は地に着いた奴隷の力強さを表しつつも、右手のシンコペーションのきいた旋律は何とも悲しげな調べである。 - Natal (1951) ナタール
ナタール(ナタウ)Natal はリオ・グランデ・ド・ノルテ州の州都であるが、ポルトガル語では元々はクリスマスの意味である。これはポルトガル人達が1599年12月25日にこの地に村を作ったことに由来している。変ホ長調、A-A'形式。歌にしたくなるようなロマンチックな旋律の曲で、ワルデマール・エンリキ Waldemar Henrique が書いた歌詞による歌曲版もあり、歌詞はナタールの美しさを語っている。A'は音域を広げ、和音を分厚くして変奏されていて一層ロマンチックだ。 - As imburanas da Pedra Grande (1948) ペドラ・グランジのインブラーナ
ペドラ・グランジとはリオ・グランデ・ド・ノルテ州北部にある町の名前。インブラーナとはブラジル北東部などに自生する高木の一種で、薬用植物である。ハ短調、前奏-A-B-A'-C-コーダの形式。楽譜の冒頭には「マシーシのテンポで(ヴィヴァーチェ)Tempo de Maxixe (Vivace)」と記されていて、マシーシ(19世紀ブラジルで流行した舞曲で、2拍子の速いテンポが特徴的)の軽快なリズムにのって颯爽とした旋律が奏される。Cはハ長調になり、左手和音3-3-2リズムの伴奏にのって、右手に16分音符の重音混じりの音階やトリルが華やかに奏される。
- No caminho do sertão (1982) セルタォンの道で
1950
- Aquele fiacre de Roma
イ長調、A-A'-B-A"-(B-)-コーダの形式(カッコ内は楽譜では演奏されないが自作自演LPでは演奏される)。オリアノ・ジ・アウメイダは1950年にヨーロッパに滞在していたので、ローマにも立ち寄ったのであろう。♩ ♪♩. の軽やかで速いテンポの伴奏にのって陽気な旋律が奏される。 - La rue Lauriston ローリストン通り
1958
- Canção de Lílian リリアンの歌
1961
- Blue medieval 中世の青
前奏-A-B-B'-A'-コーダの形式。謎めいた旋律が(一部ドリア旋法となって)奏され、Aはト短調→イ短調→ロ短調、Bも転調が頻繁で幻想的な雰囲気。
1966
- Idílio no caramanchão カラマンシャオ(四阿)の牧歌
何とも心温まるような響きの小品。変イ長調、A-B-A-B'形式。Aは右手旋律+右手内声の16分音符分散和音+左手のシンコペーションリズムが絶妙に絡み合う。Bは左手3-3-2のリズムにのって、右手に郷愁たっぷりの旋律が奏される。
作曲年代不詳
- Aquele realejo de Pigalle ピガールのあのヘアレージョ(アコーディオン)
- Montparnasse Adieu さらばモンパルナス
- Por que tanto amor?
- Prelúdio Ciclame シクラメンの前奏曲
- Quando a primavera voltar 春が再び来た時
- Romanza para uma princesa ある王女のためのロマンス
- Tema de paixão e ternura 情熱と優しさの主題
- Três movimentos poéticos 3つの詩的な楽章
- Uma rosa de junho 六月のバラ
- Uma simples saudade ある素朴な郷愁
- Um blue para Brahms ブラームスのための青
- Valsa de Londres ロンドンのワルツ
変ホ長調、A-A'-B-A'形式。優雅なワルツが奏される。Bは変イ長調になり、オルゴールのような高音で奏される。 - Valsa de Moscou モスクワのワルツ
- Valsa de Varsóvia ワルシャワのワルツ
嬰ハ短調、A-A'-B-B'-A形式。これも優雅なワルツだ。Bは変ニ長調になる。 - Variações românticas ロマンチックな変奏曲
Oriano de Almeidaのピアノ曲楽譜
Fundação José Augusto, Natal
- Prelúdios potiguares (2001)
Escola de Música da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
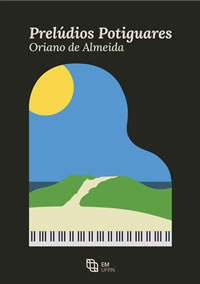 |
|
Ricordi Brasileira S.A.
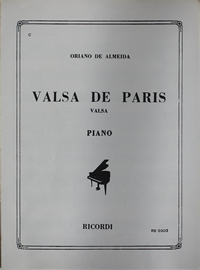 |
|
斜字は絶版と思われる楽譜
Oriano de Almeidaのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Oriano interpreta Oriano (LP)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Projeto Memória-2, UFRN-002
- Convite no olhar
- Suíte
- Improviso
- Arabesque
- Valsinha
- Valsa de Paris
- Valsa de Varsóvia
- Valsa de Londres
- Canção de Lilian
- Tema de paixão e ternura
- Tempos idos
- Idílio no caramanchão
- Cajueiro
- Eu sou de lá
Oriano de Almeida (pf)
Oriano interpreta Oriano Vol. II: Prelúdios potiguares (LP)![]()
![]()
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Projeto Memória-19, UFRN-019
- No caminho do sertão
- Lenda do carreiro
- Toada ingênua
- À sombra da velha jaqueira
- Flor de cactus
- Chorinho de Guarapes
- Sequilhos e alfinins
- Caiçara do Rio dos Ventos
- Sertanejo cantador
- Os negros do Rosário
- Polytheama
- Saudades do Potengi
- O galinho de Santo Antônio
- Xarias e canguleiros
- O alvissareiro da torre da matriz
- Sarau na rua da Conceição
- "Comprai Juá Jucá"
- Lamento da senzala
- Natal
- As imburanas da Pedra Grande
Oriano de Almeida (pf)
Oriano interpreta Oriano Vol. III (LP)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Projeto Memória-20, UFRN-020
- Quando as nuvens eram nossas
- Aquele fiacre de Roma
- Um blue para Brahms
- La rue Lauriston
- Blue medieval
- Aquele realejo de Pigalle
- Três movimentos poéticos
- Variações românticas
Oriano de Almeida (pf)
これらの3枚の自作自演LPは1981-1982年の録音。私が現在入手している音源はVol. IIのみで、Vol. I、Vol. IIIも聴いてみたいです。
Compositores Potiguares![]()
- Royal cinema (Tonheca Dantas)
- Dagmar Duarte Dantas (Tonheca Dantas)
- Louca por amor (Tonheca Dantas)
- Camiho do céu (Severo Dantas)
- Saudades de Muriú (Benilde Dantas)
- Lembranças
- Falando ao coração (Maria Célia Pereira)
- Valsa rubra
- Palmilhando flores (Alexandre Brandão)
- Acalanto e modinha (Waldemar de Almeida)
- À sombra da velha jaqueira (Oriano de Almeida)
- Saudade do Potengi (Oriano de Almeida)
- No caminho do sertão (Oriano de Almeida)
Luiza Maria Dantas (pf)
2002年のリリース。多くの曲がワルツ Valsa であるが、それにしてもテンポ・ルバート超たっぷりな演奏である。
Compositores Potiguares II![]()
- Caiçara do Rio dos Ventos (Oriano de Almeida)
- Da lontan (Paulino Chaves)
- Prece (Dolores Albuquerque)
- A dor calada é a mais sentida (Letícia Galvão)
- Yolanda (Clóvis Cussy)
- Amor em segredo (Paulo Pereira Simões)
- Sonho de amor (Teodorico Guilherme)
- Beijo da criança (José Sinésio)
- Triste e feliz (José Soares)
- Olhos (Abdon Trigueiro)
- Goló (Severo Dantas)
- Amor constante (Tonheca Dantas)
- Royal cinema (Tonheca Dantas)
- Caminho da glória (Alexandre Brandão)
- Alcanto da "Bela infanta" (Waldemar De Almeida)
Luiza Maria Dantas (pf)
2006年のリリース。Compositores potiguaresとは「リオ・グランデ・ド・ノルテ州の作曲家達」という意味。上記2枚のCDを聴くと、ブラジルにはまだ知られざるピアノ曲を作った作曲家がいて、当研究所もまだまだ調べることがあるということが分かります。
Keys to Rio![]()
Sorel Classics, SC CD 010
- Odeon (Ernesto Nazareth)
- Brejeiro (Ernesto Nazareth)
- Faceira (Ernesto Nazareth)
- Coração que sente (Ernesto Nazareth)
- Apanhei-te, cavaquinho (Ernesto Nazareth)
- Gaúcho (Chiquinha Gonzaga)
- Suspiro (Chiquinha Gonzaga)
- Atraente (Chiquinha Gonzaga)
- Ciclo nordestino No. 1, Op. 5: No. 2, Cantiga (Marlos Nobre)
- Ciclo nordestino No. 4, Op. 43: No. 5, Frevo (Marlos Nobre)
- Valsa de Paris (Oriano de Almeida)
- Preludios potiguares: No. 11, Polytheama, No. 1, No caminho do sertão (Oriano de Almeida)
- Valsa da dor (Heitor Villa-Lobos)
- Ciclo brasileiro: No. 2, Impressões seresteiras (Heitor Villa-Lobos)
- Prole do bebê No. 1: No. 1, Branquinha, No. 2, Moreninha, No. 6, Pobrezinha, No. 7, Polichinelo (Heitor Villa-Lobos)
Grace Alves (pf)
2014-2015年の録音、2017年のリリース。
Oriano de Almeidaに関する参考文献
- Joicy Suely Galvão da Costa Fernandes. "Quando as nuvens eram nossas": um itinerário da trajetória musical de Oriano de Almeida (Tese). Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2018.