Jayme Ovalleのページ
Jayme Ovalleについて
ジャイミ・オヴァーリ Jayme Ovalle(正式名はJayme Rojas de Aragón y Ovalle、姓をOvaleと綴る資料もある)は1894年8月6日、ブラジル北部のパラー州ベレンに生まれた。彼の父はチリ出身の移民で、ブラジルのパラー州でゴムノキ(ゴムの原材料となる木)の探査の仕事をしていたが、賭博好きのため一家は経済的に安定せず、ジャイミ・オヴァーリは一時ベレンのカルメル会修道院に入って学んだが直ぐに出てしまい、学校にも通わなかったため読み書きは独学であったとのこと。彼は、姉からもらった弦が一本だけの古いヴァイオリンで音楽を習い始めた。
1904年に父が亡くなり更に経済的に困窮した一家は、1911年に職を求めてリオデジャネイロに移住した。リオデジャネイロで彼は印刷所の仕事に就いた。一方ギター弾きとして腕を上げ、「カニョート Canhoto(左利き)」というあだ名で呼ばれていた。更にオヴァーリは1912年に「グループ・カシャンガ Grupo de Caxangá」という6人組の楽団のメンバーに加わった。この楽団にはピシンギーニャやドンガといった、この後ショーロやサンバの名作曲家となる錚々たるメンバーがいて、彼らはリオデジャネイロのカーニバルでも演奏を行っていた。1913年頃にオヴァーリの妹Leolina Ovalleが軍人のエウクリデス・エルメス・ダ・フォンセカ Euclides Hermes da Fonseca と結婚したが、新郎の父は当時のブラジル大統領エルメス・ダ・フォンセカであった。(エウクリデス・エルメス・ダ・フォンセカはこの後、1922年のコパカバーナ要塞の反乱事件の首謀者として逮捕され服役したが、1930年の革命によりヴァルガスが大統領になると軍人として復権した。オヴァーリが後年、ブラジル財務省の高級官僚として働いたのはこの繋がりだったのかもしれない。)1914年にはフォンセカ大統領の妻ナイール・ジ・テフェー Nair de Teffé が大統領宮殿(カテテ宮殿)でのレセプションでシキーニャ・ゴンザーガの《ガウショ(コルタ・ジャッカ)》をギターで演奏し、大統領宮殿のようなエリート層の集まる所で《ガウショ》のような大衆音楽が、しかもギターで演奏されることは一つの事件であったが、この演奏のアンサンブルのギタリストの一人がオヴァーリだったらしい。
1920年後半に、オヴァーリは作曲家・指揮者のパウロ・シウヴァ Paulo Silva に師事し、作曲や対位法などを学んだ。また詩人のマヌエル・バンデイラ Manuel Bandeira (1886-1968) と出会った。後に、オヴァーリの曲にバンデイラが詩を付けた歌曲《青い鳥 Azulão、作品21》、逆にバンデイラが書いた詩にオヴァーリが曲を付けた《モジーニャ Modinha》はオヴァーリの代表曲となる。
1930年初め頃、オヴァーリはリオデジャネイロ港の税関で働いていた。1933年にイギリスのロンドン駐在ブラジル財務省税関吏に任命された。英語を話せなかったオヴァーリはバンデイラから英語を教わり、ロンドンで4年間勤務した。1937年にはサンパウロ市文化局が主催した管弦楽曲コンテストに、オヴァーリ唯一の管弦楽曲となる交響詩《ペドロ・アルヴァレス・カブラル Pedro Álvares Cabral、作品16》をロンドンで作曲し、応募した。作曲にあたってはロンドン在住のブラジル人ピアニストのManoel Antônio Brauneにお願いして、オヴァーリがギターで弾く音楽や構想をBrauneに管弦楽にしてもらったらしい。しかしコンテストの結果は選外で、一等はジョアン・ジ・ソウザ・リマが受賞した。またロンドンでオヴァーリは《愚かな鳥 The Foolish Bird》という詩集も書いている。
1937年にブラジルに帰国。
1945年には同年に創設されたブラジル音楽アカデミーの会員に選ばれた。
1946年から1950年まで、財務省職員として米国ニューヨークに赴任。オヴァーリは若い頃より数々の女性との交際関係があったが、この時まで未婚であった。が、当地で知り合いになった31歳年下の米国女性Virginia Peckhamとブラジル帰国後に結婚し、一人娘をもうけた。彼は再びリオデジャネイロ港の税関に勤務したが、1955年9月9日にリオデジャネイロで心臓発作のため亡くなった。
ジャイミ・オヴァーリの作品には、前述の交響詩《ペドロ・アルヴァレス・カブラル、作品16》と3本のクラリネットのための《2つの即興曲 Dois improvisos》、14曲の歌曲がある。中でも前述の歌曲《青い鳥、作品21》はビクトリア・デ・ロス・アンヘレス、モンセラート・カバリェ、キャスリーン・バトルといった名歌手たちが録音している。
ジャイミ・オヴァーリのピアノ曲は彼の作品の中心をなしており、下記の作品の存在が確認されている。作曲家として初期と思われる作品6、7、8あたりのピアノ曲はブラジル民族主義がはっきりした比較的分かりやすい作風だが、その後徐々に重く暗い作品になっていき、彼のピアノ曲の代表作と言える3曲の《伝説第1番》、《伝説第2番》、《伝説第3番》はオヴァーリ独特の和音やオクターブの重厚な響きに満ち、調性も定まらず曲がりくねるような和声の、聴き手に媚びることもない謎めいた作品である。オヴァーリはそもそもその生涯からして謎めいていて、読み書きですら独学で、音楽は個人的に習ったのみで音楽学校にも通わず、ヴァイオリンを少し習い街角でギターを弾くも、ピアノを本格的に習った形跡もない。その生涯と、相当にピアノを習った者でないと書けないような濃密な響きのピアノ曲の間にはギャップを感じずにはおれません。オヴァーリの伝記本でもその謎には迫っておらず、私個人的にはもしかしてゴーストライターでも居たのではないかと(失礼ながらも)訝ってしまうのだが、オヴァーリのピアノ曲は大変個性的であり、ヴィラ=ロボス、ミニョーネ、ロレンゾ・フェルナンデスなど当時ブラジルで活躍した作曲家の作風とは全く異なっていて、思い当たるようなゴーストライターも見当たらない。このような作曲家を生む、豊かで多様な土壌がブラジルにはあるのだ、としか言いようがありません。
Jayme Ovalleのピアノ曲リストとその解説
オヴァーリのピアノ曲の作曲年は殆どが不明であるが、大部分は1920年後半から1930年代にかけて作曲されたとされている。
- Martello, Op. 6, No. 1 マルテーロ、作品6-1
マルテーロとは決まった韻律(リズム)の詩をギターの伴奏で独特の節回しで歌う、ブラジルの伝統的な芸能である。ニ長調、A-A'-B-A-コーダの形式。ギターのストロークを思わせるI度とIV度の和音の繰り返しにのって、短いモチーフが何度も奏される。時々レのミクソリディア旋法になったり短調になったりする所は、ブラジル北東部(ノルデスチ)の音楽を思わせる。 - Desafio, Op. 6, No. 2 歌合戦、作品6-2
強いて言えばイ長調。勇ましい中音部の旋律と合の手のように聴こえる低音部の旋律の掛け合いが奏される。中音部の旋律はラのミクソリディア旋法やフリギア旋法になったり、低音部の旋律はペンタトニックだったりと、この曲もノルデスチの雰囲気たっぷりである。 - Xangô, Op. 6, No. 3 シャンゴ、作品6-3
シャンゴとはアフリカ由来のブラジルの民間宗教カンドンブレの神の一つで、雷神とか裁きの神とか言われている。かつてアフリカからブラジルに奴隷として連れて来られた人たちがもたらした宗教がブラジルで独自の発展を遂げ、彼らの子孫が現在に到るまでカンドンブレの信仰を続けている。ホ短調、A-B-A'形式。低音オクターブバスの伴奏にのって重々しい旋律が奏される。Bは6/8拍子になる。 - Cantilena, Op. 7 カンチレーナ、作品7
強いて言えばイ短調。一人が朗唱しているような旋律が数小節現れ、続いて大勢が合唱するような重たい和音が続くのが繰り返される曲。曲の形式や、荘厳な雰囲気は、言わばレスポンソリウム(独唱と合唱が交互に歌う聖歌)を思わせる。 - Aboio, Op. 8 アボイオ、作品8
アボイオとはブラジルの牧童の牛追いの歌で、決まったリズムはなく、歌はだいたい母音のみで発せられるので歌詞はあるようなないようなである。この曲は旋律も和声も単純だが、荒涼とした大草原の空気感が伝わってくるような趣深い曲だ。強いて言えばホ短調、A-B-A'形式。低音部ミ-シと中音部レ-ミ-ソ-シの和音が一定のリズムでppで静かに繰り返され、それにのって牧童が即興で歌うような息の長い(ほぼ)ミのドリア旋法の旋律が現れる。広大な草原に吹く乾いた風と一人ぼっちの牧童の姿が浮かんでくるような感じだ。短いBはテンポを速め、急き立てられるような左手16分音符と右手付点音符は、牛の群が走り出したのを描いているような感じ。 - Estudo, Op. 9, No. 1 練習曲、作品9-1
ニ長調。1分足らずの短い曲で、タランテラ風。 - Scherzo, Op. 9, No. 2 スケルツォ、作品9-2
強いて言えば嬰ト短調。この曲も1分足らずの短い曲で、力強い左手4分音符にのって古風な旋律が奏される。 - Lembranças de São Leopoldo, Op. 11 サン・レオポルドの思い出、作品11
サン・レオポルドはブラジル南部リオグランデ・ド・スル州の都市。2曲とも静かで穏やかな曲で、何とも言えぬ趣がある。- Guriatã de coqueiro スミレフウキンチョウ(菫風琴鳥)
スミレフウキンチョウは南米に生息する雀の一種である。変ト長調、A-B-A'形式。穏やかに語りかけるような旋律がソ♭のミクソリディア旋法で奏される。 - Paquetá パケタ
変ホ短調、A-A'-B-A"形式。陰うつな旋律が歌うように奏される。
- Guriatã de coqueiro スミレフウキンチョウ(菫風琴鳥)
- Preludio, Op. 12 前奏曲、作品12
イ短調。バロック風の旋律が三声または二声のポリフォニーとなって奏される。 - Cantos Romeiros, Op. 13 巡礼者たちの歌、作品13
現世の苦しみを背負ったような雰囲気と、魂の救いを求めるような敬虔な気持ちが入り混じったような重々しい響きの曲。ロ短調、A-B-C-A'-B'-C'形式。Bはホ短調〜イ短調、Cは嬰へ短調だが、再現部のB'とC'はいずれもロ短調である。 - Dois retratos, Op. 14 2つの肖像画、作品14
- Manuel Bandeira マヌエル・バンデイラ
詩人のマヌエル・バンデイラはオヴァーリの友人で、バンデイラの詩とオヴァーリの音楽でいくつかの歌曲が作られている。ロ短調。重々しい和音とオクターブのバスの下行にのって、哀愁漂う旋律が語るように奏される。 - Maria do Carmo マリア・ド・カルモ
マリア・ド・カルモはオヴァーリの恋人だった女性らしい。ホ短調、A-B-A'形式。Aは短三長七の和音や増六の和音の静かなアルペジオが謎めいた雰囲気。Bはゆっくりしたシンコペーションのリズムにのって物思いに耽るような旋律が奏される。
- Manuel Bandeira マヌエル・バンデイラ
- Nininha, Op. 15 ニニーニャ、作品15
ニニーニャとは上述のマリア・ド・カルモの愛称であったとのこと。イ長調、主題〜6つの変奏〜主題からなる形式である。冒頭の主題は9小節で、穏やかな4拍子の旋律が四声のコラール風に奏される。第1変奏から第5変奏までは6/8拍子で、第1変奏は三声のポリフォニーが穏やかに奏される。第2変奏は旋律が和音となって奏される。第3変奏は旋律が低音オクターブで重々しく奏される。第4変奏は嬰ヘ短調になる。第5変奏はイ長調に戻り、右手和音の旋律と左手の中音部対旋律+ベースが重厚な響き。第6変奏は嬰ヘ短調になり、シンコペーション混じりとなる。最後に主題が嬰へ短調で奏されてピカルディの三度で終わる。 - Album de Isolda, Op. 17 イゾルダのアルバム
イゾルダは、オヴァーリの姪(オヴァーリの妹Leolina Ovalleの子で、後に画家として有名になる)の名前である。子どものためらしい作品で、構成や和声は分かりやすく、またピアノ技巧的にも初心者向けで、I、II、IV、VI番は右手・左手それぞれ単音のみで弾かれる。ポリフォニックな曲が多く、バロック組曲風にも聴こえる組曲である。- Allegretto
ニ長調。分散和音の伴奏にのって素朴な旋律が奏される。 - Allegretto
ロ長調。メヌエット風で、右手・左手の二声の掛け合いになっている。 - Allegretto
ニ長調。穏やかな旋律に対旋律が加わり、二声〜三声となる。 - Andante cantabile
ロ長調。アルペジオの伴奏にのって、歌うような伸びやかな旋律が奏される。 - Moderato
ホ長調。語りかけるような優しい旋律に対旋律が加わり、三声となる。 - Moderato
嬰へ短調。可憐で物悲しい旋律が奏される。
- Allegretto
- Ninanatatana (Coral), Op. 18
ロ短調。重々しい旋律が和音を伴って奏され、低音16分音符で半音階の対旋律が蠢くように響く。 - I. Legenda, Op. 19 伝説第1番、作品19
オヴァーリは3曲の《伝説 Legenda》と題するピアノ曲を作っている。3曲共に演奏時間12〜13分くらいに及ぶ大曲にもかかわらず、同じ旋律の再現時は和音を含め大幅に変奏されていて同一の繰り返しが見られない。また両手オクターブや重厚な響きの和音を多用した重々しい雰囲気、複雑な不協和音など、曲の意図が謎めいていながらも大曲の風格たっぷりの力作である。オヴァーリのピアノ曲に代表作として知られている曲などないのだが、音楽的に代表作をと問われれば、これらの3曲の《伝説》を挙げるのが相応しいであろう。第1番はA-B-C-D形式と、旋律の繰り返しは認めないが、曲全体に通ずるモチーフを用いることによって全体的に統一感のとれた作品である。Aは概ねロ長調。まずオクターブバスのゆっくりした連打にのって、右手に和音を伴った旋律が奏され重々しい雰囲気。2小節目の旋律で現れる♫♩. ♪♫のリズムはこの曲全体でしばしば現れるモチーフ(モチーフ1)となっている。続いて両手オクターブによるレ♯のフリギア旋法の旋律・対旋律がポリフォニックに奏される部分、嬰ト短調の♫♫♫♩|♩. ♪♩♩のモチーフ(モチーフ2)で始まる陰うつな部分、ややテンポを速めて付点のリズムで奏される、レ♯のフリギア旋法の急き立てられるような旋律の部分と続く。Bは文献によっては移行部とされる部分である。Cは概ねロ短調。ティンパニのトレモロを思わせる低音分散七度の部分にのってシのフリギア旋法の謎めいた旋律が現れるの部分、モチーフ1のリズムの繰り返しが荘厳に奏される部分、低音減五度の16分音符アルペジオにのってモチーフ2が二倍速になって劇的に盛り上がる部分と続く。Cは野生的な左手低音リズムで始まり、シのフリギア旋法の旋律がオクターブで鳴り響く(時々モチーフ1のリズムも聴かれる)。最後は低音3オクターブのうねるようなアルペジオにのって息の長い旋律がオクターブで奏され、消えるように終わる。 - Dois tangos, Op. 20 2つのタンゴ、作品20
- Tango I タンゴ第1番
ロ短調、A-B-A形式。右手に和音を伴ったアルゼンチンタンゴらしい旋律が奏され、左手低音部に半音階進行の16分音符がドロドロと鳴って何ともドス黒い雰囲気。Bは嘆くような旋律となる。 - Tango II タンゴ第2番
ハ短調、A-B形式。嘆くような旋律が現れ、ギターの音色を思わせるバスが対旋律のように動く。2/4拍子が2または6小節続くと2/8拍子が1小節挟まれる所は、溜息をついているような感じだ。
- Tango I タンゴ第1番
- II. Legenda, Op. 22 伝説第2番、作品22
嬰へ短調、A-A'-A"-コーダの形式。Aは右手はオクターブ和音を伴った旋律、左手は対旋律を兼ねたオクターブのバスで、冒頭から力強く重々しい響きだ(下記の楽譜)。
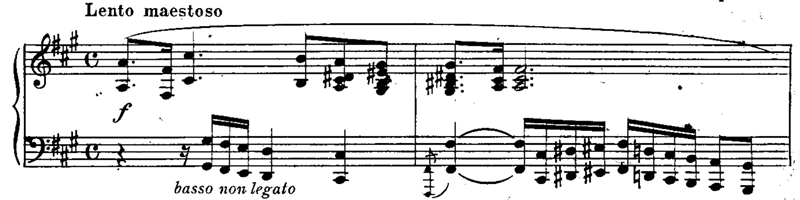
II. Legenda, Op. 22、1-2小節、Casa Arthur Napoleãoより引用
3連符が続く4小節を経て、変ロ長調とも変ロ短調ともつかぬ部分が右手2分音符のモチーフ+左手低音オクターブの半音階進行でppで始まり、両手オクターブ和音の華やかな響きに展開される。A'とA"はAの変奏で、両手オクターブ16分音符や和音がこれでもかという位に轟く(下記の楽譜)。
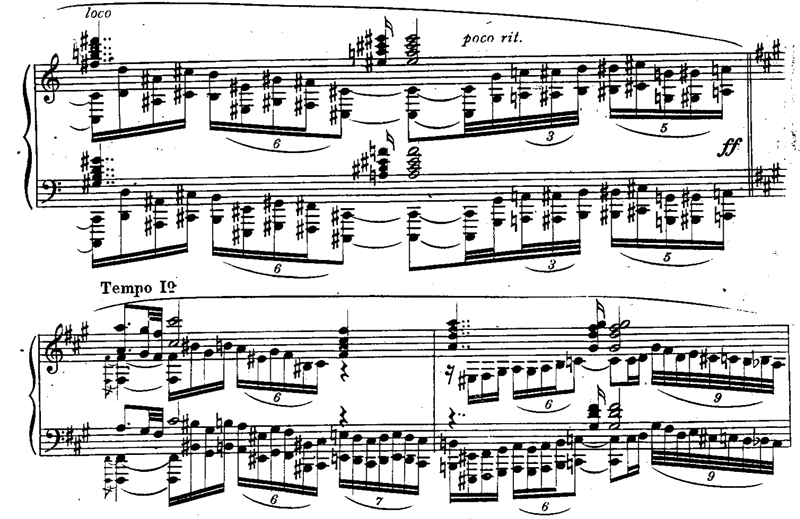
II. Legenda, Op. 22、90-92小節、Casa Arthur Napoleãoより引用 - III. Legenda, Op. 23 伝説第3番、作品23
1934年にロンドンでピアニストのManoel Antônio Brauneが行ったリサイタルで演奏されたとの記録がある。嬰ヘ長調、A-B-A'-B'-A"形式。冒頭は右手オクターブで穏やかな旋律が奏されるが、低音部はファ♯の分散オクターブがドローンとなって鳴り続き、中音部で対旋律が半音階を上下し、全体的に神秘的な雰囲気だ(下記の楽譜)。
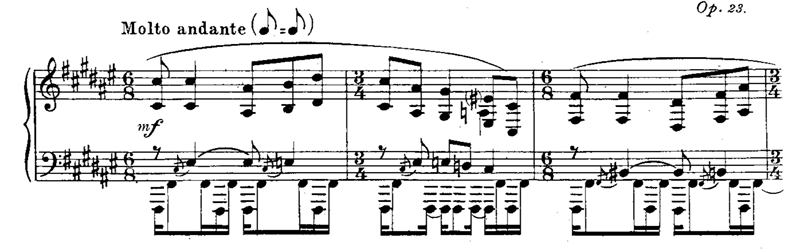
III. Legenda, Op. 23、1-3小節、Casa Arthur Napoleãoより引用
間もなくオクターブの主旋律は高音で和音を伴い、中音部対旋律もオクターブとなって派手に動き回り劇的な響きとなる。Bは別の旋律が現れるが、これも繰り返す毎に音量を増して派手な響きとなる。A'とB'はABの変奏だが和音は変わり、B'の両手オクターブ和音の盛り上がり方は凄い(下記の楽譜)。
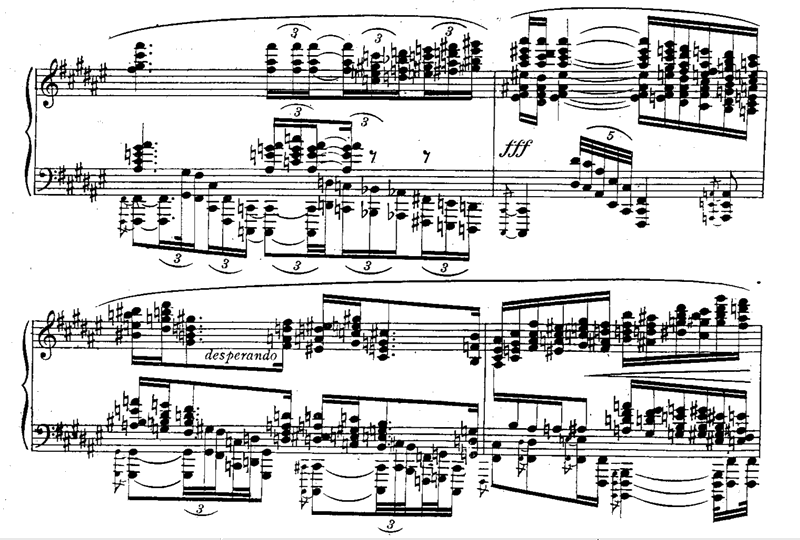
III. Legenda, Op. 23、80-83小節、Casa Arthur Napoleãoより引用
A"は冒頭の旋律が回想され、潮が引くように静かに終わる。 - Devaneio, Op. 24 夢想、作品24
長調とも短調ともつかない4分音符のモチーフが右手にゆらゆらと奏され、左手の音形は静かな8分音符から激しい16分音符オクターブまで盛り上がる。 - Noturno, Op. 25 夜想曲、作品25
嬰へ短調、A-B-C-A'-B'-C'形式。Aは暗い闇を表すような旋律が重々しく奏される。7小節のつなぎのようなBを経て、Cは嬰ト短調になり、暗い旋律の下で半音階進行のオクターブバスが蠢く。A'は嬰ト短調、C'は嬰へ短調になる。 - Lamuria, Op. 26 嘆き、作品26
陰うつな旋律がゆっくりと奏され、中音部の対旋律やバスがいずれも半音階進行するのでくすんだ響きである。曲の中間では苦悩を絞り出して訴えるようなffが響き、また静かになって終わる。 - Improviso I, Op. 27 即興曲第1番、作品27
A-B-A'形式。Aは右手ファ♯全音符の下で、左手に謎めいたモチーフが繰り返される。Bは嬰ハ短調で、重々しい旋律が繰り返される。 - Habanera, Op. 28 ハバネラ、作品28
嬰へ短調、A-B-A'-B'形式。Aは4/4拍子の右手の重々しい旋律リズムがζ♫♫♫|♩♫♫♫、左手伴奏は8分音符分散和音であまりハバネラは感じられない。Bは右手旋律に付点のリズムが現れてハバネラらしくなるが、何とも思い情念の雰囲気の曲である。 - Romança, Op. 29 ロマンサ、作品29
ホ長調、A-B形式。旋律は穏やかだが、対旋律の半音階進行が醸し出す短調の響きが陰を帯びている。旋律・対旋律は繰り返されるたびにオクターブになって音量を増し、また静かになって終わる。 - Improviso II, Op. 30 即興曲第2番、作品30
強いて言えば嬰ハ短調かホ長調、A-A'形式。低音オクターブの重々しいベースの上で、上がっては下がる旋律が気怠い雰囲気。 - Madrigal, Op. 31 マドリガル、作品31
変ホ短調、A-A'形式。二声で宗教歌を歌うような雰囲気の曲。 - Valsa, Op. 32 ワルツ、作品32
ホ短調。四声で書かれていて、付点のリズムがずっと続く。
Jayme Ovalleのピアノ曲楽譜
Casa Arthur Napoleão
- I. Legenda, Op. 19
- Dois tangos, Op. 20
- II. Legenda, Op. 22
- III. Legenda, Op. 23
- Noturno, Op. 25
- Habanera, Op. 28
- Romança, Op. 29
- Valsa, Op. 32
斜字は絶版と思われる楽譜
Jayme Ovalleのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
The Ovalle Project![]()
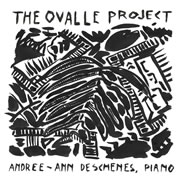 |
CD 1
CD 2
|
Andree-Ann Deschenes (pf)
2018年のリリース。オヴァーリのピアノ曲のおそらく全曲を録音したCD。
Noturnos Brasileiros![]()
Funarte, ATR 32056
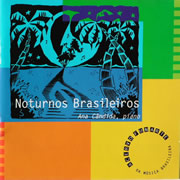 |
|
Ana Cândida (pf)
1961年録音のLPより復刻CD。
Brasil a 4 mãos![]()
Academia Brasileira de Música, ABM Digital
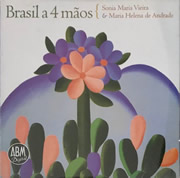 |
|
Sonia Maria Vieira (pf), Maria Helena de Andrade (pf)
《Azulão》はジャイミ・オヴァーリ作曲の歌曲をピアニストのJosé Alberto Kaplanがピアノ連弾に編曲したもの。
O Piano de Norte a Sul (LP)![]()
Sociedade Cultural e Artistica Uirapuru, LPU-1012
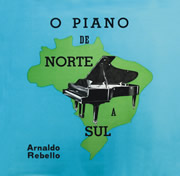 |
|
Arnaldo Rebello (pf)
Duo Kaplan-Parente - Piano Brasileiro a 4 Mãos (LP)![]()
![]()
Discos Marcus Pereira, MPA-9359
 |
|
José Alberto Kaplan (pf), Gerardo Parente (pf)
1977年の録音。
Jayme Ovalleに関する参考文献
- Humberto Werneck. O santo sujo: A vida de Jayme Ovalle. Cosac Naify 2008.
- Felipe Novaes Cantão. Três legendas de Jayme Ovalle: contribuições para o estudo e técnica do piano (Dissertação). Universidade Federal do Pará 2013.