Luis Humberto Salgadoのページ
Luis Humberto Salgadoについて
ルイス・ウンベルト・サルガード・トーレス Luis Humberto Salgado Torres は1903年12月10日、エクアドル北部、ピチンチャ州カヤンベ Cayambe に生まれた。彼の父は、地元の教会の聖歌隊の指揮者を務める作曲家であった。3歳の時に一家は首都キトに転居し、サルガードは8歳にしてキトの国立音楽院に入学し、ピアノと作曲を学んだ。小学校時代は、登校する前の早朝に父から和声を習い、昼間は小学校に通い、放課後は国立音楽院に行くというハードな生活だったらしい。青年時代には、映画館のピアノ弾きなどで収入を得ていた。
1928年にはリストのピアノ協奏曲のソリストを務めピアニストとしてデビュー。キトやグアヤキルで演奏会を催した。1931年にはLaura Merizalde Villavicencioと結婚し、長男をもうけたが、1935年に離婚している。(生計を立てるため、サルガードは映画館やナイトクラブでのピアノ弾きやピアノ教師に精を出し過ぎた影響で離婚したとする資料がある。)1934年には国立音楽院の和声と対位法の教授に就任し、その後、約四十年に亘り国立音楽院で教鞭をとった。
サルガードは欧米に留学するチャンスはなかった(1938年に、彼は政府にヨーロッパ留学の奨学金を申請したが、却下されている)。国立音楽院の教授とは言え、この頃まだエクアドルでは新古典主義だの十二音技法だのの現代音楽を詳しく知る者は居なかった。サルガードの弟は外交官だったので、弟がヨーロッパに行った折に購入してもらった本やレコードから、彼は独学で無調、十二音技法から微分音、偶然性の音楽まで学んだ。またサルガードはエクアドル国内各地を訪れ、民族音楽の調査を行った。更に彼は1938年から1945年にかけて「アンデスの声 (Voz Andes) 楽団」の指揮者を務めたり、ラジオに頻繁に出演してエクアドル民族音楽の紹介に努め、『エクアドル固有の音楽 Música vernácula ecuatoriana』(1952) という論文を著した。
サルガードは晩年まで作曲家として活動し続けた。1977年12月12日、キトで亡くなった。
サルガードの作品は多くのジャンルに亘り、作品数は約150作に及ぶ。代表作は9曲の交響曲で、《交響曲第1番 アンデス Primera sinfonía, Andina》(1945-1949) は第1楽章ではサンフアニートのリズムを、第2楽章はヤラビを、第3楽章はダンサンテを、第4楽章はアルバーソ、アイレ・ティピコ、アルサを用い、アンデスの音楽らしい五音音階も多用されているが、その一方、一部で十二音技法も使うという何とも意欲的な作品である。また《交響曲第2番 総合的 Segunda sinfonía, Sintética》(1953)、《交響曲第3番 ロココ風の主題“ラ-レ-シ-ソ-ミ”による Tercera sinfonía sobre un tema Rococó: A-D-H-G-E》(1954-1955)、《交響曲第4番 エクアドル風 Cuarta sinfonía, Ecuatoriana》(1957)、《交響曲第5番 ネオロマンティック Quinta sinfonía, Neoromántica》(1958)、《交響曲第6番 弦楽とティンパニーのための Sexta sinfonía para orquesta de cuerdas y timbales》(1968)〜フーガなどが現れる新古典主義の様式の作品、《第7交響曲 Séptima sinfonía》(1970)〜ベートーベン生誕二百年を記念した作品で十二音技法を多用、《交響曲第8番 ピチンチャの戦い150年周年を記念して Octava sinfonía, dedicada al Sesquicentenario de la Batalla de Pichincha》(1972)〜民族主義的な作品、《交響曲第9番 総合的第2番 Novena sinfonía, Sintética No. 2》(1975-7) を作曲した。管弦楽曲では、《性格的な作品 Pieza característica》(1950)、《エクアドル組曲 Suite ecuatoriana》(1969) などがある。協奏曲では、《計画的ピアノ協奏曲 太陽の乙女たちの聖別 La consagración de las vírgenes del sol, Concierto programático para piano y orquesta》(1941)、《民族的様式による幻想(ピアノ)協奏曲 Concierto fantasía en estilo nacional para piano y orquesta》(1948、エクアドル文化社コンクール一等賞受賞作)、《ヴァイオリン協奏曲》(1953)、《ホルン協奏曲》(1968)、《チェロ協奏曲》(1974-5)、《ギターのためのエクアドル協奏曲 Concierto ecuatoriano para guitarra y orquesta》(1976) などがある。室内楽曲では《弦楽四重奏曲第1番》(1958) 、《弦楽四重奏曲第2番》(1958)、《ピアノ五重奏曲第1番》(1963) 、《ピアノ五重奏曲第2番》(1973)、《ヴァイオリンとピアノのためのエクアドル奇想曲 Capricho ecuatoriano para violín y piano》(1946)、《ヴァイオリンソナタ》(1961)、《チェロソナタ》(1962)、《ヴィオラソナタ》(1973) などがある。サルガードはオペラを4つ作曲している。その中でも3幕から成るオペラ《クマンダ Cumandá》(1940-54) は、 エクアドルの作家フアン・レオン・メラ Juan León Mera の同名の小説(アマゾンの密林を舞台にした、先住民として育てられた娘クマンダの悲恋物語)を元にしていて、先輩作曲家シクスト・マリア・ドゥランも同名のオペラを1900-1911年頃に作曲しているが、いずれも未だ上演されていない。バレー音楽の代表作《舞踊組曲 Suite coreográfica》(1944-6) はBallet ShyriとBallet aborigenの2部から成り、先住民族の姿をスペイン征服前後に分けて描いている。歌曲や合唱曲も多数作曲した。
サルガードは下記のリストの通り、多数のピアノ曲を作曲したが、出版譜も録音も一部の作品のみしかなく、全貌は私も分かりません。サルガードお得意の十二音技法を用いた作品は意欲的ではあるが難解でもあり、また一方、エクアドル民族音楽の響きをそのままピアノ曲にしたような素朴な作品も多いのが特徴である。いずれの作風においても、インディヘナ(先住民)由来の民俗音楽であるダンサンテ danzante、ヤラビ yaraví、ユンボ yumboや、メスティーソ(インディヘナと白人の混血である人々)のアイレ・ティピコ aire típico、アルバーソ albazo、アルサ alza、パシージョ pasillo、サンフアニート sanjuanito などをふんだんに用いており、エクアドル民族主義を代表する作曲家に相応しいピアノ曲を残している。
Luis Humberto Salgadoのピアノ曲リストとその解説
1929
- Idilio a orillas de un lago, Barcarola ある湖の岸の牧歌、舟歌
1932
- Rapsodia aborigen (Rapsodia ecuatoriana) Nº 1 "En el templo del sol", Op. 16 先住民の狂詩曲(エクアドル狂詩曲)第1番「太陽の神殿にて」、作品16
1933
- Inti Raymi (Fiesta del sol), Música de ballet para piano インティ・ライミ(太陽の祭り)、ピアノのためのバレー音楽
1938-1940
- Tríptico aborigen, Tres danzas vernáculas 先住民の三部作、3つの土着の踊り
- En la feria de mi pueblo 私の村の市(いち)で
- Quenas y rondadores ケーナとロンダドール
- Fiesta aborigen 先住民の祭り
1940
- Fox-preludio フォックスー前奏曲
1940-1941?
- Fiesta Corpus en la aldea, Escenas típicas serraniegas 村の聖体祭、セラニエガ(山に住む人々)の典型的な光景
- Misa de fiesta y de procesión 聖体祭のミサと行列
- Los danzantes 踊り手たち
- En casa de los priostes プリオステ達の家で
1942
- Brisas del Cayambe, One-step カヤンベのそよ風、ワンステップ
- El páramo, Preludio andino-ecuatoriano パラモ、エクアドル・アンデス山脈の前奏曲
パラモとは、コロンビア・エクアドル・ベネズエラにまたがる標高3000メートル以上の高原地帯のこと。曲はファ-ラ♭-シ♭-ド-ミ♭の五音音階から成る、アンデスの民謡を思わせる旋律で始まる。この旋律は素朴な響きだが、半音階の対旋律などが絡み徐々に複雑になる。後半ではト長調のアルペジオ伴奏にのって、レ♭-ミ♭-ファ-ラ♭-シ♭の五音音階の旋律が現れて多調になり、頻繁な転調をしていく。和声的に、エクアドル民謡と現代音楽の技法を混ぜようとした、意欲的なピアノ曲に思えます。 - Galería del folklore andino-ecuatoriano, Seis cuadros vernáculos エクアドル・アンデスのフォルクローレの画廊、6つの土着の描写
- Evocación a los espíritus nativos del lago, Barcarola 湖の精霊への想起、舟歌
- Criollo sentimental y festivo, Yaraví y albazo 感傷的で陽気なクリオージョ、ヤラビとアルバーソ
- Brindis por la peaña, Alza
- Después de la cosecha, Danzante 収穫の後に、ダンサンテ
- El pintoresco baile de las cintas, Sanjuanito 絵のような美しいリボンの踊り、サンフアニート
- Siga la farra, Aire típico 騒ぎ続けて、アイレ・ティピコ
1943
- Mascarada indígena, Sanjuanito 先住民の仮装行列、サンフアニート
1944
- Sanjuanito futurista, Microdanza 未来派のサンフアニート、ミクロダンサ
サンフアニートとは、エクアドル民族舞踊・音楽の一つで、2拍子の活気あるリズムが特徴的。スペイン語の "San Juan" ーすなわち「聖ヨハネ」に起源する言葉で、洗礼者ヨハネの誕生日の6月24日を祝う「聖ヨハネ祭」で踊られたのが元だとされている。(サンフアニートが先コロンブス期の先住民由来であるとの説もある。インカ帝国における太陽神を祭る「インティ・ライミ Inti Raymi(太陽の祭り)」もたまたま6月24日であり、その関連も言われている。)元々は笛と太鼓で演奏されていたが、20世紀前半にはギターやヴァイオリンも加わってエクアドルで流行した。この作品はエクアドル民族音楽であるサンフアニートと、現代音楽の十二音技法を融合しようとした、サルガードの作曲家としての象徴的な「未来派」の作品である。曲はA-B-Aの三部形式。冒頭の4小節から成る前奏は、リズムはサンファニートだが、音の方は早速、1小節目で十二音が全て現れ、次の2小節目でまた十二音が全て現れる(下記の楽譜)。音が現れる順番は、1小節目はミ-ラ-レ-ソ-ド-ファ-シ-‥‥、2小節目はミ-シ-ファ♯-ド♯-ソ♯-レ♯-ラ-‥‥と1小節目の反行形にほぼなっている。

Sanjuanito futurista, Microdanza、1-4小節、Luis Humberto Salgado. Un quijote de la música、Ediciones del Banco Central del Ecuador / Benjamin Carrionより引用
5小節目から始まるAの部分は♩=100にテンポを速めて軽快に奏される。5-6小節で現れる十二音の音列は、反行形(7-8小節)、逆行形+移高(9-10小節)、逆反行形+移高(11-12小節)に音列が変形される(下記の楽譜)。これらの音列の特徴は随所に五音音階を挟んでいることで(下記楽譜の青の楕円)、サルガードが十二音技法の中にもエクアドル民族音楽の響きを混ぜようとした跡が窺える。
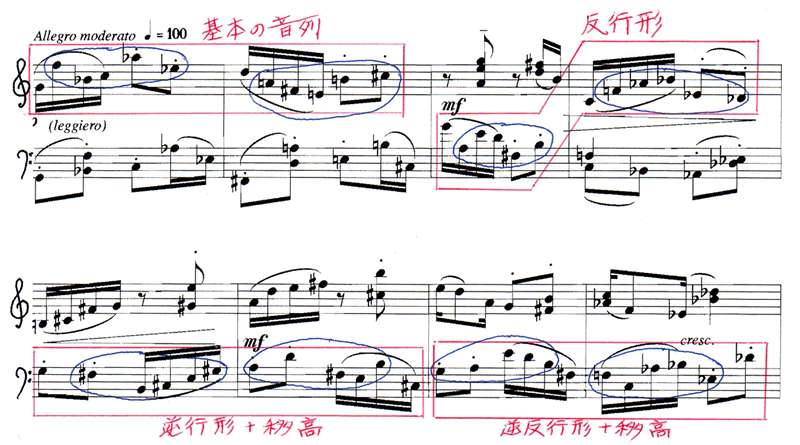
Sanjuanito futurista, Microdanza、5-12小節、Luis Humberto Salgado. Un quijote de la música、Ediciones del Banco Central del Ecuador / Benjamin Carrionより引用(一部加筆)
Bの部分は、サンファニートのリズムはほぼ同じながら、スラーの続いた滑らかな響きになり、音列とその反行形が同時に(合わせ鏡のように)奏されたりしてひとしきり盛り上がる。以上、楽譜を眺めているとサルガードの新しい作曲法への意気込みは十分感じる作品であるが、実際の音楽として聴いた際の響きは、民族音楽の匂いを少しは感じるものの、正直言って???かな。 - Nochebuena de antaño, Sanjuanito 昔のクリスマスイブ、サンフアニート
- Baile de arroz quebrado, Albazo 砕米の踊り、アルバーソ
- Jarana antareña, Alza
- Romance criollo, Aire típico クリオージョのロマンス、アイレ・ティピコ
- Mascarada de Corpus, Danzante 聖体祭の仮装行列、ダンサンテ
- En la corte del Rey Shyri, Danza ritual シリ王の宮廷にて、祭儀の踊り
- La despedida, Yaraví 別れ、ヤラビ
194?
- En torno a la choza, Sanjuanito 山小屋の回りで、サンフアニート
ニ短調、前奏-A-A-B-B-C-C-後奏の形式。民謡にそのまま伴奏を付けたような素朴な曲。トントントントンと足踏みをするようなリズムの8分音符の前奏に引き続き、Aはシ♭抜きのヘキサトニック音階の旋律、Bは一時ト短調になりこれもヘキサトニック。Cでは旋律が右手〜左手と受け継がれる。 - Visiones proféticas de Viracocha, Preludio ビラコーチャの予言的な幻影、前奏曲
- Pase del niño (escena típica), Sanjuanito 子供の行進(典型的な光景)、サンフアニート
- Pase del niño (escena típica de Navidad), Canción 子供の行進(クリスマスの典型的な光景)、カンシオン
1945
- El postrer brindis, Tonada y aire típico 最後の乾杯、トナーダとアイレ・ティピコ
- Arpa de mi tierra, Albazo 我が故郷のアルパ、アルバーソ
- Quiteño de Quito, Pasacalle キトの人、パサカージェ
- Mascarada de inocentes, Sanjuanito 無邪気な仮面行列、サンフアニート
- Rapsodia ecuatoriana Nº 2 エクアドル狂詩曲第2番
エクアドル狂詩曲と題した作品はこの第2番と、1947年作曲の第3番が残されているが、1932年作曲の《Rapsodia aborigen Nº 1 "En el templo del sol"》をサルガードは第1番と数えていた可能性が高い。第2番はト短調。エクアドルの民族舞踊や五音音階を多用しつつも、印象派風や新古典主義風、更にジャズのテンションコードまで聞こえてくる盛り沢山の内容の作品である。狂詩曲らしく様々な主題が万華鏡のように現れ、強いて形式を記すなら前奏-A-B-C-D-E-F-A-コーダとなる。打楽器的な低音強打の前奏に続き、A: 流れるような速いダンサンテのリズムに乗って哀愁たっぷりの主題が奏され、両手オクターブffまでひとしきり盛り上がる。B: 太鼓の音のような低音オクターブと、笛の音のような高音の掛け合いが始まり、ペンタトニックのアルペジオが左手右手で多調になって奏されて不気味な雰囲気。C: Aの旋律の変形がテンポを落として気怠く奏される。D: 6/8拍子のゆったりとしたダンサンテ〜2/4拍子の激しいサンフアニート〜3オクターブ離れたユニゾンで神秘的に奏されるユンボ〜軽快で速いサンフアニート、の以上の成分が代わる代わる奏されて色彩的。(ユンボとはケチュア語で「魔術師」という意味で、先コロンブス期の先住民由来の神事などで奉納される舞踊音楽で、笛と太鼓により速いテンポで演奏される。)E: Aの変奏。F: 新たな旋律のダンサンテが中音域に呟くように現れ、両手オクターブで華やかに盛り上がり、また静かになる。最後はAが再現され、上行和音のコーダで派手に終わる。
1945-1956
- Mosaico de aires nativos 故郷の民謡のモザイク
全6曲から成る組曲。各曲はそれぞれ異なるエクアドルの民族舞踊のリズムで作曲されていて、フォルクローレそのものを聴いているような作品ばかりだが、いずれもサルガードが作ったオリジナルの旋律とのこと。和声付けはロマン派位の書法で聴き易く、エクアドル音楽独特の哀愁に満ち満ちている。なお、楽譜上は全6曲がアタッカで繋がっている。- Amanecer de trasnochada, Yaraví (1945) 徹夜後の夜明け、ヤラビ
ヤラビとはペルーやエクアドル、ボリビアで歌われる哀愁を帯びた叙情歌の一つで、短調で旋律はペンタトニック、ゆっくりとしたテンポである。起源は先コロンブス期の先住民の歌で、19世紀までは先住民の民謡全体を広くヤラビと呼んでいたが、その後はメスティーソ(先住民と白人の混血)たちの間でも歌い継がれてきている。ヘ短調、前奏-A-B-A-B-間奏-C-B-間奏-C-B-後奏の形式。前奏はレシタティーボ風で、ヘキサトニックのユニゾンが漂うように奏される。Aは旋律的短音階のもの悲しい旋律、BとCは一時変イ長調で高らかに旋律は奏されるが、間もなく悲しげなヘ短調に戻る。 - Romance nativo, Sanjuanito (1947) 故郷のロマンス、サンフアニート
ト短調、A-A-B-Bの形式。2拍子の軽快な踊りのリズムにのって、素朴な旋律が奏される。Aの後半では旋律のミが♮になる(ドリア旋法)のが独特の雰囲気でイイ。Bは変ホ長調やハ短調で、旋律は高音部になったりと興に乗って盛り上がる。 - La trilla, Danzante (1945) 脱穀、ダンサンテ
ダンサンテはエクアドル先住民由来の舞踊音楽の一つで、インカ帝国において太陽神インティ Inti を祭る宗教的儀式の「インティ・ライミ Inti Raymi」で踊り、演奏されたのが元であるとされている(女神であるパチャママ Pachamama に捧げる神事で踊られるとする文献もある)。太鼓のリズムにのってピングージョ pingullo と呼ばれる竹製の縦笛で旋律が奏されるらしい。ホ短調、A-B-A-B-Aの形式。6/8拍子♪♪♪♪♩のリズムの単調な旋律が繰り返されるのは、脱穀の仕事を描写しているのかもしれない。ドが♯のドリア旋法の旋律が哀愁漂う。Bはホ長調で、抒情的な雰囲気。 - Al que no alienta, copa!, Alza (1944) 元気のない人へ、乾杯!、アルサ
アルサとはエクアドルの民族舞踊の一つ。ホ長調、A-A'-B-A'-B-A'の形式。陽気な歌が歌われるような曲。Bはト長調になる。 - Criollita presuntuosa (1943) 自惚れたクリオージョの娘
ハ短調、A-A-B-C-Aの形式。優雅でちょっと気取った踊りのような雰囲気。BとCは変ニ長調になり、華やかになる。 - Nocturnal, Pasillo (1956) 夜に、パシージョ
パシージョはコロンビアやエクアドルの代表的な民族音楽の一つである。パシージョは19世紀初め頃に生まれ、語源は「小さなステップ」という意味で、元々は民族舞踊とその音楽であったが、19世紀末頃よりコロンビアではモラレス・ピノ、またエクアドルではシクスト・マリア・ドゥランといった作曲家達によりサロン音楽としても発展した。20世紀になると器楽曲であったパシージョに歌詞が付けられて歌われるようになり、一方踊られることは減り、現在はコロンビアやエクアドルに加えて、パナマ、コスタリカなどの中米でも民謡として歌われている。この曲はト短調、前奏-A-A-B-C-B-C-A-コーダの形式。哀愁たっぷりの美しい曲です。寂しげな4小節の前奏に引き続き、Aは切なく悩ましい旋律がゆったりとしたパシージョのリズム♪♪γ♪♩にのって奏される。Bは変ロ長調の旋律がオクターブで朗々と歌われ、Cは一時変ト長調になったりとロマンチック。最後に前奏が静かに再現されて終わる。
- Amanecer de trasnochada, Yaraví (1945) 徹夜後の夜明け、ヤラビ
1947
- Rapsodia ecuatoriana Nº 3 エクアドル狂詩曲第3番
ホ短調、大まかにA-B-C形式である。Aの冒頭は両手オクターブでダンサンテのリズムの重々しい旋律が現れる。この旋律はミ-ソ-ラ-シ-レの五音音階だが、所々でソ、ラ、レが♯になるのが趣き深い。旋律は左手伴奏を伴って繰り返され、アルペジオのカデンツァが挟まれる。次のBは嬰ハ短調になり、舞曲風の6/8拍子はユンボかアイレ・ティピコのリズムであろう。笛の音色のような軽快な旋律が奏され、ニ短調に転調すると両手オクターブ和音となり華やかに盛り上がる。技巧的なカデンツァで締めくくられると、最後のCはロ短調になり、2拍子のサンフアニートのリズムにのって賑やか盛り上がり曲は終わる。 - Estampas serraniegas, Serie de seis danzas ecuatorianas セラニエガ(山に住む人々)の印象、6つのエクアドルの舞曲集
- Ecos del Páramo, Yaraví パラモのこだま、ヤラビ
ニ短調、前奏-A-A'-間奏-A-A'-間奏-B-A'-間奏-B-A'-コーダの形式。Aはアンデスの山中で一人寂しく歌うようなヘキサトニックの旋律がしっとりと奏される。Bはト短調になり、高音部オクターブffでやや情熱的な旋律になる。 - Bajando de la feria, Danzante 縁日を下って、ダンサンテ
変ロ長調、前奏-A-間奏-A-B-B'-間奏-A-コーダの形式。太鼓を打つような左手伴奏にのって、ピングージョ pingullo(竹製の縦笛でエクアドルの民族楽器)が高音で吹いているようなペンタトニックの旋律が右手オクターブで奏される。Bは変ホ長調から頻繁に転調する。 - Noviazgo indígena, Sanjuanito 先住民のデート、サンフアニート
Noviazgoとは「結婚を前提のカップルの交際や関係」という意味ですが、そう書いては長ったらしいのでここでは「デート」と意訳しました。ロ短調、A-B-B-A-C-C-A-B-A形式。2拍子の軽快な踊りのリズムにのった曲で、素朴な感じのカップルの浮き浮きした気持ちが伝わってくるよう。Cはホ短調になり、左手アルペジオの伴奏が可憐な雰囲気。 - Arpas y guitarras, Albazo アルパとギター、アルバーソ
- Entre compadres, Aire típico 実父と代父の間で、アイレ・ティピコ
嬰へ短調、前奏-A-間奏-A-間奏-B-間奏-B形式。Aはほぼ4小節の同じ旋律が4回繰り返される。Bはイ長調になる。 - Amores furtivos, Pasillo 秘かな愛、パシージョ
ホ短調、前奏-A-A-間奏-B-Bの形式。陰うつな前奏に続き、Aの前半はゆったり、後半はAllegroにテンポを上げてパシージョのリズムにのった旋律が奏される。Bはト長調になり、小気味よいパシージョのリズムが続くが、最後はホ短調に戻り終わる。
- Ecos del Páramo, Yaraví パラモのこだま、ヤラビ
1948
- Variaciones en estilo folklórico "Tema nacional con variaciones" フォルクローレの様式による変奏曲「我が国の主題と変奏曲」
1949
- Marcha solemne 荘厳な行進曲
- Danza vernácula, Nº 4, Danza 土着の踊り第4番、ダンサ
194?-1950
- Primera sonata (Sonata dramática) ソナタ第1番(ドラマチックなソナタ)
- Lento - Allegro giusto
- Andante placido
- Allegro risoluto
- Suite ecuatoriana エクアドル組曲
1951
- Segunda sonata ソナタ第2番
- Allegro appassionato
- Larghetto
- Allegro con brio
195?
- Tres siluetas de mi raza, Música de ballet para piano 私の血筋の3つのシルエット、ピアノのためのバレー音楽
1957
- Seis fases rapsódicas sobre tres acordes de serie dodecafónica 十二音技法での3つの和音による6つのラプソディックな段階
- Allegro molto moderato
- Quasi adagio
- Allegro risoluto
- Andante quasi recitativo
- Lento misterioso
- Allegro brillante
1968
- Quadrivium クアドリビウム(四学科)
- Preludio 前奏曲
- Toccata トッカータ
- Coral コラール
- Fuga フーガ
1969
- Tercera sonata ソナタ第3番
- Moderato assai - Animato non troppo
- Andantino alla berceuse
- Final. Allegro energico
1977
- Suite para cuatro números 4つの番号のための組曲
- Pascua del sol, Preludio 太陽の祭、前奏曲
- La hilandera nativa, Immpromptu 先住民のはた織り、即興曲
- Aire típico アイレ・ティピコ
- Sanjuanito サンフアニート
Luis Humberto Salgadoのピアノ曲楽譜
Ediciones del Banco Central del Ecuador / Benjamin Carrion
 |
|
CONMUSICA (Corporación Musicológica Ecuatoriana)
- Enciclopedia de la Música Ecuatoriana (2002)
- El pintoresco Baile de las Cintas, sanjuanito
Archivo Equinoccial de la Música Ecuatoriana
- Cancionero Ecuador: Antología musical indispensable, Tomo I (2012)
- Arpas y guitarras, Albazo - No. 4 de la Serie de 6 danzas ecuatorianas: Estampas serraniegas
- Cancionero Ecuador: Antología musical indispensable, Tomo V (2013)
- Mosaico de aires nativos (suite)
- Sanjuanito futurista, Micro danza
FONSAL (Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito)
- Estampas serraniegas, Serie de seis danzas ecuatorianas
- Galería del folklore andino-ecuatoriano, Seis cuadros vernáculos
- Mosaico de aires nativos
- Rapsodia ecuatoriana No. 1 "En el templo del sol"
- Rapsodia ecuatoriana No. 2
- Rapsodia ecuatoriana No. 3
- Variaciones en estilo folklórico "Tema nacional con variaciones"
Luis Humberto Salgadoのピアノ曲CD
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Grandes temas de música ecuatoriana![]()
- Mosaico de Aires Nativos (Luis H. Salgado)
- Amanecer de trasnochada (yaraví)
- Romance nativo (sanjuanito)
- La trilla (danzante)
- Al que no alienta, copa (alza)
- Criollita presuntuosa (albazo)
- Nocturnal (pasillo)
- Sanjuanito futurista (sanjuanito) (Luis H. Salgado)
- Brindis al pasado (pasillo) (Luis H. Salgado)
- Fiesta (albazo) (Gerardo Guevara)
- Tonada (tonada) (Gerardo Guevara)
- El espantapájaros (pasillo) (Gerardo Guevara)
- Apamuy shungo (yumbo) (Gerardo Guevara)
- Pasional (pasillo) (Enrique Espín Yépez)
- Articulo 8 del Codigo Civil (pasillo) (Sixto María Durán)
- Sumac shungulla (fox trot) (Sixto María Durán)
- Brumas (pasillo) (Sixto María Durán)
- Souvenir (página de álbum) (Sixto María Durán)
- Lamparilla (pasillo) (Miguel A. Casares)
- Vasija de barro (danzante)
Guillermo Meza (pf), Marcelo Ortiz (pf)
Souvenir de l'Amérique du Sud![]()
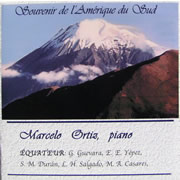 |
|
Marcelo Ortiz (pf)
1995年および2000年の録音。Marcelo Ortizはエクアドル出身のピアニストで、現在カナダに在住し活動中とのこと。
Piano Music by Ecuadorian Composers![]()
- Rapsodia No. 3 for Piano in E Minor (Luis Humberto Salgado)
- Suite for Piano, Mosaico de Aires Nativos: VI. Nocturnal (Pasillo) (Luis Humberto Salgado)
- Suite for Piano, Galeria del Folklore Andino-Ecuatoriano: III. Brindis por la Peaña (Alza) (Luis Humberto Salgado)
- Canción triste for Piano in G Minor (Corsino Durán)
- Tristes alegrías for Piano in D Minor (Yaraví) (Corsino Durán)
- Fiesta for Piano (Aire típico) (Gerardo Guevara)
- Albazo for Piano (Gerardo Guevara)
- Pasillo for Piano in D Minor (Gerardo Guevara)
- Marcha funebre for Piano in E Minor (Claudio Aizaga)
- Acuarela for Piano in A Minor (Claudio Aizaga)
- Pasillo for Piano in B Minor (Claudio Aizaga)
- Capillana for Piano in G Minor (Danza nativa aire de San Juan) (Juan Pablo Muñoz Sanz)
- Danza Inkasca for Piano in A Minor (Juan Pablo Muñoz Sanz)
- Vision for Piano in G Minor (Pasillo) (Juan Pablo Muñoz Sanz)
- El Espantapájaros for Piano in E Minor (Pasillo) (Gerardo Guevara)
Alex Alarcón Fabre (pf)
2016年のリリース。
Luis Humberto Salgadoに関する参考文献
- Isadora Ponce Berrú. Expresión estética y mestizaje en la obra de Luis Humberto Salgado. Disertación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2014.
- Lucas Santiago Bravo Lituma. Análisis formal de tres rapsodias para piano de Luis Humberto Salgado. Tesis, Universidad de Cuenca 2016.