Kilza Settiのページ
Kilza Settiについて
キウザ・セッチ・ジ・カストロ・リマ Kilza Setti de Castro Lima は1932年1月26日、サンパウロに生まれた。彼女の父は音楽好きで、家にはオペラのレコードが沢山あり、それらを幼い頃から聴いていたとのことである。5歳でピアノと歌を母から習い始め、8歳頃からフルクトゥオーゾ・ヴィアナらにピアノを師事した。
その後、サンパウロ演劇音楽院でピアノとクラシックバレエを学び、1953年に卒業するとピアニストとして活動した。また1954年には作曲家のカマルゴ・グァルニエリの弟子になるための試験に自作曲《青い湖の精 A mãe d'água do lago azul》を提出して認められ、同年から1960年までカマルゴ・グァルニエリに作曲を師事した。セッチが作曲した混声合唱曲《2つのアカペラ混声合唱曲 Dois corais a capella mistos》(1958) は1958年リコルディ作曲コンクールで佳作に選ばれ、混声合唱曲《セイレーンの王のバラード Balada do rei das sereias》(1958) は1959年サンパウロ州作曲コンクールで2等賞を得た。更に歌曲《愛されたある男のための大きな愛のトローヴァ Trova de muito amor para um amado senhor》は1961年にはラジオMEC主催の「ブラジル歌曲コンクール」で1等賞を得た。民族音楽の研究に興味を持っていた彼女は、1959年頃よりバイーア州サルヴァドールに赴いてカンドンブレの音楽を採譜したり、サンパウロ州のサンバ・ジ・ホーダの調査を行った。
セッチは1961年にLuiz Antônio de Castro Limaと結婚してリオデジャネイロに移り住むと、ゲーハ=ペイシェに管弦楽法を師事した。1966年には奨学金を得て、ブエノスアイレスのトルクァト・ディ・テラ研究所内のラテンアメリカ音楽高等研究センターに留学し、電子音楽を学んた。1970年にはグッゲンハイム奨学金を得てポルトガルのリスボンに数ヶ月滞在し、ミシェル・ジャコメッティ Michel Giacometti やフェルナンド・ロペス=グラサ Fernando Lopes-Graça に師事して民族音楽学を研究し、ポルトガルの地方で口頭伝承されている音楽の調査を行った。
1978年から1982年にかけて、サンパウロ州北部の大西洋沿岸地方に住むカイサラス Caiçaras と呼ばれる人々の音楽を調査・研究し、1985年に『沿岸地方の歌におけるウバトゥバ:サンパウロ州カイサラとその地の音楽の研究 Ubatuba nos cantos das praias: estudo do caiçara paulista e de sua produção musical』という本を上梓してサンパウロ大学より博士号を授与された。また1994年からはブラジル北部の先住民チンビラ族の音楽を収集し、2004年に3枚組CD『アムジェキンーチンビラ族の音楽 Amjëkin - Música dos Povos Timbira』を編集した。2022の時点でも彼女は作曲を続けている。
キウザ・セッチは百曲以上の作品を作っている。彼女の作品は歌曲や合唱曲が多く、《カンチーガ Cantiga》(1960)、《星 A estrela》(1961)、《愛されたある男のための大きな愛のトローヴァ》(1961)、《カルロス・ドゥルモン・ジ・アンドラージの3つの歌曲 Três canções de Carlos Drummond de Andrade》(2002)(いずれもピアノ伴奏)などが代表作である。また、独唱・混声合唱・10弦ギター・太鼓のための《ミサ・カイサラ Missa Caiçara》(1990) と、声・フルート・ピアノ・クラヴァス・ムバラカのための《Ore ru Nhamandu Etê Tenondeguá - preces Mbyá-guarani》(1993) は民族音楽研究の影響を示すような作品で、特に後者は前衛音楽のようでもあり五線譜の世界から離れた先住民の音楽そのままのようにも聴こえる作品である。
キウザ・セッチのピアノ曲は和音を華麗に鳴らすような曲は少なく、二声〜四声のポリフォニックな曲が多い。またブラジル北東部(ノルデスチ)の民謡で多用される教会旋法、即ちリディア旋法とミクソリディア旋法およびその混合を用いた曲が多い。ポリフォニーもノルデスチ音楽の教会旋法も極めてブラジル的であり、彼女のピアノ曲はちょっと取っ付き難い響きではあるがブラジル民族主義に満ちた作品揃いである。
Kilza Settiのピアノ曲リストとその解説
1953
- A mãe d'água do lago azul 青い湖の精
カマルゴ・グァルニエリの弟子になるための試験に提出された作品。題名からも推察できるが印象主義的な曲で、また調性が定まらない響など、キウザ・セッチが既に高度な作曲技法を身につけていたことを示している曲である。A-B-A'-B'-A"-コーダの形式。Aは上下するアルペジオが半音階や全音音階混じりで移ろうように変化していく。Bはアルペジオの上で呟くようなハ長調の旋律が現れるが、旋律がシンコペーション混じりなのがブラジル(特にサンパウロ州あたりの)民謡を連想させる。10小節のA'を経て、B'は民謡風の旋律がト長調で再現される。コーダは魔法がかかったような急速なアルペジオが奏され、最後は水の精が湖の底に消えていくような重々しい両手オクターブで終わる。
1955
- Seis variações para piano (sobre um tema popular) ピアノのための6つの変奏曲(民謡の主題による)
- Tema
- 1.ª variação: Moderato
- 2.ª variação: Saltitante
- 3.ª variação: Bem triste!
- 4.ª variação: Allegro
- 5.ª variação: Lento
- 6.ª variação: Vivo
- Toada トアーダ
トアーダとは主にブラジルの中部〜南部で歌われる民謡の一つのジャンルで、一般的に単純なメロディーに自然や故郷を歌う哀愁のこもった歌である。ゆっくりとした気怠いシンコペーションのリズムにのって息の長い旋律が奏され、中音部内声に絶えず対旋律がまとわる。強いて言えばへ長調だが、しばしばシが♮(ファのリディア旋法)に、ミが♭(ファのミクソリディア旋法)になりノルデスチの音楽のようにも聴こえる。
1958
- Seis peças em clave de Sol ト音記号による6つの小品
子どものために作られたような雰囲気の曲で、楽譜は第6曲〈ルンドゥ〉を除いて両手ともト音記号、控えめな重音の伴奏に単音の旋律と音数は少ないが、半音階を用いた微妙な和音の移ろいが何とも深い味わいの小品集である。1979年に第1番、第3番のみが《Duas peças para piano》の題名で出版された。
- Roda ホーダ
ト長調、A-A'形式。シンコペーションの左手伴奏にのって、右手に童歌を思わせる素朴な旋律がソのミクソリディア旋法で奏される。A'は左手伴奏の和音が半音階で移動して色彩的な響きだ。 - Acalanto 子守歌
一応イ長調の伴奏にのって、ホ長調ともラのリディア旋法とも聴こえる旋律が静かに奏される。 - Tanguinho タンギーニョ
ニ短調、A-B-A'形式。シンコペーションの左手伴奏にのって、右手に哀愁漂う旋律が奏される。Bでは旋律は左手になり陰うつに奏される。 - Valsa ヴァルサ
イ短調、A-B-A形式。寂しげな旋律が奏される。Bでは旋律は左手になる。 - Modinha モジーニャ
A-A'形式。旋律と対旋律の二声が対話するように奏される。始めはイ短調で、途中からニ短調になる。 - Lundu ルンドゥ
ホ長調、A-B-A-B'形式。威勢の良い左手リズムにのって、右手16分音符スタッカートの旋律が無窮動で奏される。
- Roda ホーダ
- Primeira valsa ヴァルサ第1番
曲全体が三声〜四声の複雑なポリフォニーで書かれ、左手・右手共にオクターブを越える音程が頻繁に現れるので演奏の関係で重たい響きになる、この頃セッチが師事していたカマルゴ・グァルニエリの影響の強い作品である。イ短調、A-B-C-B'-A-コーダの形式。Aは右手に哀愁たっぷりのヴァルサ・ブラジレイラらしい旋律が奏され、その下で対旋律が絡み合う。Bは旋律が左手〜右手と掛け合いで現れる。Cの旋律はBに似ているが、右手旋律はオクターブ、左手伴奏は分厚い和音で情熱的な響き。 - 8 variações para piano (sôbre um tema popular "Onde vais, Helena") ピアノのための8つの変奏曲(民謡「どこへ行くの、エレナ」の主題による)
- Tema
- 1.ª variação: Triste
- 2.ª variação: Com recitativo, Com muita expressão
- 3.ª variação: Alegre e bem ritmado
- 4.ª variação: Com movimento
- 5.ª variação: Calmo e contemplativo
- 6.ª variação: Com alegria
- 7.ª variação: Cômodo
- 8.ª variação: Agitato
1959
- Interlúdio (à memória de Joaquim Carlos Nobre) 間奏曲(ジョアキン・カルロス・ノブリの思い出に)
A-B-A'形式。静かなシンコペーションの左手伴奏にのって、半音階混じりの旋律が語るように奏される。 - Cinco peças sobre Mucama Bonita (Canto popular infantil) ムカマ・ボニータによる5つの作品(わらべ歌)
1960年に催されたサンパウロ州作曲コンクールで佳作となった作品。原曲は1955年作曲の《ピアノのための6つの変奏曲(民謡の主題による)》で、おそらくコンクール応募のために改訂したものと思われる。改訂したのは冒頭の主題に左手対旋律混じりの和音を加えたことと、各変奏では若干の音の変更をしたこと以外に第3変奏と第4変奏の順を逆にしたこと、原曲の第5変奏を省き、原曲の第6変奏を第5変奏として、また最後の主題の回想を省いたことである。
1960
- Baião À moda do Luiz Gonzaga ルイス・ゴンザーガ風のバイアォン
ルイス・ゴンザーガ Luiz Gonzaga (1912-1989) はブラジルの作曲家・歌手・アコーディオン奏者。彼はブラジル北東部(ノルデスチ)の音楽による歌を多数自作自演し、特にそれまであまり知られていなかったバイアォンを世に広め「バイアォンの王様 O Rei do Baião」と呼ばれた伝説的な音楽家である。A-A'-A"形式。左手にオスティナートで奏されるバイアォンのリズムにのって、右手高音部にスタッカート混じりの跳ねるような旋律が変奏されつつ繰り返される。右手旋律はミのミクソリディア旋法で、一方左手和音は半音階進行しつつ移動し、ハ長調のI度-V度を繰り返すところは多調の響きで面白い。 - Suíte para piano ピアノのための組曲
- Ciranda シランダ
左手は概ねニ長調で3-3-2のリズムの伴奏が奏され、右手は時々ドが♮(レのミクソリディア旋法)になる16分音符が跳ねるように奏されて子どもが遊んでいるような雰囲気。 - Samba-lenço サンバ・レンソ
サンバ・レンソとはサンバの前身となる踊りの一つ。19世紀またはそれ以前より主にブラジルの黒人達が太鼓の伴奏で歌い踊っていたもので、レンソ lenço(ポルトガル語でスカーフのこと)を振りながら踊ることが多かったらしい。一応ハ長調で、左手オスティナートの伴奏にのって、素朴な旋律が時々ファが♯(ドのリディア旋法)に、シが♭(ドのミクソリディア旋法)になって奏される。最後に旋律が繰り返されるときは五音音階に変奏される。 - Valsa ヴァルサ
イ短調、A-B-A'形式。左手伴奏にのって、右手に哀愁漂う旋律が奏される。曲全体の哀調や、左手伴奏が時々バイシャリア(ショーロで低弦ギターが主旋律の合間に音階などの短い対旋律を合いの手のように入れること)を思わせる音階を奏でるところなど、ヴァルサ・ブラジレイラの雰囲気たっぷりである。 - Lundu ルンドゥ
ト長調、A-B-A'形式。快活な左手リズムの上で右手16分音符が優美に奏され、踊りの光景のよう。Bでは左手に歌うような旋律が現れる。 - Catira カチーラ
カチーラ catira(またはカテレテ cateretê)はブラジルの民族舞踊で、ギターを伴奏にして(歌が入ることもある)、手を叩き、足を鳴らしながら二列になって踊る。トゥピ族あたりのブラジル先住民の踊りが起源か、またはアフリカからの奴隷やヨーロッパからの移民の舞踊の混合とも言われており、現在はサンパウロ州やミナスジェライス州、マットグロッソ州など主に内陸部の地方に残っている。ニ長調、A-B-A-B-C-C形式。Aは前奏のような静かな部分で、楽譜に "Com nostalgia" と記され、十度重音のモチーフと中音部密集和音のモチーフが交互に現れて一種のコール・アンド・レスポンスのよう(セッチの師のカマルゴ・グァルニエリがこの手法をピアノ曲《ポンテイオ45番》(1959) などで用いている)。Bは一転して速いテンポのリズムが現れ、Cではそのリズムにのって右手に陽気な旋律がレのミクソリディア旋法で奏される。
- Ciranda シランダ
1969
- Duas peças 2つの作品
ブラジルでは何人もの作曲家達が、アフリカ由来のブラジルの民間信仰カンドンブレを題材としたピアノ曲を作っているが、セッチは自らカンドンブレが盛んなブラジル北東部のバイーア州に赴いてカンドンブレの音楽を研究しており、この組曲の主題も彼女自身が現地で採譜した音楽を元にしているらしい。- Canto de Yemanjá イエマンジャの歌
イエマンジャとはカンドンブレの神々の一つで、海の女神である。A-A'-コーダの形式。Aのゆっくりと呟くような右手旋律は一応ト短調だが、左手伴奏和音は無調に近く神秘的な響きである。A'は左手に旋律、右手に伴奏と交替する。 - Canto de Erê エレの歌
カンドンブレではエレ(エシュとも呼ばれる)は人間と神を繋ぐメッセンジャーを担う神格で、悪戯者でもある。20秒程の短い曲で、右手に一応ニ長調の快活な旋律が奏され、左手はファ♯-ソの重音連打が悪戯っぽく鳴る。
- Canto de Yemanjá イエマンジャの歌
1987
- Multisarabanda ムルチサラバンダ
カマルゴ・グァルニエリ生誕80周年を記念して作曲された。自筆譜には「サラバンド:ドビュッシーについての分析において、また私の師で友人であるカマルゴ・グァルニエリを讃えて。サラバンド:チネッチの演奏で聴いた《ピアノのために》の素晴らしい音の思い出に。」と記されている(ジルベルト・チネッチ Gilberto Tinetti はブラジルのピアニスト)。強いて言えばハ長調、A-B-A'形式。Aはドビュッシーの《ピアノのために Pour le piano》の第2曲〈サラバンド sarabande〉の冒頭8小節と同じリズムの似たモチーフが両手ユニゾンで奏され、次に落ち着いた旋律が現れ、長九の和音や属七の和音の平行移動がドビュッシーを思わせる響きである。Bは左手は8/9拍子、右手は3/4拍子のポリリズムになり、左手は2-2-2-3のリズムの音形が伴奏のように繰り返され、右手は3拍子の息の長い旋律が奏される(Bの部分の楽譜の冒頭には「少し生き生きと(♩.=69 aprox.)、しかしサラバンドの性格を保ちながら。左手はアクサクのリズムを連想して。」と記されている)。
2005
- XIV Estação da Via Sacra "Jesus é sepultado" 十字架の道行きの第14留「イエスは埋葬される」
「十字架の道行き」とはカトリック教会の信心業で、イエス・キリストの死刑の宣告から十字架上で亡くなり埋葬されるまでが14の留(復活の場面を含めると15留)に分かれていて、カトリック教会では14枚の絵または彫刻が架けられている。ブラジルの作曲家Sergio Chneeが「十字架の道行き」の各留を印象としたピアノ曲の作曲を12人のブラジルの作曲家に委嘱し(Sergio Chnee自身も3曲作り)、集められた15曲は2013年にCD「Via Sacra」としてリリースされた。セッチが作曲したのは〈第14留「イエスは埋葬される」〉である。セッチのピアノ曲の中でも最も前衛的と言えそうな作品で、無調で、楽譜には小節線が全くない。低音に葬送行進曲のような短二度混じりの4分音符が重々しく奏され、それにのって呻くようなモチーフが変奏されつつ繰り返し現れる。
2022 (1942年に作曲、作曲者により演奏されたが、2022年に楽譜に記された)
- Memórias de infância 子ども時代の思い出
この作品はキウザ・セッチがまだ10歳の1942年に作曲し、作曲者により演奏されたが、2023年開催の「第30回イトゥイウタバ・ピアノコンクール」の課題曲とするために楽譜が記された(詳しくは後述)。- I. Valsinha "Beija-flor" (versão reduzida) ヴァルシーニャ「ハチドリ」(簡易版)
ハ長調、A-B-A形式。セッチが10歳の作品らしい、左手ブンチャッチャッの伴奏にのって右手に旋律が奏される。曲の大部分でそれぞれのフレーズが5小節単位なのがちょっと変わっている。 - I. Valsinha "Beija-flor" (versão ampliada) ヴァルシーニャ「ハチドリ」(拡大版)
「簡易版」の変奏のような曲であるが、半音階の使い方が10歳の作品っぽくない気がする。ハ長調、A-B-A'形式。簡易版と比べて、伴奏和音が半音階進行する前奏が加わり、右手旋律が始まると左手伴奏はしばしば半音階の対旋律を奏でたりする。 - II. O dançar flamenco フラメンコを踊る人
A-B-C-D-B'-A'-B"形式。概ねミの旋法(フリギア旋法に似ているがソが♯になったりならなかったりする)で次々と主題が現れる。Cは楽譜にカンテ・ホンドと記され、朗唱するような旋律とギターを思わせる和音の平行移動が奏される。
- I. Valsinha "Beija-flor" (versão reduzida) ヴァルシーニャ「ハチドリ」(簡易版)
2022
- Mazurquinha 小さなマズルカ
ミナスジェライス州イトゥイウタバで毎年催されている「イトゥイウタバ・ピアノコンクール」では、毎回一人の作曲家のピアノ曲を課題曲として取り上げている。2023年の第30回コンクールではキウザ・セッチが取り上げられることになった。そこで2022年に彼女はコンクールの課題曲として《Mazurquinha》、《Samba manhoso》、《Tristonha moda》、《Sambalelê no azul》の4曲を新たに作曲し、セッチの既存作品と合わせて各年齢別の10曲のピアノ独奏曲と、1つのピアノ連弾用組曲が課題曲となった(2023年の課題曲のウェブサイトはここです)。ハ長調。二声で書かれていて、それぞれが半音階進行を多く含むので、ちょっとひねくれた響きに聴こえる。3拍子ではあるが曲中に付点リズムは全く現れず、あまりマズルカのような雰囲気はしないんだけど。 - Samba manhoso 器用なサンバ
ハ長調。二人の楽器奏者が即興で掛け合うような二声の部分と、二人で合わせて軽快なリズムを刻むような部分が交互に現れ、いずれもシンコペーションが効いていて楽しい雰囲気だ。 - Tristonha moda 悲しげなモーダ
二声または三声のポリフォニーがゆっくりと奏される部分と、楽譜に「ラスゲアードのように como rasgueado de cordas」と記された密集和音の連打の部分が交互に奏される(ラスゲアードとはギター奏法の一つで、左手で和音を押さえて、右手の指の爪で上から下に掻き鳴らすように弾く奏法のこと)。一部イ短調が感じられるところがあるが、大体は無調で、悲しげと言うより放心したような響きの曲。 - Sambalelê no azul ブルースでサンバレレ
ほぼブルー・ノート・スケールで作られた曲。左手は伴奏だったり対旋律になったりする。
Kilza Settiのピアノ曲楽譜
Escola de Música da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)
- Cadernos musicais brasileiros, vol. 15: O piano de Kilza Setti
- A mãe d'água do lago azul
- Toada
- Seis variações para piano (sobre um tema popular)
- Seis peças em clave de Sol
- Primeira valsa
- Oito variações para piano (sôbre um tema popular "Onde vais, Helena")
- Interlúdio (à memória de Joaquim Carlos Nobre)
- Cinco peças sobre Mucama Bonita (canto popular infantil)
- Baião À moda do Luiz Gonzaga
- Suíte para piano - cinco danças
- Duas peças
- Multisarabanda
- Via Sacra XIV - Estação "Jesus é sepultado"
- Memórias de infância
- Mazurquinha
- Samba manhoso
- Tristonha moda
- Sambalelê no azul
- Seis peças em clave de Sol de Kilza Setti, nas leituras para piano a 4 mãos
Ricordi Brasileira S.A.
 |
|
Editora Novas Metas
 |
|
斜字は絶版と思われる楽譜
Kilza Settiのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
O piano de Kilza Setti![]()
Selo Minas de Som - Escola de Música da UFMG
- A mãe d'água do Lago Azul
- Toada
- Seis variações para piano (sobre um tema popular)
- Seis peças em clave de Sol
- Primeira valsa
- Interlúdio (à memória de Joaquim Carlos Nobre)
- Cinco peças sobre Mucama bonita (canto popular infantil)
- Baião À moda de Luiz Gonzaga
- Suíte para piano
- Duas peças (Canto de Yemanjá / Canto de Erê)
- Multisarabanda
- XIV Estação da Via Sacra "Jesus é sepultado"
- Memórias de infância
- Mazurquinha
- Samba manhoso
- Tristonha moda
- Sambalêlê no azul
- Seis peças em clave de Sol (4 mãos)
- Roda - Arr. Denise Garcia
- Ninar - Arr. Guilherme Viégas
- Tanguinho - Arr. Pedro Pascoali
- Valsa - Arr. Leonardo Paz
- Modinha - Arr. Francisco Zmekhol
- Lundu - Arr. Vitor Alves
Ana Cláudia de Assis (pf), Daniela Carrijo (pf), Araceli Chacon (pf), Adriano Lopes (pf), Denise Martins (pf), Arthur Versiani de Azevedo (pf)
2023年の録音・リリース。
Brasileira: Piano Music by Brazilian Women![]()
![]()
Centaur Records, CRC 2680
- Prelúdio (Maria Helena Rosas Fernandez)
- Valsa (Maria Helena Rosas Fernandez)
- Cinco Peças sobre Mucama Bonita (Kilza Setti)
- Valsa-Chôro No. 2 (Adelaide Pereira da Silva)
- Suíte No. 2 (Adelaide Pereira da Silva)
- Corta-Jaca (Brazilian Tango) (Chiquinha Gonzaga)
- Meditação (Chiquinha Gonzaga)
- Atraente (Polka) (Chiquinha Gonzaga)
- Cenas Brasileiras (Nininha Gregori)
- Arabesco (Maria Luiza Priolli)
- Lundu Carioca (Maria Luiza Priolli)
- Suite Nordestina (Clarisse Leite)
- Samba Sertanejo (Branca Bilhar)
Luciana Soares (pf)
2003年の録音。
Encontros com a Música de São Paulo![]()
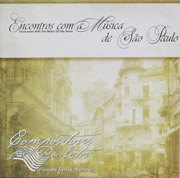 |
|
Sylvia Maltese (pf)
Mulheres Compositoras França - Brasil![]()
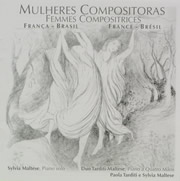 |
Piano solo
Piano a quatro mãos
|
Sylvia Maltese (pf), Paola Tarditi (pf)
2009年の録音。
Via Sacra - Piano Brasileiro Contemporâneo IV![]()
- 1ª Estação, Jesus é condenado à morte (Sergio Chnee) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 2ª Estação, Jesus carrega a pesada cruz (Diogo Lefèvre) (Rogério Zaghi, pf)
- 3ª Estação, Jesus cai pela primeira vez (Rodolfo Coelho de Souza) (Rogério Zaghi, pf)
- 4ª Estação, Jesus encontra a sua Mãe Santíssima - meditação para piano (Almeida Prado) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 5ª Estação, Simão Cirineu ajuda a Jesus - A segunda queda de Jesus (Edmundo Villani-Côrtes) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 6ª Estação, Verônica limpa o rosto de Cristo (Amaral Vieira) (Rogério Zaghi, pf)
- 7ª Estação, Jesus cai pela segunda vez - La seconde chute (Jorge Antunes) (Rogério Zaghi, pf)
- 8ª Estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém - Antifonias (Eduardo Guimarães Álvares) (Rogério Zaghi, pf)
- 9ª Estação, Jesus cai pela terceira vez (Sergio Chnee) (André Pédico, pf)
- 10ª Estação, Jesus é despojado de suas vestes - Sem título, Só-nus (Silvia de Lucca) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 11ª Estação, Jesus é pregado na cruz - Crucifixus (Mario Ficarelli) (Rogério Zaghi, pf)
- 12ª Estação, Jesus morre na cruz (Achille Picchi) (Rogério Zaghi, pf)
- 13ª Estação, Jesus é entregue à sua santa Mãe (Ricardo Tacuchian) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 14ª Estação, Jesus é sepultado (Kilza Setti) (Rogério Zaghi, pf)
- 15ª Estação, Ressurreição (Sergio Chnee) (Paulo Gazzaneo, pf)
El Fin Del Silencio: Latin American Women Composers![]()
![]()
Pixaudio
- Recuerdos de mi tierra: I. Evocacion criolla (Lía Cimaglia)
- Nocturno, op. 13 (Cecilia Arizti)
- Valsa-Choro N. 1 (Adelaide Pereira da Silva)
- Dos trozos: I. El afilador, II. Toque de campanas (María Luisa Sepúlveda)
- Jeugos para Diana (Alicia Terzian)
- Preludios: I. Niebla, II. Benteveo (Lita Spena)
- Preludes: I. Calme et expressif (Ruhig) (Carmela Mackenna)
- Evoluciones: I. Allegro, IV. Moderato, Vals (Rocío Sanz Quirós)
- Siete piezas latinas: Días de lluvia (Graciela Agudelo)
- Recuerdo de Los Andes, Mazurca (Modesta Sanginés)
- Trujillo mío (Rosa Mercedes Ayarza)
- Scriabiniana: II. Lento (Rosa Guraieb)
- Escena de niños (María Teresa Prieto)
- Cinco peças sobre Mucama Bonita (Kilza Setti)
- De mi infancia: I. Cajita de música, II. El arrorró de la muñeca, III. Micifuz (Isabel Aretz)
- Noche de luna en Altamira, Valse nocturno (María Luisa Escobar)
- Le sommeil de l'enfant, op. 35. Berceuse (Teresa Carreño)
- Trois morceaux pour piano: I. Tristesse, III. Petite berceuse (Teresa Carreño-Tagliapietra)
- Feche os olhinhos, que o soninho vem... (Berceuse) (Clarisse Leite)
- Variaciones para piano (Modesta Bor)
- Saudade (Chiquinha Gonzaga)
Antonio Oyarzábal (pf)
2023年のリリース。
Músicas e músicos de São Paulo (LP)
Museu da Imagem e do Som de São Paulo, MIS 002
LP 2
- Chora minha terra (Dinorá de Carvalho)*
- Pássaro colorido (Dinorá de Carvalho)**
- Valsa da primavera (Dinorá de Carvalho)**
- Lundu, No.3 das 9 Danças brasileiras (Ascendino Theodoro Nogueira)**
- Serenidade (Souza Lima)***
- Oito variações sobre o tema "Onde vais Helena" (Kilza Setti)****
- Festa na roça (Sérgio de Vasconcellos-Corrêa)*****
- Dança charrua n.º 1 (Breno Blauth)*****
- Dança charrua n.º 2 (Breno Blauth)****
- Variações sobre um tema de cana fita (Sérgio de Vasconcellos-Corrêa)****
- Tocatina (Sérgio de Vasconcellos-Corrêa)****
- Jogos selvagens (Amaral Vieira)******
Ester Fuerte Wajman (pf)*, Eny da Rocha (pf)**, Yara Ferraz (pf)***, Attilio Mastrogiovanni (pf)****, Eudóxia de Barros (pf)*****, Amaral Vieira (pf)******
1978年の録音、1979年リリースのLP。
Kilza Settiに関する参考文献
- Sandra Regina Zumpano Rodrigues. Reflexões interpretativas: canções para canto e piano de Kilza Setti. Dissertação, Universidade Federal de Uberlândia 2011.
- Valéria Peixoto (Organização). Kilza Setti: catálogo de obras. Academia Brasileira de Música 2025.