Waldemar de Almeidaのページ
Waldemar de Almeidaについて
ワウデマール・ジ・アウメイダ Waldemar de Almeida は1904年8月24日にリオグランジ・ド・ノルテ州マカウ Macau で生まれた。一家は彼の生後6ヶ月で州都ナタウに引っ越した。彼は子どもの頃からピアノを習い始めた。9歳の時にナタウに映画館シネマ・ロイヤルが開館すると、そこでドアマンとして働いた。当時の映画は無声映画(サイレント映画)で、映画の場面に合わせた音楽をピアニストが弾いていた。ある日、映画館お抱えのピアニストが上映時間になっても来なかった。そこで映画館の支配人は少年ワウデマールに「映画に合わせてピアノを弾きなさい。できる限り演奏して、休憩時間以外はピアノを止めないように。」と指示した所、ワウデマールは2時間ピアノを弾ききり、それで彼は映画館でピアノを弾くようになったとのことである。10代の時サンパウロに住んだ時期があったが、やがてナタウに戻り、当地でピアノに加えヴァイオリンやチェロも習った。1921年にはナタウの劇場での演奏会でのピアノ伴奏をした記録が残っている。
1921年10月、リオデジャネイロに移り、国立音楽学校 Instituto Nacional de Música に入学し学ぶも1923年に中退した。1923年末から1924年にかけて父と主にドイツに滞在し、彼はベルリンでピアノや和声学を学んだ。また1924年のバイロイト音楽祭を鑑賞している。帰国後はナタウでリサイタルをする機会もあった。1926年と1927年の二度に亘ってはフランスのパリに渡航し、ペルルミュテールにピアノを師事した。パリではヴィラ=ロボスにも会い、ヴィラ=ロボスの音楽がパリで大人気であることは我々の誇りであると記している。ブラジル帰国後は、1929年にリオグランジ・ド・ノルテ州政府庁舎でソロリサイタルを催すなどピアニストとして活躍し、また1929年に「Curso Waldemar de Almeida」と名付けた自らのピアノ教室を開講した。ピアノ教室の発表会は1930年から1951年まで計102回を数えている。彼の従弟で、かつピアノの弟子であった当時9歳のオリアンネ(オリアノ)・ジ・アウメイダが1931年に父を失うと、オリアンネの後見人となって世話をした。
1932年、Hylda Rosemary Wicksと結婚。5人の子どもをもうけ、中でも長男のCussy de Almeidaはヴァイオリニストに、二男のWaldemar de Almeida Juniorはチェリストになった。
1933年にリオグランジ・ド・ノルテ州立音楽学校がナタウに創立され、ワウデマール・ジ・アウメイダは校長に就任。「Curso Waldemar de Almeida」でのピアノレッスンも並行して続け、ピアノ指導者として活発に活動した。
彼はブラジル統合主義運動の政治家としても活動し、州議会議員の選挙に立候補するも落選したが、1935年には統合主義党のリオグランジ・ド・ノルテ州代表に就任している。
1949年、弟子のオリアノ・ジ・アウメイダがワルシャワで開かれた第4回ショパン国際ピアノコンクールに出場し、「Distinction」の成績を得た。
1950年、ワウデマール・ジ・アウメイダはリオグランジ・ド・ノルテ州立音楽学校を辞任し、一家はペルナンブーコ州レシフェへ移住した。この年、州立音楽学校への補助金が大幅に削減されたことが影響しているのでは、と彼の息子達は後に回想を語っているが、転居のはっきりした理由は不明である。レシフェとナタウは約250km離れているが、彼は頻繁にナタウとを行き来して両方の都市でピアノを教え続けた。
1954年にポーランドの有名なピアニスト、ハリーナ・チェルニー=ステファンスカがレシフェを訪問しリサイタルを催した。彼女はワウデマール・ジ・アウメイダの弟子であるエリアナ・カルダス Elyanna Caldas (1936-2025) の演奏を聴き、翌年に開催される第5回ショパン国際ピアノコンクールに出場するようカルダスに勧めた。更にコンクール主催者からはワウデマール・ジ・アウメイダにオブザーバーとして来場するよう招待状が来た。しかし、カルダスにはポーランドへの渡航費が無く援助も得られなかった。そこでカルダスのためにワウデマール・ジ・アウメイダは自分の所有する土地を売却して費用を捻出し、1955年2月にワウデマール・ジ・アウメイダとカルダスはワルシャワに渡航。カルダスはブラジル人唯一のコンテスタントとして出場したが一次予選で敗退した。
1961年には、彼の弟子16人の演奏による、全曲ワウデマール・ジ・アウメイダのピアノ曲による演奏会がナタウで催された。
1962年、リオグランジ・ド・ノルテ連邦大学に音楽学部が設立され、ワウデマール・ジ・アウメイダは初代学部長に就任した。
1967年、全ての官職を退任。1975年1月に妻と共にサンパウロに移り住んだ。彼は元々肺気腫を患っていたが、同年5月に心筋梗塞を発症し入院の末、5月25日に亡くなった。
ワウデマール・ジ・アウメイダの作品は殆どがピアノ曲である。数曲の宗教曲と約20曲の歌曲を作曲したが、それらの中で楽譜が現存するのは4曲のみである。
Waldemar de Almeidaのピアノ曲リストとその解説
斜字は出版がなく、かつ手稿譜が現存せず、どんな曲だか不明な作品です。
1920年頃
- Sonho de anjo 天使の夢
1921
- Flôr de Belém, Valsa ベレンの花
1921年から1922年にかけてワウデマール・ジ・アウメイダの3曲のピアノ曲が「Walmeida」のペンネームで出版されている。これはその1曲で、パラー州の州都ベレンに住んでいる叔父母のRaymundo de Almeida、Oneglia Correia de Almeida夫妻(オリアノ・ジ・アウメイダの両親)に献呈されていて、「ベレンの花」とは叔母を指していると思われる。ニ短調、A-B-A-C-A形式。Aはため息をつくような前打音混じりの旋律と、音階で進行するベースはヴァルサ・ブラジレイラ(ブラジル風ワルツ)らしい雰囲気で哀愁たっぷり。Bはヘ長調になる。Cはニ長調になり、オクターブ和音で奏される旋律が華やか。
1922
- Flôr da tarde, Valsa lenta op. 2 午後の花、ゆっくりとしたワルツ、作品2
- Flôr das ruínas, Valsa lenta op. 3 廃墟の花、ゆっくりとしたワルツ、作品3
1924?
- Mazurca マズルカ
- Prelúdio n. 1 前奏曲第1番
1936
- Paisagens de leque 扇子の風景画
扇子に描かれた色々な絵の場面を音楽にしたのであろうか。ワウデマール・ジ・アウメイダの詩的想像力の豊かさを感じさせる曲集である。出版譜の表紙には全8曲の題名が記されているが、実際には第3番と第4番は出版されなかった。- Valsa nobre 高雅なワルツ
楽譜の冒頭には以下の解説が記されている。『この風景画は、ルイ15世の豪華な舞踏会におけるヴェルサイユ宮殿の壮麗さを彷彿とさせます。この絵は、華やかな衣装を身にまとい、粉を塗った紳士たちが淑女たちの繊細な指に手を添え、宮廷指揮者が指揮する〈高雅なワルツ〉の音色に合わせ、優雅なカップルたちが踊る瞬間を描いています。』曲はイ短調。オクターブ混じりの右手旋律は豪奢な雰囲気ながら、そこはかとない哀愁が漂う。旋律と伴奏和音が合っていないと(短九度など)思わざるを得ない部分がいくつかある。 - Borboleta 蝶
楽譜の冒頭には『緑の草の中 / 白い蝶が舞う / 緑の草の中』と記されている。40秒ほどの短い曲。イ短調。冒頭にI度+V7度を重ねた謎めいた和音が鳴る。続いて、蝶がひらひらと舞うような16分音符がオスティナートで流れ、その上の高音部で「フルートのように」と記された旋律が彷徨うように奏され、何とも幻想的な調べである。最後は冒頭の和音がpで再び奏される。 - O camundongo Mickey ミッキーマウス
- A Baronesa 男爵夫人
- Passeio às Rocas ホカス通りの散歩
楽譜の冒頭には以下の解説が記されている。『ナタウの貧困地区の風景。地域色豊かなモチーフ。月明かりの夜、ホカス通りでは子供たちが遊んでいる。四つ角では、二人の若者がギターを弾いている。一人はセルタネージョを巧みにつま弾き、もう一人はありきたりな伴奏を弾いている。場面は消える。さらに先では、少女たちが石畳で遊んでいる「ボン・バルキーニョ、ボン・バルキーニョ、通させて…」。すぐに別の場面に移る。少年たちは輪になり、手をつなぎながら歌う「アリアンサ橋の上を、みんな通るんだ」。』曲の前半は嬰ト短調で、中音部でアルペジオ和音と悲しげな旋律が奏され、高音部に16分音符の分散和音が流れる。後半はロ長調になり、右手高音部分散和音の中から童歌「ボン・バルキーニョ」の旋律が奏される。また左手には別の旋律が奏される(これが童歌「アリアンサ橋の上を…」かは筆者は確認できませんでした)。 - Desfile de quintal 裏庭の行進
楽譜の冒頭には以下の解説が記されている。『子どもの頃、箒の柄のカービン銃と古いブリキの太鼓が鳴り響く裏庭の軍事パレードで、兵士や将軍を演じたことのない人はいるだろうか?この風景画は、そんなパレードの一つを描いている。小隊の指揮官はジョアンジーニョで、彼らが歌う行進曲に合わせて行進する。彼らは「ミネイロ・パウ」を歌い、行進のリズムに合わせて合唱隊が歌う。すると、華やかなパレードを中断させる声が聞こえる。指揮官の母親が彼を呼ぶ声だ。力強い2つの和音が響き、最初は前打音、次はペダルを用いて演奏され、これらは北部の人の歌声が「ジョアンジーニョ!」と呼びかけるという見事に明確な意図を伝えている。』楽譜はト音記号のみで書かれ、嬰ヘ長調。前半は勇ましくも可愛らしい行進曲は奏され、後半では付点のリズムの「ミネイロ・パウ Mineiro Pau」の旋律が現れる。「ミネイロ・パウ」は、かつてアフリカから連れてこられコーヒー農園で働かされた黒人奴隷たち由来の民謡で、木の棒を振りながら歌う。曲の最後は上述の解説通り、2つの和音が突然鳴り響いて終わる。 - Acalanto da "Bella Infanta" 美しい王女の子守歌
この曲は、リオグランジ・ド・ノルテ州に伝わる古い詩と歌〈美しい王女 Bella Infanta〉の旋律に基づいて作曲された。詩は、かつてイベリア半島で流行した「シャカラ xácara」という古代ポルトガル語の物語詩に基づいている。昔の詩の世界に想いを馳せるような趣深い曲である。ト短調。冒頭で〈美しい王女〉の旋律が静かに短音で奏される。続いて、楽譜に「子守歌のテンポ Tempo de Berceuse」と記された、揺かごのような左手オスティナートの伴奏が奏され、それにのって呟くような旋律が現れ、やがて〈美しい王女〉の旋律が再び奏される。 - Realejo 手回しオルガン
全曲楽譜はト音記号で書かれ高音部のみで奏されるので、オルゴールの音色にも聴こえる曲。嬰ヘ長調。冒頭は楽譜に「手回しオルガンのように Como se fosse um realejo de manivela」と記され、高音部の3拍子のオスティナートが流れる。9小節目から、その更に高音で旋律が16分音符音階混じりで奏される。高音部の旋律は途中で童歌〈未亡人 Senhora Dona viúva〉、モジーニャ〈お眠り、カルメラ Dorme Carmela〉が挿入される。
- Valsa nobre 高雅なワルツ
1940
- Dansa de indios (Dança de índios) 先住民の踊り
ワウデマール・ジ・アウメイダのピアノ曲の中でも最も民族主義がはっきりとした作品である。曲名は「先住民の踊り」だが、私にはアフロ=ブラジル音楽のようにも感じます。強いて言えば変ホ長調、A-B-C-A-B'-コーダの形式で、調性からはソナタ形式とも言えよう。A(第一主題)は野生的なリズムで低音ミ♭-シ♭が鳴り続けるのにのって軽快な旋律が奏される。旋律は時々多調の響きになることもあって面白い。初め中音部で呟くようにpで奏される旋律は、徐々に高音部へと音量を増しつつポリフォニックになり、変ロ短調のB(第二主題)になって左手オクターブに力強い旋律が現れる。C(展開部)は変ロ短調〜変ロ長調と転調しつつAの変奏が奏される。再び変ホ長調のAが再現され、続くB'では変ホ長調のままでffで右手オクターブ和音にBの旋律が現れ、両手オクターブ交互連打のコーダで終わる。 - Divertimento n. 1 ディヴェルティメント第1番
- Minuêto メヌエット
イ長調、A-A'-B-B-C-A"形式。曲名通り和音まで古典的な調べの曲。Aは3拍子4分音符の伴奏にのって上品な旋律が奏される。Bは流れるような8分音符の旋律が奏される。Cはイ短調になる。
1940-1941?
- Dança dos congos (1940?) コンゴの人たちの踊り
- Dança dos mamulengos 操り人形の踊り
- Divertimento n. 2 (1941) ディヴェルティメント第2番
- Divertimento n. 3 (1941) ディヴェルティメント第3番
- Divertimento n. 4 (1941?) ディヴェルティメント第4番
イ短調、A-B-A'-B'形式。終始、速いテンポの威勢の良い曲。Bはイ長調になり、B'は同じ旋律がイ短調で奏される。
1943
- Brincando com escalas 音階遊び
1944-?
- Noturno n. 1 em mi bemol menor (1944) 夜想曲第1番変ホ短調
ショパンの影響を受けつつも、独特の暗い雰囲気を持つ曲。A-B-A'形式。Aは8分音符分散和音の伴奏にのって陰うつな旋律が奏される。Bはテンポを速めて、急き立てるような3連符のモチーフが何度も繰り返しながら徐々に音量を増し、両手ユニゾンの急速な3連符が嵐のように奏される。A'は旋律がショパンの夜想曲のように装飾されて変奏され、消えるように終わる。 - Noturno n. 2 em mi menor 夜想曲第2番ホ短調
1948年頃
- Prelúdio n. 2 (1947?) 前奏曲第2番
- Prelúdio n. 3 (1948) 前奏曲第3番
- Prelúdio n. 4 (Homenagem a Debussy) 前奏曲第4番(ドビュッシーを讃えて)
1948
- Acalanto e modinha 子守歌とモジーニャ
モジーニャとは18~19世紀にブラジルで流行した歌謡曲のジャンルで哀愁溢れる曲が多い。A-B-C形式。Aは空虚五度の左手オスティナートにのって右手高音部に素朴な旋律が奏され、透明感のある調べである。Bはイ短調になり、モジーニャ〈最初の恋 Primeiro amor〉の旋律が高音部オクターブで奏される。Cは〈最初の恋〉の旋律が低音部に現れ、高音部には16分音符の対旋律が奏される。 - Toccata de Clô (Toccata) クロのトッカータ(トッカータ)
「クロ」とは、当時のリオグランジ・ド・ノルテ州知事Sylvio Pedrozaの妻であるClotilde Pedrozaの愛称である。Sylvio Pedrozaはワウデマール・ジ・アウメイダの知人で、Sylvio Pedrozaの兄弟や母はかつてワウデマール・ジ・アウメイダのピアノの弟子であった。1959年の出版譜では曲名から「クロ」が除かれ《トッカータ》となっている。曲はイ短調、A-B-A'-B'-C-A"-コーダの形式。全曲16分音符が途切れることが無く、ワウデマール・ジ・アウメイダのピアノ曲の中でも最もピアニスティックな曲である。Aは16分音符の両手交互打鍵が鋭い響き。Bは左手アルペジオにのって右手にオクターブの旋律が情熱的に奏される。A'は途中からハ短調になり、B'もハ短調である。Cは右手アルペジオの下で、左手低音部で新たなオクターブの旋律が現れる。
?-1957
- Invocação n. 1 祈り第1番
- Invocação n. 2 祈り第2番
- Invocação n. 3 (1953) 祈り第3番
- Invocação n. 4 (1957) 祈り第4番
1953
- Estudo n. 1 練習曲第1番
- Valsa nobre n. 2 高雅なワルツ第2番
イ長調、A-B-A'-C形式。Aは付点リズムの陽気なワルツが奏される。BとCは嬰ヘ短調になる。
1954
- Pastoral 牧歌
変イ長調、A-B-C-A'形式。Aは8分音符和音が優しく奏される。時々挿入される16分音符アルペジオ和音が増三和音で影を落とすような響きである。BはAの変奏で穏やかな雰囲気。Cは頻繁な転調の部分を経てA'に戻る。
1958
- Dança e canção da Rua dos Tocos トコス通りの踊りと歌
1959
- Dancinha 小さな舞曲
1960
- Fantasia para dois pianos ou piano e orquestra 2台ピアノまたはピアノと管弦楽のための幻想曲
1965
- Serenata na solidão 一人ぼっちのセレナーデ
作曲年代不詳
- Lenda 伝説
Waldemar de Almeidaのピアノ曲楽譜
Campassi & Camin
- Flôr de Belém, Valsa (o pseudônimo de Walmeida)
Casa Bevilacqua
- Flôr da tarde, Valsa lenta op. 2 (o pseudônimo de Walmeida)
- Flôr das ruínas, Valsa lenta op. 3 (o pseudônimo de Walmeida)
Irmãos Vitale
- Paisagens de leque, N.º 1. Valsa nobre
- Paisagens de leque, N.º 2. Borboleta
- Paisagens de leque, N.º 5. Passeio às Rocas
- Paisagens de leque, N.º 6. Desfile de quintal
- Paisagens de leque, N.º 7. Acalanto da "Bella Infanta"
- Paisagens de leque, N.º 8. Realejo
- Noturno
- Toccata
La fotolito (Roma)
- Dansa de indios
斜字は絶版と思われる楽譜
Waldemar de Almeidaのピアノ曲CD・LP
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。
Realejo, Oriano de Almeida interpreta Waldemar de Almeida (LP)![]()
RSLPC 7.002
 |
|
Oriano de Almeida (pf)
1969年の録音。
Marluze Romano interpreta Waldemar de Almeida (LP)![]()
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Projeto Memória-5, UFRN-005
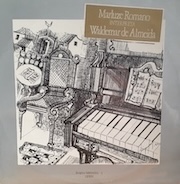 |
|
Marluze Romano (pf)
1983年の録音。
Compositores Potiguares![]()
- Royal cinema (Tonheca Dantas)
- Dagmar Duarte Dantas (Tonheca Dantas)
- Louca por amor (Tonheca Dantas)
- Camiho do céu (Severo Dantas)
- Saudades de Muriú (Benilde Dantas)
- Lembranças
- Falando ao coração (Maria Célia Pereira)
- Valsa rubra
- Palmilhando flores (Alexandre Brandão)
- Acalanto e modinha (Waldemar de Almeida)
- À sombra da velha jaqueira (Oriano de Almeida)
- Saudade do Potengi (Oriano de Almeida)
- No caminho do sertão (Oriano de Almeida)
Luiza Maria Dantas (pf)
Compositores Potiguares II![]()
- Caiçara do Rio dos Ventos (Oriano de Almeida)
- Da lontan (Paulino Chaves)
- Prece (Dolores Albuquerque)
- A dor calada é a mais sentida (Letícia Galvão)
- Yolanda (Clóvis Cussy)
- Amor em segredo (Paulo Pereira Simões)
- Sonho de amor (Teodorico Guilherme)
- Beijo da criança (José Sinésio)
- Triste e feliz (José Soares)
- Olhos (Abdon Trigueiro)
- Goló (Severo Dantas)
- Amor constante (Tonheca Dantas)
- Royal cinema (Tonheca Dantas)
- Caminho da glória (Alexandre Brandão)
- Alcanto da "Bela infanta" (Waldemar De Almeida)
Luiza Maria Dantas (pf)
2006年のリリース。Compositores potiguaresとは「リオ・グランデ・ド・ノルテ州の作曲家達」という意味。上記2枚のCDを聴くと、ブラジルにはまだ知られざるピアノ曲を作った作曲家がいて、当研究所もまだまだ調べることがあるということが分かります。
Brazilian toccatas and toccatinas![]()
![]()
- Toccata (Amaral Vieira)
- Toccata (Brasílio Itiberê)
- Toccata (Waldemar de Almeida)
- Tocata (Armando Albuquerque)
- Tocata (Radamés Gnattali)
- Toccata (Camargo Guarnieri)
- Toccatina, Ponteio e Final, Op. 12 (Marlos Nobre)
- Suíte acessível (Henrique de Curitiba)
- The Three Marias (Heitor Villa-Lobos)
- Tocata (Heitor Alimonda)
- Toccata (Cláudio Santoro)
- Tocata do Joezinho (César Guerra-Peixe)
- Tocata (Bruno Kieffer)
- Toccata da Alegria (Almeida Prado)
- Toccata (Ronaldo Miranda)
Vânia Pimentel (pf)
2000年の録音。
Waldemar de Almeidaに関する参考文献
- Antonio Guilherme Cardoso Rodrigues e Erickinson Bezerra de Lima. Paysagens de Leque de Waldemar de Almeida (1904-1975): uma nova edição. Revista Vórtex, Curitiba, v.5, n.3 2017.
- Claudio Galvão. O nosso maestro: biografia de Waldemar de Almeida. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 2019.