Antonio María Valenciaのページ
Antonio María Valenciaについて
Antonio María Valencia Zamorano(アントニオ・マリア・バレンシア・サモラーノ)は1902年11月10日、コロンビア南西部の都市のカリに生まれた。父親のJulio Valenciaは、作曲家ペドロ・モラレス・ピノが率いる楽団「リラ・コロンビアーナ(Lira colombiana)」のチェロ奏者で、父から音楽を教わったアントニオ少年は9歳の時には地元でピアノリサイタルを開いている。13歳の時には、"Himno al Regimiento Ricaurte de Bogotá" という歌曲を作り、作曲コンクールに応募している。14歳の頃にはパナマと米国南部に演奏旅行をしている。1918年(15歳)で首都ボゴタの国立音楽院に入学し、ピアニストのHonorio Alarcónに師事し、本格的にピアノを習った。
1923年ーちょうど20歳の時、バレンシアはコロンビア政府より奨学金を得て、国立音楽院院長のギジェルモ・ウリベ・オルギンの勧めによりフランスに留学。パリのスコラ・カントルムに入学しヴァンサン・ダンディに作曲を、ポール・ブローにピアノを師事した。優秀な成績でピアノのディプロマを取得し、また1927年3月にはパリのサラ・エラールでデビューリサイタルを催した。(このリサイタルの演目は、バッハの平均率に始まり、シューマンのダヴィッド同盟舞曲集、ドビュッシーの喜びの島などが演奏され、締めはアルベニスの組曲イベリアより「セビリアの聖体祭」「トゥリアーナ」と意欲的なプログラムだ!。)
パリに6年間滞在し、バレンシアはコンサートピアニストとして活躍、1929年にはスコラ・カントルムのピアノ科教授の就任を要請されるまでになったが、同年9月コロンビアに帰国。翌1930年にはボゴタの国立音楽院教授に就任したが、家族の事情などで間もなく国立音楽院教授を辞めて故郷カリに戻り、1933年にはカリ音楽院を創立し、自ら院長を務めた。1936年に再びボゴタに移り、ギジェルモ・ウリベ・オルギンの後を継いでボゴタの国立音楽院院長に就任したが、カリ音楽院との両方の音楽院院長職はさすがに無理があったらしく、約一年で国立音楽院の方は辞職している。
その後もバレンシアはピアニストとして国内外で活躍しつつ、カリでは、1940年にカリ音楽院交響楽団を創立し、カリ音楽院院長職も1951年まで続けた。
バレンシアは1952年7月22日にカリで死去。まだ49歳であったが、晩年はモルヒネ中毒だったとのこと。
バレンシアは、10代の頃からパシージョなどの民族舞踊を用いた作品を作っていて、パリ留学直前の1923年には民族主義的なヴァイオリン曲 "Danza colombiana" を作曲している。留学中の作品にはフランス印象主義の影響が強く見られ、更にコロンビア帰国後の後期の作品は、コロンビア人らしい民族主義とフランスで会得した高度な作曲技法が昇華したとも言えるような作品群が多い。バレンシアはいろいろなジャンルの作品を作ったが、中でも力を入れたのが宗教曲で、混成四部合唱のための "Misa breve de Santa Cecilia" (1941)、"Requiem" (1943)、混成四部合唱・オルガン・管弦楽のための "Himno eucarístico" (1946) などが代表作。合唱曲ではコロンビアや近隣南米諸国の民謡を元にした作品があって、ピアノと混成四部合唱曲 "Coplas populares colombianas"、ペルー民謡による混成四部合唱曲 "Kunanti-tutaya"、エクアドル民謡によるテノールと男声五部合唱曲 "El peregrino"、ボリビア民謡による混成三部合唱曲 "Pastoral" などがある。歌曲も多数作曲している。管弦楽曲は少ないが、フルート協奏曲 (1917)、ハープ協奏曲 (1937)、管弦楽のための "Chirimía y bambuco sotareño" (1942、原曲はピアノ曲) などがある。室内楽曲では木管五重奏曲 (1935)、ピアノトリオ "Emociones caucanas" (1938年完成) などがあり、またいくつかのヴァイオリン曲も作っている。
バレンシアのピアノ曲は、パリ留学以降に作られた作品が、数は少ないが聴き所である。ドビュッシーなどの印象主義と、コロンビアの民族音楽を融合した見事な作品となっている。1936年以降は音楽院院長職やピアニストとして忙しかったのか、ピアノ曲が作られていないのが残念であり、コロンビアの作曲家らしい大曲を作ってくれたならな〜と思わずにはいられません。
Antonio María Valenciaのピアノ曲リストとその解説
1916
- Soledad, Vals 孤独、ワルツ
ニ長調、A-A-B-B-C-C-Aの形式。右手三度重音の旋律が明るい雰囲気の、サロン風ワルツ。Cはト長調になる。
1917
- Pasillo パシージョ
変ホ短調、A-B-A-B形式。Aは感傷的な旋律がオクターブや三度重音で奏される。Bは右手8分音符の分散アルペジオの中から旋律が浮かび上がる。 - Palmira, Pasillo パルミラ、パシージョ
パルミラは、コロンビア南西部のバジェ・デル・カウカ県にある町の名前。変イ長調、A-B-C-D形式。パシージョのリズムが浮き浮きするような陽気な曲。BとDの部分は高音部を舞うような8分音符の旋律が華やか。Cはロ長調になる。
1918
- Pasillo Nº 4 パシージョ第4番
1919
- Pasillo Nº 6 パシージョ第6番
- Mazurca triste 悲しいマズルカ
1922
- Vals ワルツ
1924
- Choral varié (à la manière de Bach) 多彩なコラール(バッハ風に)
1925
- Berceuse 子守歌
変ホ長調。ゆったりとした3連符のアルペジオにのって、微睡みを誘うような旋律が奏される。sus4や増三和音の使用とか、ほとんど毎小節転調すると言ってもいい位の和音の移ろいが、夢の世界のような何とも幻想的な雰囲気を醸し出している。28小節目で最初の変ホ長調に戻り、冒頭の旋律が回想され、静かに曲は終わる。 - Suite 組曲
- Fantaisie avec Fugue 幻想曲とフーガ
- Allemande アルマンド
- Minuet メヌエット
- Sarabande サラバンド
- Rondeau ロンド
- Giga ジーグ
- Sonatina en Do Mayor ソナチネハ長調
1926
- Élégie エレジー
- Neblina 霞
1927
- Ritmos y cantos suramericanos Nº 5 南米のリズムと歌第5番
- Ritmos y cantos suramericanos Nº 8 南米のリズムと歌第8番
- Impromptu 即興曲
変ロ短調、A-B-A形式。全音音階などを多用した幻想的な小品。Bは概ね変ト長調になる。 - Aube estivale 夏の夜明け
当時パリ留学中のバレンシアは、ピアニストのポール・ブローにピアノを師事していた。ポール・ブローはパリ郊外のGazeranという所に別荘を持っていて、その別荘の名を "Les Éolides" としていた。ちなみに、"Les Éolides (アイオリスの人々)" とは、詩人Leconte de Lisle (1818-1894) の書いた詩の一つで、またセザール・フランクはこの詩を元にして交響詩 "Les Éolides" を作曲している。バレンシアは別荘 "Les Éolides" に度々泊まっていたとのことで、この曲の自筆譜に "Les Éolides, 17 Agosto 1927" と記されている事からも、バレンシアがその田舎の夏の夜明けの光景に魅せられてこのピアノ曲を作ったものと思われる。一分半ほどの短い曲でト長調、A-B-A-B-A形式。田舎の夏の夜明けの清々しい空気が漂うような曲で、8小節の主題が奏された後は、数小節毎に次々と転調していくのが夜明けの空の色が変わっていくのを描写しているようで色彩的な響きだ。増五度の和音も現れ、印象主義風の響きでもある。最後に冒頭の主題が繰り返され、静かに曲は終わる。 - Mazurka pour endormir mon bebé 赤ちゃんのおやすみのためのマズルカ
たった2時間半で作曲された曲らしい。変ロ短調、A-A-B-B'-A-コーダの形式。高音部ユニゾンの物悲しいモチーフに引き続き、マズルカのリズムを刻む左手伴奏にのって、8分音符が上へ下へと舞うような旋律が奏される。Bは変ホ長調で始まるが、転調を繰り返す。
1929
- Bambuco "del tiempo del ruído" バンブーコ「騒音の時」
"tiempo del ruído" が具体的に何の騒音を指しているのかはっきりしませんが、コロンビアで "tiempo del ruído" と言うと、1687年3月9日の夜にボゴタの街全体に響き渡った原因不明の大きな騒音の言い伝えが有名である(この大きな騒音の原因は、遠くの地震か火山爆発のためか、はたまた悪魔の叫びかと諸説あり)。またこの曲はバレンシアが子供の頃、母と叔母が弾いていた古いバンブーコの旋律を元に作ったらしいです。一応ホ短調。三度重音のモチーフが7小節現れた後、サパテアードの踊りを思わせるような軽快なリズムが続き、所々バンブーコらしい旋律や冒頭のモチーフも挟まれつつ進む。軽快なリズムは高音で変奏されたり、右手と左手でヘミオラになったりと面白い響きの曲だ。 - Chirimía y bambuco sotareño チリミアとソタラのバンブーコ
前作同様、バレンシアがフランス留学を終えてコロンビアに帰国した直後に作られた、言わばフランスで学んだ作曲技法と、コロンビア民族主義が合体した作品である。曲は "Chirimía" と "bambuco sotareño" の二部から成る構成。前半のChirimíaとは、中南米の民族楽器でオーボエに似たダブルリードの木管楽器のことだが、コロンビア南西部の太平洋岸地方(カウカ県など)では民族楽器の合奏のこどを指すらしい。左手低音にppで始まる付点リズムのオスティナートにのって、右手にチリミアの調べを思わせる旋律が奏される。調性は一応ハ長調だが、「ファ」抜きのヘキサトニック旋法である。この旋律は変奏されつつ変ホ長調や変ロ長調で繰り返される。後半のbambuco sotareñoは「ソタラのバンブーコ」という意味で、ソタラはカウカ県東部のソタラという村の名前。コロンビアの作曲家Francisco Diago (1867-1945) が作った "El sotareño" という民謡をバレンシアは元にしている。ハ短調で、"El sotareño" が哀愁たっぷり奏されるが、旋律はポリフォニックで和声も複雑の凝った作りだ。拍子も12/16で始まるが、10/16〜11/16〜13/16と次々と変わっていく。最後はハ長調になり、クレッシェンドしてffで終わる。この作品は、後の1942年にバレンシア自身により管弦楽曲にも編曲された。
1935
- Sonatina boyacense ボヤカのソナチネ
1935年、チリ出身の名ピアニストであるクラウディオ・アラウがコロンビアに演奏旅行に来ていた。アラウは前年(1934年)に、ベネズエラの作曲家バウティスタ・プラーサの作曲した "Sonatina venezolana" というピアノ曲を献呈されていた。バレンシアはカリでアラウに会い、"Sonatina venezolana" の楽譜を見せてもらったらしい。この曲に触発されてバレンシアが同年作曲したのが、Sonatina boyacenseとのことである。ボヤカとはコロンビア中部の県名。3/8拍子の軽快な曲で、九度や増五度の和音が多用されているのは印象主義風だが、コロンビアらしいパシージョやバンブーコなどのリズムや哀愁ある旋律などがいい雰囲気だ。一応ニ長調、ソナタ形式。第一主題は右手に分散和音の主題が爽やかな響きで奏され、左手に1小節遅れて主題の反行形が追い、パシージョのリズムが挟み込まれる。バンブーコのリズムが静かに鳴らされると、第二主題に移り、嬰ヘ短調のヘキサトニック音階の民謡風の旋律が高音部に現れる。この旋律のリズムはコロンビアの民族舞踊グアビーナらしい。展開部は14小節のみで、パシージョのリズムや第一主題の断片が展開される。再現部はイ長調の第一主題、ニ短調の第二主題と奏され、最後は急にニ長調になって終わる。
1936
- Preludio 前奏曲
Antonio María Valenciaのピアノ曲楽譜
Fondo Editorial Universidad EAFIT
 |
|
Cali: Corporación para la Cultura
- Imagen y obra de Antonio María Valencia, Volumen II por Mario Gómez-Vignez
Editorial Universidad del Valle
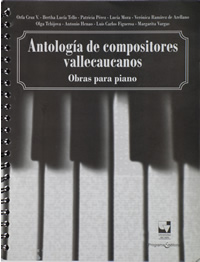 |
|
Antonio María Valenciaのピアノ曲CD
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Antonio María Valencia, Obras de cámara y obras para piano![]()
Banco de la República Colombia
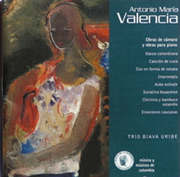 |
|
Trío Biava Uribe: Luis Biava (vn), Luis Gabriel Biava (vc), Blanca Uribe (pf)
2002年の録音。
Tiempo de piano - Música para piano de compositores colombianos del siglo veinte![]()
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia
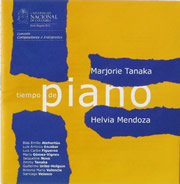 |
|
Marjorie Tanaka (pf), Helvia Mendoza (pf)
Latin American Dances![]()
![]()
Intim Musik, IMCD 061
- Brejeiro (Ernesto Nazareth)
- Dança de Negros (Fructuoso Vianna)
- Danzas Cubanas (Ignazio Cervantes)
- Tango (Marlos Nobre)
- Congada (Francisco Mignone)
- Tango (Francisco Mignone)
- Frevo (Marlos Nobre)
- Milonga (Alberto Ginastera)
- Jongo (Lorenzo Fernandez)
- No Puedo Contigo (Ernesto Lecuona)
- Tango Brasileiro (Alexandre Levy)
- Bambuco (Antonio Valencia)
- Galhofeira (Alberto Nepomuceno)
- Odeon (Ernesto Nazareth)
- Dança Negra (Camargo Guarnieri)
- Tango, arr. Godowsky (Issac Albeniz)
- Farrapós (Heitor Villa-Lobos)
- Dança Brasileira (Camargo Guarnieri)
- À la Cubana (Enrique Granados)
- Tres Danzas Argentinas (Alberto Ginastera)
Clélia Iruzun (pf)
1998年の録音。
Fresco![]()
![]()
KyG Productions
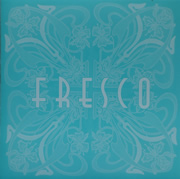 |
|
2011年のリリース。